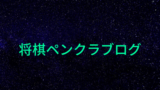YouTubeチャンネル「将棋伝説」、225本目の動画は「二・二六事件の日の対局」です。
1936年2月26日の未明、二・二六事件が勃発しました。 この日は、関根金次郎名人-木村義雄八段戦、土居市太郎八段-大崎熊雄八段戦が行われていました。 今回は、二・二六事件の日の将棋連盟の様子などを見ていきます。
* * * * *
「将棋伝説」チャンネル、今後も動画が増えていく予定ですので、よろしければ、チャンネル登録をお願いいたします。
→「将棋伝説」
* * * * *

二・二六事件の日の対局
1936年2月26日の未明、二・二六事件が勃発しました。この日は、関根金次郎名人-木村義雄八段戦、土居市太郎八段-大崎熊雄八段戦が行われていました。今回は、二・二六事件の日の将棋連盟の様子などを見ていきます。将棋ペンクラブログ→→