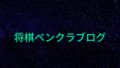YouTubeチャンネル「将棋伝説」、180本目の動画は「その王手飛車が敗着でしょ」です。
「プロの対局では、王手飛車取りをかけたほうが負ける」という話をよく聞くことがあります。
今回は、その典型例と言える局面を見ていきます。
* * * * *
「将棋伝説」チャンネル、今後も動画が増えていく予定ですので、よろしければ、チャンネル登録をお願いいたします。
→「将棋伝説」
* * * * *

「その王手飛車が敗着でしょ」
「プロの対局では、王手飛車取りをかけたほうが負ける」という話をよく聞くことがあります。今回は、その典型例と言える局面を見ていきます。将棋ペンクラブログ→→