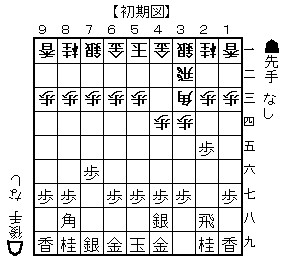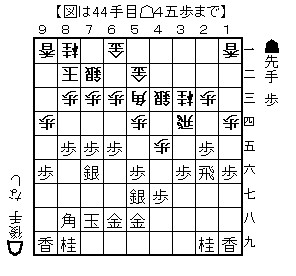日経の勝村実記者「王座戦は中原防衛 光る加藤(一)八段のがんばり」より。
この頃の王座戦は三番勝負で、中原王座が二-〇で防衛している。勝村記者の加藤一二三八段についての記述は、今の加藤一二三九段を彷彿させてくれる。
「その加藤(一)八段が今期の挑戦権をにぎる前は、例年にない不調であった。だいたい棋風は仕掛けがおそく、じりじりとわずかなポイントをかせぎ、その積み重ねで指す方式だから、将棋は長くなる、時間はなくなるで、周囲をはらはらさせるむきがある」
意外と大胆な書き方だ。
「加藤(一)八段が挑戦権をかけた最後の一番はたいへんな戦いだった、おそらくそれは、一つの記録であると思う。相手は長谷部七段。昨年からぐんぐん勝率をあげている。棋風は加藤と同じように読みきれぬ手は指さぬ慎重型」
当時、私は子供だったが、少しイヤな予感がした。
「その二人が、がっちり組んで中盤手詰まり。明らかに千日手模様となった」
子供心に、そのような二人が対戦するのなら、そうだろう、そうだろうと思った。
「長谷部七段は動く事ができない。加藤八段は打開することができる。加藤八段は同一手順の反復を千日手の一歩前でやめて別の反復手段に移るのだが、その打開手順発見のための努力は午後十時から午前一時までの三時間におよんでいる。手順なしとみて、千日手に踏み切ったのは深夜、午前一時半であった」
当時、私は鼻の調子が悪くて、耳鼻科へ行かなければと思っていたのだが、急に鼻が重苦しく感じられてきた。
「そんな次第で、指しも指したり480余手。平均手数の四局分の長さとなった。千日手指し直しは午前二時三分から。こうした想像を絶する時間のスタートは、千日手規約改正の産物。それに伴う悲劇第一号局というべきであろう。この将棋の手数が220余手。終局は午前六時をまわり、気づいたときには朝の白さが目に痛かった。」
頭も重くなってきた…
「二度の詰めを逃した長谷部七段には、悔いが残ったことと思われる。が、これだけ戦えばいうことないのか、表情に無念の色をみせないところ、すっきりしたものを感じた。それもさることながら、疲労と非勢の中に寸隙をとらえてハネ返す力を残していた加藤八段にはびっくり。これも根性の男というしかない」
この文章を読んだ翌週、私は耳鼻科に通いはじめた。実話です。