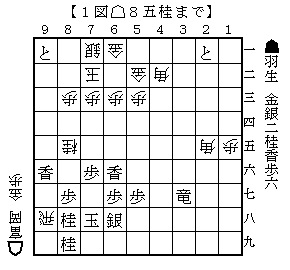将棋世界1983年2月号、故・能智映さんの「棋士のたのしみ」より。
半年ほど前だったか、『週刊現代』のグラビアで”勝負師たちのちょっといい表情”の解説文をたのまれたときにはまいった。
将棋記者として書いてはみたい。しかしだ、永年にわたって棋士を撮り続けてきたカメラマンの炬口勝弘氏、弦巻勝氏の写真は”ちょっといい”どころかあまりに露骨だ。
芹沢をはじめ、周りのものに相談したら「なんでも頼まれたら、やる一手!」という。こわごわ書いたら、「もうちょっと刺激的に」と週刊誌のほうから注文がついた。商売で”文字”を売っている身だから当然なおした。だが、ゆるされなかったか。「もうちょっと手を入れていいですか?」と聞かれた。「いいよ」というのが、気にせず、気まぐれなわたしの主義だ。
それでも、実は週刊誌の校了から発売まで気が気ではなかった。
その雑誌が出たのは、ちょうど名人就位式の前日だったかと思う。加藤の謝辞も良かった。明るい席だった。
見た人に文句をいわれそうだったので、やや逃げ気味だったのだが、そこで佐藤大五郎八段につかまってしまった。―少々恐れていたのだが、にこやかに話かけてきた。
「週刊誌で見ましたよ。わたしのことを書いてくれていますね」 ―けっこう、ごきげんな顔である。まだいう。
「ファンの人たちから、いろんな情報が入ってくるんですよ。でも、こんどはよかったですね。内藤さんの上にわたしがあって(誌面ではたしかに佐藤のほうが上になっている)、しかもファッションをほめてくれている。数十万円のベルベットの背広や、800万円の金時計はほんとですがねえ―」ときた。
こういうときはあとのせりふにトゲがあるのが普通だ。また逃げ腰で聞いた。やっぱりぴしゃりときた。
「でもね、あとに”もっぱら池袋のキャバレーでもてている”ようなくだりがあったのは少しばっかり気になったよ。最近は高級クラブへ行くことが多いからね」
いつきびしく詰め寄られるかと思ったが、それでも気のいい大五郎氏は笑顔をたやさない。ちょっぴり気取りながらいう言葉がよかった。
「それでもねえ、高級クラブなんて書かれちゃうと生意気に見えて、ファンから浮き上がっちゃうからね」。わたしもけっこう気を遣っているのだが、本人たちもこれほど細かく気を回しているのである。
同じ就位式の日に花村元司九段もいた。対局相手を背にしてお金を勘定している写真が同じ週刊誌に出た。わたしはふざけて「どこの競輪場の配当ぞ?」と書いた。これもヤバイと思っていたが、「気にしなさんな、なにを書かれてもへっちゃらや。ハハハハハ」とふとっ腹に一蹴された。実は、まだ読んでいないらしいのが、いかにも花村らしいところだ。
しかし、思わぬところでつかまった。真部一男七段である。これにはわたしもとまどった。自分が書いただけに、よく読んでいなかったが「男性が熱を上げる男性」のようなことが書かれていた。
「あれはひどいよ」と笑いながら抗議されたが、ほんとういって、わたしにはまったく身におぼえがなかった。真部はさらに、「女房に『やっぱりねェ』といわれちゃいましたよ」と詰め寄ってくる。
そんな感じを真部から受けた気がぜんぜんないのだからおかしい。―調べてみると、担当者が文章をおもしろくするために、一部分書き加えていたのだ。よくあることだ。
真部が笑いながら抗議していたので、これはそれほど気にしていなかった。ところが、こんどは当日家に帰ったとたんに芹沢から電話があった。
「あの週刊誌見たよ。うちのカミサンが怒ってるぞ!」というのだ。芹沢自身ならまだしも、和子夫人に怒られては、芹沢家に出入りできなくなってしまう。実際、あわてたが、ここは落ち着いて聞くべきだ。
「カミサンがテレビの”目方でドン”に出たとき、どんぶりめしを2杯喰って、出すものも出さずにハカリに直行した。屠殺場に向かうブタじゃあるまいし―、なんて書いただろ?あれでカンカンだよ」
だが、いいわけさしてもらえば、それは芹沢自身の口から聞いた言葉だ。―ヤバイとは思いながら、次の言葉をまっていると、やにわに女の声に変わった。もう逃げる手だてはない。観念して聞くことにした。まぎれもなく和子夫人の声だ。
「いえ」といった。続いてどんな怒声が出てくるかと身構えた。
「うそですよ。わたしはこの人に怒っているんですよ。ほんとにそう思っているから、そんなことを人前でしゃべるんですよね」
しかし、書かれている行動については、うそともほんとうともおっしゃらなかった。だから、わたしはまだ半信半疑でいる、などと書いたら、まだ電話がリーンと鳴るのか。
いろいろと話題豊富だった。そのグラビアは異例ともいえる8ページ。だから、彼らは口をそろえていうのである。
「これだけ大きく取り上げてくれると、将棋界の宣伝に役立つね。これ、広告代にしたらいくらになるんだろうか?」
将棋指したちの発想は、どこまでもユニークだ。
(中略)
少々理屈っぽい話が続いてしまった。だが、将棋指したちはおおむねおおらかに応対してくれる。連盟の中でわたしが耳をそば立たせていると、だれもが「また書くんでしょ!」と明るい笑いを見せてくれる。
内藤國雄王位など、対局の前夜や打ち上げの宴で神戸組の情報をいろいろとしゃべってくれて「これ書いちゃあかんで」「これは書いてええわ」などとサービスしてくれるし、中原誠前名人も「おかしいんだよね」などと話しかけてきて、ときどきおかしなネタを提供してくれる。
ちょっと恐ろしかったことがある。大柄で坊主頭の小堀清一八段が、「あのうー」といって寄って来た。普段あんまり付き合いがないので、「こりゃあ、まずいな!」とさとった。その話の前にわたしは、この”棋士の楽しみ”の「将棋界はゆかいな動物園」の中で、小堀さんと33匹のネコ(?)のことを書いた。それへの抗議かと思って、一瞬たじろいだ。
ところがである。あの白髪の温かみのある(見方がこう変わるから記者なんていうのは当てにならない)顔が、ぐっとほころんでいる。小堀、ゆったりと笑みを見せてこういうのだ。
「ありがとうございました。わたしのことをいろいろ書いていただいてありがとうございました」―明治の人だけにまことにていねいである。「いや」といってまた思う。―あの取材は小堀本人にはせずに、電話で妹さんにしたはずだが―と。気恥ずかしかった。
「ネコに代わって、わたしはお礼をいいますよ」と八段がいっているように聞こえたが、本気であることは、その顔に出ている。なぜなら、少し腰をひいた形のわたしには、小堀のやさしそうな顔と白髪が白ネコに見えたのだから―。
すこし変わっているのは板谷進八段で、会うたびに「あんたは、ひどいことばかり書くから少々お世辞をつかっとかないかんわ」などといって、ループタイやネクタイ、ウイスキーなどをプレゼントしてくれる。―こっちが書かせてもらっているのだから、まったく立場は逆なのだが、田丸昇七段など、わたしを横目でじろりと見ながらいうのである。
「書いていただくだけでいいじゃないの!」
もっとも、いつか中原に「週刊誌などにいろいろ書かれていやでしょうね」と聞いたら「いや、変なことが書いてありそうだと、見出しを見れば想像がつくんで読まないことにしているんです」とケロリといっていた。もっとも、対照的に妙に風変わりな人もいる。
「そうそう今週の『週刊◯◯』にわたしのことが出ていますから読んでおいてくださいよ」―ものにこだわらない米長だ。
ところがである。冒頭に書いた事件のあと、ご招待に応えて米長家を訪問したら、意外なところから手ごわい抗議を受けた。
「どうぞ」という明子夫人の声に上がるやいなや、長女の喜美子ちゃん(中学1年)が「将棋世界」の前年9月号をかかえてきていうのである。
「ここにわたしと(林葉)直子ちゃん(4級)が先崎君(1級)をいじめた様子が書かれているけど、あれはちょっと違うんです!」
助け舟が欲しいところなのだが、意地悪く明子夫人はニヤニヤ笑って素知らぬ顔。米長はむしろ逆に「怒れ、怒れ!」とけしかける始末だ。いっこうに漕ぎ出してこない。<あるいはこのためにわたしを呼び出したのか>と思えるほどきびしい追求だったが、これでいい。この可愛い抗議はうれしかった。彼女もわたしの文を読んでいてくれたのだから―。しかし、またもう一度、自らの仕事を見つめ直さなくては、と痛感したものだった。
——–
「薪割り大五郎」と呼ばれた故・佐藤大五郎九段。
棋風も豪快だったが、遊び方も豪快だった。
この時代、池袋は現在とは違って、かなり場末のイメージで捉えられていた。
そういう意味では、「池袋のキャバレー」というのは、当時では「銀座のクラブ」「六本木のクラブ」の対極に位置する概念の店ということになる。
——–
故・花村元司九段もとても花村九段らしい情景。
棋士になる前の花村九段は博打全般を得意としていたが、1948年以降は、競輪のみが唯一の趣味の賭け事だった。
——–
故・真部一男九段は当時の美男子棋士の代名詞だった。
「男性が熱を上げる男性」と書かれたのも、税金のようなものと言うことができるだろう。
——–
「将棋学徒」と呼ばれた腰掛銀の鬼・故・小堀清一九段。
内藤國雄九段、神谷広志八段など、棋士には猫派が多いような感じがする。
——–
たしかに、書くということは、いろいろと難しい。