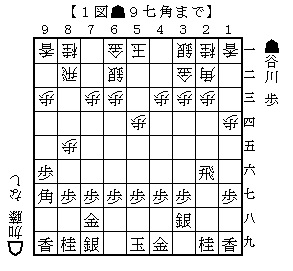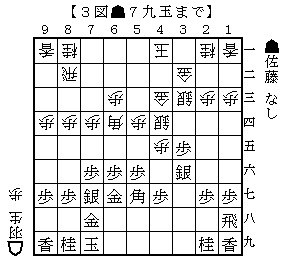倉島竹二郎さんの「昭和将棋風雲録」より。
いつのほどからか、私はほとんど将棋を指さなくなってしまった。10数年前、NHKのテレビ放送で加藤治郎八段(当時)に角落将棋を教えてもらったが、専門家と指したのはそれが20数年ぶりのことであった。文壇将棋大会でも行司をつとめて、もっぱら世話役にまわっていたし、将棋会館に出かけても、手ごろな相手を見つけて囲碁ばかり打っている。といって、将棋に興味を失ったわけでは毛頭なく、むしろ将棋の醍醐味は年とともに加わってくる気がするのだが、周囲に好敵手がいなくなったのと―いや、ほんとうは、名人上手の勝負をもっともらしく解説批評している手前「何だ、こんなヘボ将棋だったのか」と思われたくないという、ケチな職業的見栄のなせるわざなのであろう。
が、市川時代はだれかれの見境なくよく指した。付近には大崎八段後援会の免状持ちの旦那衆がかなりいて相手にことかかなかったし、大崎邸でも、内弟子の藤川義夫君や林勝三君、それに太期喬也君などに挑戦して、バット(莨)1、2個の小さい真剣(賭け)で指してもらった。駒割りは何であったか忘れたが、素人なかまではそうとう強いとうぬぼれていた私も内弟子諸君には歯が立たず、いつも莨を取られっぱなしで、世間ではまだ一人前の棋士とは見られなくても、その道に一生を賭けた人間の心構え―根性の相違といったものをじみじみとさとらされたものである。
一度、溝呂木七段とも真剣で指したことがある。蛎殻町の溝呂木邸に観戦に出かけた節、溝呂木さんから「腕だめしに僕と二枚落ちで指してみないか、君が勝ったらご馳走するよ」とすすめられた。二枚落ちならなんとかなるだろうと思った私は「先生から逆に片褒美(一方だけから褒美なり懸賞なりを出すこと)では申しわけない。負けたら私の方からもご馳走します」と私は意気込んでいった。その将棋はうまく私が勝った。溝呂木さんは「思いのほか強いな」と、ほめ、ご馳走のかわりだといって、よく使い込んだ榧の盤と黄楊の駒、それに駒台までつけて私にくれた。溝呂木さんは人形町生まれの生粋の江戸っ子であり、前身は唐物問屋の若主人だというほどあって、旦那気質の粋なところのある人で、後で思うと、私がいつか板盤とチャチな駒しか持っていないことを話したのを覚えていての、勝負にかこつけての心づくしであったのかもしれない。
——–
倉島竹二郎さんが溝呂木七段邸で観戦をしていたのは、昭和7年から昭和10年までのこと。
——–
莨はタバコ。バットはゴールデンバットの通称。
現在も20本入りで210円で販売されている。(通常のタバコの半分ほどの値段)
——–
何の前触れもなく榧の盤と黄楊の駒をプレゼントされれば、もらった方も心の負担になる。というか、前触れがあっても心の負担になる。
溝呂木光治七段は、真剣勝負を相手の心の負担を減らすクッションにしたわけで、まさしく人生の達人と言ってよいだろう。
——–
無粋な話で恐縮だが、現代の法律では、真剣勝負は法律違反となるが、片真剣(一方は負けても何の債務を負わない)は法には触れない。
最後の真剣師・大田学さんが通天閣道場でやっていた指導将棋。太田さんに勝ったら只、太田さんに負けたら指導料500円を支払う、太田さんは負けても何も支払わない。これが将棋の片真剣の近世の事例。