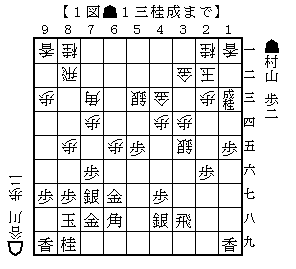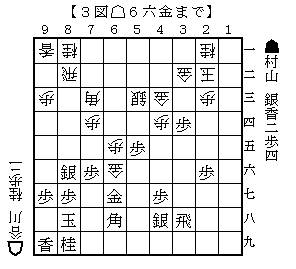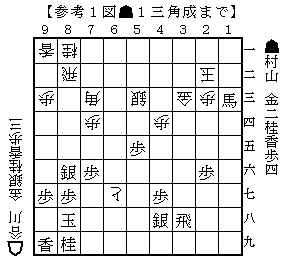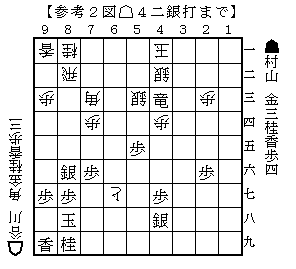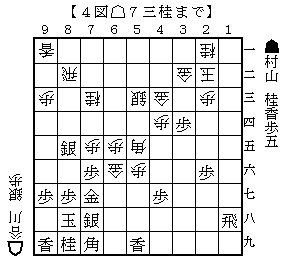将棋世界1993年4月号、中野隆義さんの第42期王将戦第4局(谷川浩司王将-村山聖六段)観戦記「聖よ、もっと爪を伸ばせ」より。
「終盤は村山に聞け」という物言いが耳に入ってきたのは、村山がデビューして間もなくのことであった。関西将棋会館の棋士室で、数人の棋士が棋譜を並べたり現在進行中の対局を検討する。そんな時に、終盤の詰むや詰まざるやの局面になったら、村山に尋ねればまず間違いなしというのだから、これは棋士室の主というか神のようなものである。
最近では「褒め殺し」なる技が出てきているが、勝負する者は、押し並べて相手のことを褒めたりはしないものである。お世辞のつもりでお上手を言ったら、自信をつけさせることとなり、本当に強くさせてしまう結果ともなりかねないし、何よりも、そう簡単に後輩を認めてしまうのは、先輩としてまたプロとしてのプライドが許さぬことである。それなのに、村山の終盤の読みの深さと正確さを認める冒頭の言葉が生まれたというのは尋常なことではないのである。
村山の大物ぶりを目の当たりにしたのは数年前のこと。東京での対局を明日に控えた村山が、夕刻の「桂の間」に所在なげな風をして入って来た。部屋ではいつものように、その日の将棋が継ぎ盤に並べられ、棋士や奨励会の連中が健闘を重ねていた。
村山が来た瞬間、部屋に「うおっ」という感じの空気の揺れが起こった。皆、関西棋界の怪童・村山を意識している。誰かが「さっ、丁度いいところです。ここに座って。さっ、どうぞ」と盤側に手招きをしたが、村山は、検討の輪には加わるそぶりも見せず、部屋の隅に体をくずおれるようにして腰を下ろした。
局面は、終盤の大詰めを迎えていた。形勢不利と見られた側が必死の勝負手を放ち、優勢側を見る間に受けなしに追い込んだ。しかし、そのために駒を山ほど手渡してもいる。
「これは、詰むよねえ。さすがに」
「でも、変に詰ましにくい格好かもしれない……ね」
”待った”が利く継ぎ盤では、何度も何度も即詰の順を目指しては現局面に戻すことを繰り返した。
「ね。村山くん。どお」
村山より先輩格の棋士がタイミングよく声をかけ、皆の視線が一斉に村山に向けられた。
ものうげに身を起こした村山は、顔だけを盤面の方に近付ける。盤と村山との空間をさえぎっていた棋士がのけぞって村山のために視界を開いた。目を細めたまま、数秒盤面を見遣ると、村山は一言「詰みます」とだけ言って再びだるそうに身を沈めた。つまらんもんを見ました、と顔に書いてある。
「ほんとに詰むの。村山君」
「……」
「ねえ、どうやるのかな」
「詰みます」
「……」
部屋には、険悪な雰囲気がちらと見えてくる。村山の力を見ようという下心半分の気持ちを見透かされた上に、バカにされかかっているかのようなやり取りである。
「ねえ、ほんとに詰むんだったら、どうやって詰ますのかなあ。教えてよ、どうやったら詰むのかなあ」
おどけてはいるが、マジに答えなかったら許さんゾの気合が籠っている。
こりゃ、面白いことになってまいったぞと聞き耳を立てる記者のその耳に入ってきた言葉は、信じられないものだった。
「どうやったら詰まないんですか」
スコーン。と満塁ホームランを場外まで持って行かれる音が、頭の中でした。こりゃ、モノホンだ。すげえのが出てきたな。と、思ったものである。
(中略)
東京から広島まで新幹線で約4時間。山陽本線の各駅停車に乗り換えて1時間と少しで山口県の大畠駅に着く。飛行機が大の苦手である記者は、一人で動く場合はまずほとんどが地を這って行く。
3局を終えて谷川3-0のスコアは意外であった。村山が3局とも終盤で勝ち筋を見逃すという負け方をしているのも解せないことである。勝負が終盤に持ち越される展開になれば村山に十二分に勝機があると踏んでいただけに、もっとも恵まれた流れにありながらそれを村山がものにできなかったことが、素直に信じられぬのであった。
控え室に入ったのは午後の3時を回った頃。現在の局面(1図)を並べてあると思われる継ぎ盤を見ると、驚いたことに谷川の王様に王手がかかっていた。
2日制のタイトル戦の戦いでは、1日目は比較的穏やかな流れの中にいるような局面までしか駒を進めない、という感じがあるのだが、そんな感覚はもう過去のものなのかと思わせられる超スピードである。
1図以下の指し手
△1三同香▲1四歩△同香▲同香△1三歩▲同香成△同玉(2図)異例の超スピード進行には理由があった。村山は、昨年の王将リーグ第1戦対南戦で、1図までそっくりの将棋を指していたのだった。
20年ほど前は、うまくいった新工夫の手で数ヵ月は稼げたものである。それが今では、コピーやファクシミリのお蔭で情報の伝わる速度が分単位になっている。村山-南戦の進行は谷川は先刻承知の上である。
1図以下、村山-南戦は△1三同桂▲1四歩△1二歩▲1八飛と進んで先番の村山が勝った。本譜は△1三同香と谷川が新対策を出し、局面は未知の世界へと突入した。
△1三同香に使われた21分という時間は、村山にとってイヤな感じのする長さである。そして、その後の谷川の指し方に全く渋滞が見られないのもその感じを増幅させている。この時間の使い方は、研究範囲の指し手の確認作業をし、自信を持って突き進んで行く時のものだ。
△1三同玉(2図)と、王様を矢面に立てて平然としているのが凄い。思えば10年前、加藤名人を3-1と追い込んでの名人戦七番勝負第5局。銀2枚丸損という加藤捨て身の突進をかわし損ねて敗れた谷川が、局後「もっと顔面で受けなければいけませんでした」と、歯噛みした姿が浮かぶ。試練に出会う度に谷川将棋は強靭さを増してきている。
2図以下の指し手
▲3六歩△6六香▲3五歩△8六歩▲3四歩△2二玉▲8六銀△6七香成▲同金△6六金(3図)「この将棋は、研究していてこれで指せると判断した通りに進んでいます」
2日目の早朝。部屋に届けられたスポーツニッポン紙に載っていた谷川のコメントである。一方の村山は、「攻め合いでは一手負けそうです。どうしましょう」などと言っている。
こんな、軍の機密に属することを載せていいのかしらと心配になった私は、スポニチの大西記者にお伺いを立ててみた。
大西記者の答えは明快だった。
「そういう意見もあるでしょうが、タイトルを争うほどの者には、それで勝敗がどうこういうことはないとちゃいますか。読者に喜んでもらえることはどんどん載せる。それがスポニチの方針です。封じ手なんなのか、と聞いたこともありますよ。さすがに教えてはくれへんでしたけど。ガハハ」
△6七香成で村山陣の金を1枚はがした谷川は、▲同金に△6六金(3図)とかさにかかる。
控え室では正副立会人の森雞二九段と東和男七段が継ぎ盤の検討に余念がない。△6六金への先手の応対は2種類ある。一つは、▲同金と食いちぎって攻め合いを策す順、もう一つは本譜の▲7七金と寄って受けに回る順である。
「攻め合うのやってみようよ。▲6六金△同歩。ここで▲3三銀△同桂▲3七香と」(森)
「!」
先に銀を打ち込んで桂馬を呼んでから香と突っ立てるのが、終盤の魔術師の異名をとる森九段の面目躍如たる手段。攻めの速度を上げる強烈な手筋である。
「後手は勢い歩を成る一手(△6七歩成)と。それで、さあ行け。▲3三歩成△同金直▲同香成△同金▲1三角成(参考1図)だ。どうだ、これで」
▲1三角成を△同玉なら、▲2五桂と打って後手玉は詰む。なんとも凄い殴り込みである。
「△3二玉と逃げる一手ですね。▲3一馬と捨てて、これは取る一手。▲3三飛成で、うわーっ、これは生きた心地がしませんね。後手も」(東)
「合駒は簡単(▲4三桂以下詰み)だけど、王様寄って(△4一玉)▲4三竜に、そこで合駒か、△4二銀打(参考2図)と。えっ、あっ、おいっ。詰まない―のかっ、ホントに?」(森)
後手玉が詰まないと、攻めているうちに自玉が詰めろとなってしまった先手が負けである。
攻め合いがだめなら受けに回るしかないが、▲7七金には△5六桂がなんとも痛烈であった。
(中略)
一方的な谷川の攻勢をじっと耐え、反撃に望みを託す村山。しかし、懸命の頑張りも空しく谷川よしと見られる形勢の差は縮まる気配を見せない。それどころか△7三桂(4図)と桂まで使われては差が縮まるどころか、ますます開いてしまおうかという按配である。
8五の銀を飛車で取らないのがミソ。駒の効率を極限まで高める光速流の駒さばきに学びたい。
このぶんでは、終局は早くなりそうだなあ。久しぶりに村山と麻雀をぶとうかな。すぐに気持ちが緩むのが、我ながら嘆かわしいと思うところである。
(中略)
朝、目覚めた村山には、体が全く動かせない日がある。起き上がるどころか、指先を3センチ動かすことさえできない。アパートの片隅にうずくまったまま、ひたすら水だけを飲み、体が動いてくれるまでの時をじっと耐える。
突き詰めて考えれば、誰にでも命の持ち時間はあるのだけれど、村山と対していると、時間の重みを切に感じる。その村山が、最後まで勝負を捨てずに残り1分まで命を削って戦った。それに応えるべく、谷川の収束はあざやかだった。
(中略)
もう、戦いは終わったのだ。村山よ、ゆっくり休むがいい……。抜け殻の記者は、「実力が足りませんでした。弱すぎます」という村山の談話をぼんやりと聞く。感想戦で村山が流した涙には気がつかなかった。
谷川の「4連勝で防衛できる相手とは思っていなかった」という言葉は嬉しかった。3連勝の後、手綱を緩める事なく戦ったのは、村山の強さと恐ろしさを知っているからであろう。
我に返って思う。
そうだ、村山。自分で言った通りまだまだ君は弱い。谷川を倒すには、3図の時点で参考2図を掘り起こし、なおかつその岩盤をぶち破って、その先に即詰みを見つけ出すほどの集中力とパワーを備えなければならないだろう。君がその力を携えて再びタイトル戦の舞台に上がり立つ日を、記者は待っている。
* * * * *
中野隆義さんは、この当時は将棋世界編集部に在籍しており、第1局の時もそうだったが、一貫して、村山聖六段(当時)の叔父さんのような心情を観戦記に表わしている。
第1局の観戦記→挑戦者・村山聖六段(当時)
* * * * *
『聖の青春』に、村山聖九段が20歳前後の頃、東京将棋会館の控え室で先輩棋士達に「どうやったら詰まないんですか」と話す有名なエピソードが出てくるが、この観戦記がその原典。
* * * * *
2図の谷川浩司王将(当時)の△1三同玉が凄い一手。
▲3六歩で3五の銀を殺されるのが目に見えているわけで、間接的顔面受けとでも言うのか、その後の展開を見ると、まさに肉を切らせて骨を断つような狙いだ。
* * * * *
2図以下▲3六歩△6六香。
この局面で封じ手となり、昨日の記事で出てきた封じ手用紙の▲3五歩となる。
「攻め合いでは一手負けそうです。どうしましょう」のコメントも、攻め合いの▲3五歩を封じ手とした直後のもの。
* * * * *
3図の段階では、先手に勝ちがなかったことになる。
▲7七金からは一方的に攻められる流れとなってしまった。
「このぶんでは、終局は早くなりそうだなあ」
しかし、4図から村山六段は必死に粘り、投了図では一手違いまで持ち込んだ。
「攻め合いでは一手負けそうです」の通りとなった形となる。
* * * * *
この観戦記の題名は「聖よ、もっと爪を伸ばせ」。
「聖よ、もっと爪を伸ばせ」に類する言葉は出てこないが、爪や髪の毛を伸ばし放題だった村山聖六段。盤上・盤外で”村山聖六段らしさ”をもっともっと出してほしいという願いだったのだろう。
* * * * *
「実力が足りませんでした。弱すぎます」
感想戦の後なのか、あるいはもう少し経ってからなのか、村山聖六段が悔し涙に泣き崩れたと言われている。