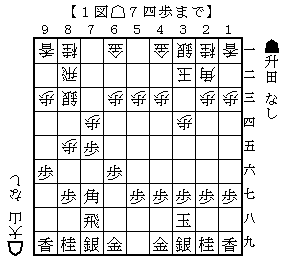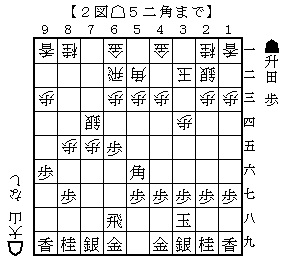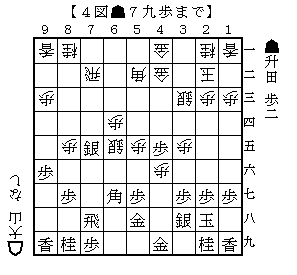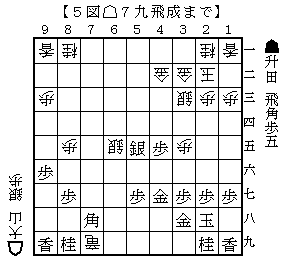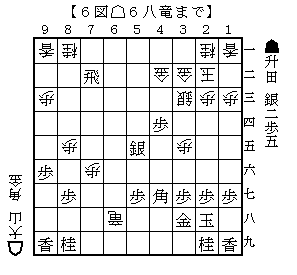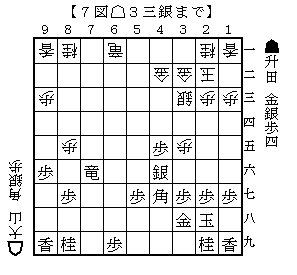将棋世界1981年1月号、加藤治郎名誉九段の「忘れえぬ観戦」より「未完成の一局」。
”忘れえぬ観戦”が編集部からの注文である。私は”観戦”にはこのうえなく恵まれた棋士の一人。歴代名人の木村、塚田、大山、升田、中原をはじめ、現代の棋界を代表するあらゆる棋士達の対戦を、ときには立会人、ときには観戦記者として、数え切れないほど数多く観戦している。
従って、その中から一局だけ”忘れえぬ観戦”を撰ぶのは至難中の至難事である。
”さて、どれにしたら”と思い悩む日が幾日か続いた。が、ある日偶然手許にあった棋聖戦の古い切り抜き帳を眺めているうちにふと本局の大山、升田戦が目にとまった。
あれから13年を経たいまでも、対局の情景が鮮明に浮かぶ、強烈な印象の一戦であり、両雄の数ある名勝負の中でも、稀に見る一大激闘譜である。私は瞬間これに決めた。
昭和42年11月8日、於・東京将棋会館
第13期棋聖戦・挑戦者決定準決勝
(持ち時間各6時間)
▲九段 升田幸三
△名人 大山康晴▲7六歩△3四歩▲7五歩△8四歩▲6六歩△8五歩▲7七角△7二銀▲7八飛△8三銀▲9六歩△4二玉▲4八玉△3二玉▲3八玉△7四歩(1図)
火と火の戦い
全将棋ファンを二分する両巨豪がまさか準決勝で顔を合わせるとは夢にも思わなかった。今期棋聖戦中、願ってもない好カードであり事実上の挑戦者決定戦ともいえよう。だが世の中は広大、別の見方をするものもある。
本局の数日前、口の悪い新鋭棋士の某氏が”準決勝で大山、升田がぶつかってよかったですね。前期のように別々の組み合わせでは両人とも決勝まで残るかどうかわかりませんからね”と、冗談とも本気ともとれる言葉をはいた。(注=前期準決勝では、大山は高島五段、升田は中原六段にそれぞれ敗れて、決勝戦は新鋭同士の争いとなった。決勝戦では中原が勝って挑戦者となり、続く山田棋聖との五番勝負にも勝って、初の棋聖位に就いた)
私はこの話を両人にした。両人ともぶすっとした顔で聞いていたが、やがて升田は”両人とも敗退したら強そうに見えて弱い。時代は変わったといわれるだろう”と、はっきり言った。時代が変わるかどうかは、大山、升田の勝者が挑戦者になるかどうか、続く挑戦五番勝負で、中原青年棋聖とどんな戦い方をするかにかかっている。
さて、ムダ口をたたいているうちに、指し手は快調に進み、わずか10手前後で局面は早くも未知の世界へとびこんでしまった。
いつもは升田の火、大山の水の戦いだが、本局はどうやら、火と火の戦いらしい。
私の前述の告げ口で、両人とも怒っちゃったのかな。
以上が、私の本局観戦記第1譜の観戦記である。
1図以下の指し手
▲8八角△7二飛▲7四歩△同銀▲6五歩△7五歩▲6八飛△6二飛▲2二角成△同銀▲5六角△5二角(2図)新型の超急戦法
両雄の将棋は戦型、戦略ともにスケール雄大、しかも一手一着が独創的で新鮮潑溂。そのうえ、宿命のライバル同士だけに、すさまじいばかりの闘魂が自ずと盤上に爆発する。ファンにはこれがたまらない魅力なのだ。
本局、大山の居飛車は一般の定跡書にあるような平凡なものではなかった。いきなり右銀を飛頭にとびだす棒銀流の超急戦。いままでだれも試みなかった新型の超急戦法だった。
大山は△7四歩(1図)と突きながら”この棋譜をだまって棋力鑑定にだしたら、係の先生から、両人とももう少し定跡書をご覧なさい、とたしなめられるだろ”と笑う。
升田もすぐ”これが事実上の棋聖戦かな。だから読者にもおもしろく見せなきゃあ”と同じように笑う。笑いあってはいても、両雄の頭脳は猛烈な速さで回転、盤上の変化をくまなく読んでしまう。
新型の将棋は地図も磁石盤も持たずに未踏の深山を踏破するようなもの。しかも、最長7分の快速でふっとばしている。両雄ならではできない芸当である。
升田が角交換から筋違い角を5六に放って次の▲6四歩を狙えば、大山も5二に筋違い角を打ってこれを受ける。
局面が棒銀から相筋違い角に変わるとともに、攻守もいつの間にかその所を変えながら超急戦局も一時的に小康状態にはいった。
2図以下の指し手
▲7八銀△3三銀▲7七銀△4二金▲2八玉△5四歩▲3八銀△4四歩▲6六銀△2二玉▲4六歩△5一金▲7八飛△7二飛(3図)異国人同士の会話
▲7八銀以下は第二次駒組み期。
升田は▲2八玉と寄せながら”大山君と予選でこんなに早く顔を合わせるとはめずらしいね”と、つぶやく。大山はすぐ”タイトル戦では初めてでしょうね”と、答える。大山対升田戦は本局が151戦目。過去の戦績は大山84勝(不戦1)。升田65勝。持将棋1。公式戦の最多対戦の新記録である。これは、両雄がここ20数年間、他の棋士に比べとび抜けて強かったからにほかならない。
若い頃の両雄はタイトル戦の挑戦権を争って戦った。当時の目標は木村名人であり、塚田名人(故、名誉十段)だった。木村が引退し、塚田が後退したあとは、タイトルの争奪戦に終始した。なるほど、こんな風にみてくると、タイトル戦でこれほど早く(といっても準決勝だが)顔を合わせたのは、あとにも先にもこれが初めてのようである。
なお、両雄は対局中直接話し合うことは滅多にない。前述の会話も実は観戦子が間にはいっている。この点、両雄は言葉の通じない異国人同士のようなもので、間に通訳が入らなければ会談ができないのである。
3図以下の指し手
▲6四歩△同歩▲7五銀△6五銀▲4七角△4五歩▲同歩△4六歩▲5八角△5五歩▲6七角△4一金寄▲5八金左△3五歩▲7九歩(4図)名人芸、升田の角使い
昔から天才は角使いがうまいと言われている。現棋界でも角使いの名人は升田で、金は大山、飛車は大野八段(故、九段)との定評がある。(いまなら桂は中原名人と続くところだが、当時はそれほど有名ではなかった)。
これから始まる、升田の角使いに注目されたい。
升田はまず▲6四歩と戦端を開き、△同歩と取らせて▲7五銀と歩を取り返しながら、銀に銀を体当たりさせる。△7五同銀なら▲8三角成で升田優勢。
大山はこれを嫌って△6五銀とかわしながら角当たりの逆先をとる。
升田が▲4七角とかわせば、大山はさらに△4五歩▲同歩△4六歩で敵角を5八に撃退、続いて△5五歩と突き、次の△5六歩をねらう。△5六歩▲同歩△同銀と敵銀に進撃されては升田陣は壊滅する。
升田陣危うし。が、升田は▲6七角とのぞき、敵銀の進撃をぴたりと止めてしまう。やはり升田の角使いは名人芸である。
局後、大山も”▲6七角があるとすれば△4六歩は指し過ぎ。だまって△5五歩が本手でした”と、好手▲6七角を認めながら△4六歩を悔やむ。
升田の▲6七角で大山の反撃が止まり、局面は△4一金以下またしても緩やかな流れにかわる。と、みられたとき、升田は突如長考に沈んでから▲7九歩の奇手を放つ。
4図以下の指し手
△3二金上▲6四銀△7八飛成▲同角△2五角▲5五銀△5八角成▲同金△4七金▲同銀△同歩成▲同金△4九飛▲3八金△7九飛成(5図)疑問手対好手
升田の▲7九歩は次に▲6四銀の決戦をねらった一着。あらかじめ飛車交換後の△7九飛打ちを消した渋い好手である。
升田は▲7九歩と打ちながら、無言のまま大山の額のあたりをぎょろりとにらむ。相手の手応え、心の動揺をたしかめる得意のゼスチャーである。
大山は真新しいハンカチをひざの上にひろげ、扇子を片手に悠然と熟考にはいる。ハタ目には全然動揺の色は感じられなかった。
だが、形勢はこのあたりから徐々に升田に有利となっていった。
局後、大山は「△3五歩は5二角をさばく意。が、角がいなくなったあと自陣を薄くするので疑問。△3五歩では△4三角から△5二飛-△5六歩の攻めをねらうべきだった」という。
形勢の差は疑問手△3五歩と好手▲7九歩の差であるらしい。
大山が11分で△3二金上と自陣を強化しながら決戦に備えれば、升田は再検討の7分でぐいっとばかり力をこめて▲6四銀とでる。
いよいよ、乗るかそるかの大決戦の幕は切って落とされた。
大山が飛車交換から△2五角と大さばきにでれば、升田は▲5五銀と歩を払いながら敵の攻めを催促する。一見、いかにもゆっくりした手にみえるが、次に▲4四歩の攻めと▲4六銀の受けとをみた攻防手。こんな落ち着いた手が指せるのも敵の△7九飛を消している▲7九歩のおかげである。
4六歩を失っては万事休す。大山の△5八角成から△7九飛成までは絶対の攻めである。
5図以下の指し手
▲7二飛△7六歩▲6七角打△6九銀▲5六角△同銀▲同角△5八銀不成▲4四歩△4七銀不成▲同角△6八竜(6図)優勢、升田ごきげん
大山の△7九飛成に、升田は頭上高々と飛車を振り上げてから盤も割れよとばかり▲7二飛と打ちおろす。ノータイム指しと、いままで聞いたことのないような大きな駒音。形勢われに有利とみての会心の一着らしい。
苦吟12分、大山は△7六歩と打って敵飛の利きを止める。角取りの先だ。この手で△6九銀では▲4四歩△7八竜▲同飛成△同銀不成▲6二飛△6八飛▲4三角以下、寄せ合い大山の一手負けとなる。
升田は”目にもの見せん”と言いながら、ハデな手つきで▲6七角と打ち、角に角をつなぐ。単に角の受けというより、次の▲4四歩-▲4三歩成-▲2三角成の寄せをねらった攻防兼備の角打ちである。
升田はこの角打ちもさきの▲7二飛と同様にお気に入りの手らしく”攻防綾なす将棋じゃな。こりゃ久し振りで名局ができた”と至極ごきげんである。
大山の△6九銀から△5八銀不成までは大体一筋道。
ここで升田は”いいさばきだね。お互いに”と言いながら▲4四歩と突く。▲4四歩は待望久しかった急所の攻め。次に▲4三銀と打つことができれば、大山の玉はほとんど受けなしとなる。どうやら”お互いさま”の言葉は、▲4四歩で勝ちとみた升田の大山へのお世辞らしい。
大山は△4七銀不成▲同角と金銀を交換してから△6八竜と引く。
△6八竜は敵の▲6五角出を消しながら△4八金(一手スキ)の寄せをねらった局面随一の勝負手。
さあ、どちらが早いか、戦局は一手を争う寄せ合いの終盤戦へと突入した。
6図以下の指し手
▲6九歩△6一竜▲7六飛成△4五金▲4六銀打△4四金▲同銀△同銀▲4五歩△3三銀(7図)無念、名局を逸す
升田は”ははあ、敵は粘ろうというのだな”と、つぶやきながら少考3分で▲6九歩と打ち、△6一竜に▲7六飛成と成りかえる。
▲6九歩は自陣のキズを消した堅実な着手。無論これでも手数は多少長引くが升田の優位は不動と思われた。ところが、▲6九歩は失着であり、6図では升田に早く、かつ鮮やかな勝ち方があったのである。
▲6九歩では▲4三銀が正着。▲4三銀に△4八金なら▲3二銀成△同金▲同飛成△同玉▲6五角以下明らかに升田の一手勝ちだった。▲6五角は敵竜の利きに角をとびだす妙手。①△4一玉なら▲5二銀以下即詰み。②△6五同竜なら▲4三金△2二玉▲4八金まで、升田の玉は二手スキ、大山の玉は必至となり、いずれも先手必勝。
右の順は、対局中はもとより局後の感想戦のときも、両対局者はじめ盤側のだれひとりとして気がつかなかった。
ところが、升田が家に帰り床についたとたんに気づき、それを翌朝早く拙宅に電話で知らせてくれたのである。
いつもの升田なら一瞬で発見できる順。体調が不順(当日は風邪ひきで高熱だった)だったか、あるいは魔がさしたというほかはないであろう。
仮に▲4三銀で升田が勝っていたら本局は近来の名局と絶賛されたに違いない。早い勝ちと名局をともに逃す。升田にとってはまことに惜しい逸機だった。
危機を脱した大山はすかさず△4五金以下自陣を立て直してしまう。
苦戦の将棋を”勝負勝負”と相手に息もつかせず迫ってゆく呼吸といい、容易に決め手を与えぬ強靭な二枚腰のねばりといい、大山の強さ、とくに苦戦のときの強さには舌をまかざるをえない。
7図以下の指し手
▲7三歩△6七角▲7九竜△6六竜▲6八歩△8九角成▲同竜△4六竜▲4八銀△5五桂▲8三角成△5八銀▲5九金△4七銀打▲5八金△同銀不成▲5六銀△4九金▲5五銀△4八竜▲同金△同金▲1六歩△4七銀不成▲同馬△同金▲3八銀△4六歩▲同銀△同金▲5五角△4五金▲3四桂△1二玉▲4二桂成△同銀▲6四角△4六桂▲4七歩△3八桂成▲同玉△4六歩▲同歩△7四角▲4七桂△5八銀▲4八金△4七銀不成▲同金△5八銀▲4八銀△2六桂▲同歩△2七銀▲同玉△4七銀不成(投了図)
まで、150手で大山名人の勝ち最近稀な名勝負
升田は勝機と同時に名局の誕生を逸した。このため戦局は長期戦の色が濃くなった。が、形勢は依然升田が勝勢である。それは持歩の数が4対1の大差だからである。
ところが7図あたりから升田は急にペースを乱してしまう。
▲7三歩は不急の攻めで正着は自陣補強の▲5八銀。だが、大勢に影響するほどのことはなかった。
ひどかったのは△6七角▲7九竜△6六竜と進んだときの▲6八歩である。
升田「▲6八歩は大ポカ。結果は銀桂と角の二枚替えのうえ、味方の竜がそっぽへいってしまったのだからひどすぎる。▲6八歩では▲5六銀△4九角成▲6八歩△4八銀▲同金△同馬▲3八金△4七馬▲同銀で優勢だった」
不急の攻めにつづいて大ポカを出す。やはり、升田の心のすみには”相手は二枚腰、戦いを長引かせては面倒”と、いった焦りがあったのだろう。そして、その焦りは大ポカで落胆に変わり、ここでまた▲4八銀の失着がでてしまった。▲4八銀は▲4八金打が正着。これなら大山の△5五桂から△5八銀の攻めがなく、勝敗は不明のまま長い戦いが続けられたはずである。
大山の△5五桂以下は、食いついたら離れぬスッポン攻めだ。しかも、このスッポン攻めは、大山のお家芸の一つだけに相手にとってはまことに始末が悪い。升田もかなり頑強に抵抗したが結局は空しかった。
△4七銀不成に、升田は”これまで”と、はっきり言って駒を投じ、大山は深く頭を下げて礼を返した。
終了は午後5時18分。両雄ともかなりの早指しだったが、最近本局ほどスピードとスリルを満喫し、絢爛華麗な戦いに終始した将棋は稀だった。やはり当代を代表する、超ヘビー級の対戦はすばらしい。
注=この期、大山は決勝戦で二上八段(現九段)を降し挑戦者となったが、続く中原青年棋聖(当時六段、21歳)との挑戦五番勝負に1-3で敗れ、棋聖位の奪還に失敗した。
——–
升田幸三九段が「大山君と予選でこんなに早く顔を合わせるとはめずらしいね」と話すと、すかさず「タイトル戦では初めてでしょうね」と大山康晴名人。
この会話が二人同士ではなく、観戦記者である加藤治郎名誉九段に向けられているわけで、とても可笑しい。
さすがに感想戦では直接二人が会話をすることになるのだが、やはり本当はこの二人は仲が良かったのではないかと思えるほど。
——–
この一局、大山-升田戦の醍醐味、振り飛車らしい捌きと指し回し、を120%味わえる素晴らしい将棋。
お時間のある方は、ぜひ盤に並べてみてください。