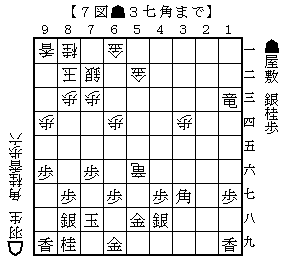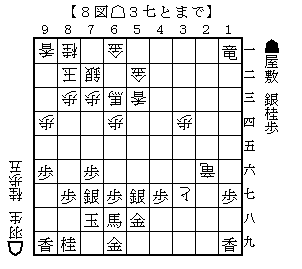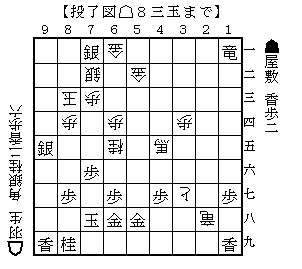将棋世界2001年10月号、片山良三さんの第42期王位戦〔羽生善治王位-屋敷伸之七段〕第3局観戦記「銀得で不利という、不条理」より。
7図以下の指し手
△2七角▲7七銀△6三角成▲1一竜△2六歩▲4六角△2七歩成▲1三角成△5三香▲6八馬△2六竜▲5七銀△3七と(8図)
〔戦意喪失〕
残り10分になった屋敷に対して、羽生の△2七角は残酷とも言える非情の責めになった。△6三角成と引きつけられれば、羽生の玉は詰む形が想像できなくなるが、このラインには障害物がないので止めようがない。詰みそうにない敵玉に時間切迫の状況で向かっていかなければならないウンザリ感を想像してみてほしい。屋敷の心理的な負担を一瞬で読み切り、相手が最も嫌がる指し手を選択できるのが、羽生一流の高度な勝負術なのだ。
当面は銀損という小さくない駒損なのだが、なぜか指しにくさは感じない。その点は羽生も同意して「歩の数が多いからでしょう」と明確な分析をした。事実、馬を作ったあとは△2六歩からのと金の製造。この時点で羽生も「やっと良くなった」と認めた。
もっと良くできそうな将棋を決めきれなかったことで著しく消耗していた屋敷は、△2七角を見たところで、この将棋にはすでに自分に勝ちが出ないことを悟っていたと思う。
△5三香と、あくまでも手厚い手で制空権を確保し、△3七とと元手がかかっていないと金を働かせる羽生。屋敷から、銀得という物質的な優位さえ奪ってしまえば、勝ちは向こう側から転がり込んでくるという大局観だ。
8図以下の指し手
▲9五歩△同歩▲9四歩△2八竜▲9三桂△同桂▲同歩成△同香▲8六銀△6五桂▲7五桂△4五馬▲8三桂成△同玉▲9四歩△5七香成▲9三歩成△同玉▲8五香△8四歩▲同香△6八成香▲同金上△8三歩▲7一銀△8四歩▲9五銀△8三玉(投了図)
まで、106手で羽生王位の勝ち〔痛い負かされ方〕
▲9五歩以下は、単なる形作り。終局を確認するための作業工程に過ぎなかった。投了図から▲7五香で詰めろを継続したとしても、△7四歩で今度こそなにも手がない。
屋敷独特の変則的な揺さぶりが全く通用しない七番勝負。今回は序盤の再三のフェイント攻撃に羽生が挑発されて、屋敷が主導権をつかんだようにも見えたが、「銀得なのに、すでに悪いかもしれない」という不思議な展開に頭を抱えた。ポーカーフェイスを崩さない屋敷だったが、こんなショックな負かされ方も、初めてだったのではないか。
羽生は新たな挑戦者がやってきたときに、(多分意識的に)こんな負かし方をする。ただ負かすのではなく、心の奥底にコンプレックスという傷も負わせようという計算なのではないか。まさに王者の勝負術を見せてもらった気がする。
力の半分も出させてもらえない屋敷は第4局以降にどんな巻き返しを見せてくれるだろうか。「力が入り過ぎと違うか」とは、立会人の内藤九段の指摘。ウキウキとして競艇場に行くような、普段着の屋敷に戻ることができれば、羽生の精密な思考回路をも乱せるかもしれない。
—————-
△2七角という、穏やかに見える一手が超激辛なのだから驚いてしまう。
大山康晴十五世名人流の、若手の挑戦者の心の奥底にコンプレックスを植えつける、という狙いではなかった可能性もあるが、とにかく挑戦者の心が折れてしまうような負かし方。
しかし、よくよく考えると「激辛」というのは相手を攻撃する手ではなく自陣を固める手である場合が多いので、穏やかに見える一手が激辛であることは不思議なことではないのかもしれない。