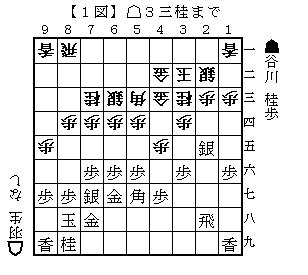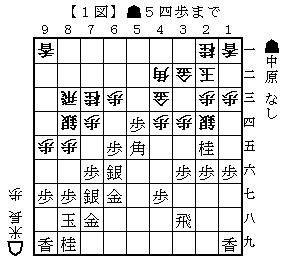先崎学五段(当時)渾身の観戦記。
将棋世界1991年7月号、先崎学五段の第49期名人戦〔中原誠名人-米長邦雄九段〕第3局観戦記「偉大なる虚像」より。
「ええ、勿論米長九段の応援です。スケールの大きな将棋に憧れますね。一度でいいから名人になってほしい」
(42歳・会社員 四段)
「ワシの好きなのは、何といっても昔升田、今米長だ。実績では大山、中原に負けるが、それがどうしたちゅうんじゃ。まったくだらしのない奴だ。一度くらいは名人取らんかい」
(69歳・二段)
「将棋のことはよく分からないんですけど、米長先生ってなんだかとても魅力的なんです。イヤラシイところがなくて、本当に爽やかな感じ。ス・テ・キ。えっ?名人に挑戦するの。頑張ってほしいわ」
(32歳・主婦 覚えたて)
「おい、米長の弟子の先崎というのはあんたか、俺は米長の大ファンなんだ。今日は苦戦しとるが、必ず勝っていると信じてるぞ。ちょっとアンタ、米長に発破をかけて来てくれんか」
(当日、大盤解説場にて。やや興奮気味か?47歳・自営業)
「え―なんだかよくわかんないけど、とっても素敵、いいオジさん。不倫してみたい、なんて。ヤダーこんなこと言わせないでよ」
(20歳・女子大生)
「勝って欲しい。本当に勝って欲しいんだ・・・」
これらの声は、総て、師匠が名人挑戦者になってから僕の耳に寄せられた声なき声である。僕が米長門下だということもあるのだろうが、僕の周囲には、米長ファンが多い。米長ファンの特徴は、まず、なんといっても熱烈的なことである。野球に例えるならば、中日、阪神といったところのファン気質と通ずるものがある。おおむね、声が大きく、躁型で、人情に脆く、ファンであることを誇りに思うようなところがある。対して中原ファンは、なんとなく巨人が好きという巨人ファンが多いように、なんとなく中原が好きというような人が多いように思う。
とにかく、僕の周りには、どうしようもないくらいに熱烈的な米長ファンが多いのである。彼らは水割りを三杯も飲むと、決まってこう叫ぶのだ。
「一度でいいから名人を!」
事実、かつてこれ程までに声援を背に受けて登場した挑戦者が、昭和46年度の升田幸三の他にいただろうか。
しかし、棋士仲間、関係者、ファンなどの無数の声なき声の殆どは、どうしても中原から名人を取ることができず、そのことからくる無念の思いがちょっとした仕種にも表れ、翳りをつくる米長邦雄という脆い存在に対する隔靴掻痒ともいうべき同情票なのである。米長ファンのもう一つの特徴として、熱烈的なわりには、素直から程遠いことがあげられる。誰もが、名人戦になると”勇者”の指手がおかしくなってしまうことを知っており、にもかかわらず「もしも」を期待して声援を送っているのである。
そうなのだ、水割り三杯飲んで「一度でいいから!」と叫んだ”同志”は、その後、決まってこう呟くのだ。
「でも、また駄目だろうな」
ああ!こんなに悲しい物語があるだろうか―。
第1期竜王戦のことも忘れられない。
名人位に縁の無かった師匠としては、新設された名人と同格の地位を持つ竜王に就くことは大きな意味を持っていた。準決勝で高橋に競り勝ち、相手の山は中原-島戦、当然宿敵中原が出て来ると思いきや、決勝に躍り出て来たのは島だった。米長と島では、格が違う。島はタイトルはおろか、全棋士参加の棋戦の優勝もなく、タイトル挑戦もない。順位戦のクラスはB2で、こうした実績に弱いマスコミやファンは「米長竜王」誕生があたかも既成事実のように書きたてた。「大豪米長に挑む新鋭島」といったニュアンスの記事が目についた。「挑戦者の島は」と明らかな誤りをおかす記事すらあった。これは、師匠にとって不利だが、師匠のような古い考え方を受け入れることをハナから拒否する島にとってはこの上ない高材料だった。島は洋服で対局に臨んだ。
アルマーニのスーツを着て、またそれを着ることを宣伝して対局に臨んだ島に対し、師匠はなにを感じたか。あくまでも僕の想像にすぎないが、異星人(エイリアン)と盤を挟んだように受け取ったのではないだろうか。アルマーニというブランド名は、たしかに音に聞こえる有名ブランドだが、もちろんそれを着ているからといってその人間のステータスがあがるわけではない。師匠のような古い人間にはオシャレとはさりげないものだという美意識がある。自分からアルマーニという言葉を口に出す島が相手だ。そこにか感性の繋がりは微塵もなかった。
ましてや、師匠にはタイトル戦の場に洋服で臨むことは、恥ずかしいことだという強い気持ちがある。また、また聞きで書くのはルール違反かもしれないが、島は、対局の前夜祭ではジュースを飲んでいたという。ジュースの話は有名だが、壇上で、いい男が、ジュースを片手に乾杯というのではあまり良い気持ちはしない。島だってビールくらい飲めないわけではないのだ。
―この竜王戦、師匠は、負けるべくして負けたといえるだろう。
待ち合わせの時間や約束に対して厳格なのは昔からである。
内弟子の頃、林葉と二人であやうく破門になりかけたことがある。千葉に遊びに行っていて、6時迄には戻る約束だったが、千葉市の森林公園で遊び過ぎてしまい、千葉駅についたのは、とうに6時を過ぎていた。1時間半あまりの遅刻である。
千葉駅から恐る恐る二人で話し合い電話をかけようということになった。
「直子ちゃん、してよ」
「先崎、あんたしなさいよ」
結局、僕が電話をかけることになった。
「すいません―実は今千葉駅にいて、遅れてしまうんですが・・・」
「なんだと、もう一度言ってみろ」
「今、千葉駅に・・・」
「馬鹿もん! 6時に帰ると言ったじゃないか、師匠との約束を破るとは何事だ」
「・・・すいません」
「とりあえず、今日は帰ってこなくてよろしい。師匠との約束を守らないような弟子を預かるわけにはいかない。千葉なら佐瀬先生の家が近い。そこへ行きなさい。ところでブス直子はいるのか」
当時、僕は与五郎(意味不明)、林葉はブス直子と呼ばれていた。林葉さんも異常な雰囲気を察してはいたろうが、受話器を握るなり、動かなくなってしまった。今さら佐瀬邸に行くわけにもいかず、とにかく戻ろうということになり電車に乗ったが、阿佐ヶ谷駅までの1時間余、一言も口をきかなかった。林葉は、うつむいて、目は赤くそまっていたが、涙はこぼさなかった。その頃は毎日僕を泣かしていたので、僕の前で涙を見せる訳にはいかなかったのだ。
事情を聞いた佐瀬先生の奥様にあやまって頂いて破門にこそならなかったが、それから1週間あまりは”破門”という言葉が頭の片すみから消えなかった。
それ以来、僕は時間に対して潔癖症になった。
さわやかで、常に回りに気をつかう師匠だが、人間である以上、良いところばかりではない。
僕は経験がないので分からないのだが、七番勝負という長丁場を闘うとき、もしかしたらこのような繊細な部分が災いとなり、あと一歩の壁を破れないのではないだろうか?
こういうことが、名人戦の組み合わせが決まってから、頭の中にチラチラしてこびりついて離れなかった僕が、必ずや一度は名人に就くと信じている。しかし、ファンの間では”米長名人”というのは、現代のお伽話となっているようだ。アマチュアのファンの反応も厳しく、本誌が行った予想投票では、中原ノリの声は、8対2よりも9対1に近かったそうである。ファンの数に差があるとは思えない。いや、むしろ米長ファンの方が多いのではないだろうか。にもかかわらず、大差がついたのは、明らかに米長ファンが彼を見放したからだ。弟子が、複雑な感情で師匠を見放したように、ファンもファンであるまま師匠を見捨てたのだ。
そんな状態で名人戦は始まった。第1局が始まる前、師匠は、親しい棋士仲間を集めて、池袋で食事の会を開いた。同席した人の話によると、気のおけない、楽しい宴だったそうである。
親しい仲間は、最近不調の人が多く、落ち込んでいた友人達をねぎらい、なぐさめ、お互い頑張ろうといい、河豚をつついた。また、去年の暮には、その年に親を亡くした人達を集めて、食事の会を開いている。好き放題やっているようにみえて、優しい一面を持っているのだ。
だが弟子としては、不調の友をなぐさめるのももちろんいいのだが、名人戦一本に打ち込んで欲しいとも思った。
(つづく)
—–
明日(12月18日)は、故・米長邦雄永世棋聖の命日。
対局者だからこそ書ける自戦記、
対局者ではない観戦記者だからこそ書ける観戦記、
というものがある。
そういう意味では、この先崎学五段(当時)の観戦記は、弟子でなければ書けない観戦記。
今日から3日間、先崎学五段(当時)の観戦記を通して、”棋士・米長邦雄”と向い合ってみたいと思う。