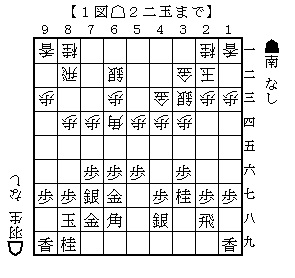将棋世界1991年6月号、大崎善生さんの「編集後記」より。
昨年の5月のある日、突然、総務のN口君に呼ばれました。手が震えて撮れないから、代わりにお願いしますというのです。升田先生が身分証明書用の写真のためにわざわざ、連盟に出向いてこられたのでした。
「先生、では4、5枚お願いします」「ウム、よろしい」。私も手が震えました。夢中でシャッターを押し続けて「ありがとうございました」と頭を下げると、突然眼光鋭く私をにらみ「6枚撮った!!」そして、「4、5枚と言ったじゃろう!!」
カシャ、カシャと鳴るシャッター音を数えてらしたのだ。しかし、言葉とは裏腹に瞳はいたずらっ子のように優しく輝いていました。
「4、5枚というからいかん、何枚でもよろしいぞ」
今となっては忘れられない思い出です。
——–
大胆さと豪放さの奥に細やかな気遣いのあった升田幸三実力制第四代名人。
いかにも升田流の風情だ。
——–
しかし、これを「升田幸三」がやるから最高のエピソードになるわけで、他の人が同じことをやっても、「??」あるいは「何を勘違いしているのだろう」などと思われてしまうだろう。特に、いつも優しそうな人や愛想のいい人がこれをやったら、甚だしく逆効果になること間違いなしだ。
——–
升田幸三実力制第四代名人がそうというわけではないが、昔から思っていることがある。
それは、強面キャラクターあるいは悪役キャラクターが得をする、ということ。
映画などで、「生徒から慕われ、親からの評判も良く、同僚からの信頼も厚い教師」役と「日頃から悪事に手を染めている札付きのヤクザ」役がいたとする。
ある日、教師が電車に乗っていると、乗客の若い男が肩がぶつかったと言ってお年寄りの男性に因縁をつけていた。しかし、教師は急いでいたので、それを横目に電車を降りた。
同じ頃、ヤクザが道を歩いていると、怪我をした子猫が道端で苦しそうにしているのを見かけた。捨て猫なのだろう。ヤクザは子猫を抱え、そばにあった動物病院に入り、受付で、「こいつを治してやってくれ。失敗したらここにダンプカー突っ込ませるからな」と言って1万円札5枚を受付に放り投げ、子猫を置いてすぐに出て行った。
この2つの場面を見た後では、あくまで映画の中での話だが、ほとんどの人はヤクザの方がいい人に感じてしまうのではないだろうか。
普段との落差、それがマイナス方向に働くかプラス方向に働くかで大きく印象が変わってしまう。
映画の中では、教師は電車の中の老人を助けることを期待されているわけで、その期待が裏切られただけで評価は急激にマイナス方向に向かっていく。反対に、ヤクザは株価急上昇。
トータルすれば、教師のほうが高く評価されなければならないことは分かっていても、そうなってしまいがちだし、それが映画の演出でもある。
三浦友和さんが演じるヤクザが、自分が育った孤児院の子供たちにひそかに玩具をプレゼントしているようなパターンがまさにその図式で、これは映画「泥だらけの純情」での事例。
——–
将棋で90対10で優勢だったのが60対40に差が縮まった時、悲観してそのまま形勢を逆転されることが多い。
反対に10対90で敗勢だったのが40対60に差が縮まると、その勢いで勝てることが多い。
冷静に考えれば40対60よりも60対40の方が状況は良いわけだが、それまでの状態と比較してその変化の落差が心理に及ぼす影響が大きいのだろう。
悪役キャラクターが得をする、という話と共通する部分があるのかもしれない。