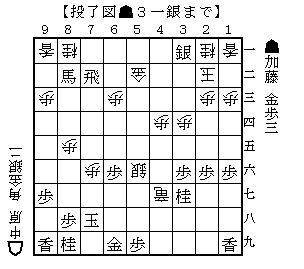将棋世界1982年10月号、毎日新聞の井口昭夫さんの第40期名人戦最終局レポート「加藤新名人誕生」より。
一日目朝
立合いの木村義雄十四世名人夫妻を宿舎のホテル・ニューオータニから将棋会館へ午前8時半にご案内した。この時間の都心は、まだ比較的すいていて、午前9時対局開始には早すぎたが、前後して、もう一人の立会い丸田祐三九段、観戦記の原田泰夫八段も控え室に姿を見せ「やあ、久し振りだね」と木村名人は大喜び、早速、懐旧談に花が咲いた。十四世名人のお元気なのは喜ばしい。
異例づくめの名人戦だった。実質10局目になったため、将棋会館の宿泊施設が間に合わず、前夜泊まったのは中原名人と加藤十段の二人だけ、朝食も各自、外でお願いするという申し訳ない始末だった。
ただし、大勝負の最終局にふさわしいお膳立ては多かった。木村十四世名人が本格的な立合いをするのは初めてだったし、二日目の大盤解説は東京・関西両将棋会館、東京・毎日新聞、新宿駅前と、大きな所で4ヵ所が予定された。
対局開始
4階特別対局室。さすがに両対局者は緊張気味だった。座布団を二枚重ねにして座った木村名人の両脇に丸田九段と原田八段、ずらりと和服姿の三人が並んだのは壮観だった。
対局会心宣言で加藤十段が7六歩と角道をあける。当然のようだが、この一つの情景からも、いろんなことが思い出される。第7局の冒頭、中原名人の先手番で始まろうとした瞬間、加藤十段が「今回は最終局なので振り駒だと思いますが」と口を切った、あのときの緊張―。第8局の振り駒の際、緊張しすぎたか大野八一雄四段の手を離れた歩の一つが、石葉亭のベランダの下駄の上に飛んで落ちたこと―。
7手目、2六歩。第2局から指し直し第6局まで先手がずっと採用した飛先の歩を突かない矢倉など、もうすっかり二人は忘れてしまったようである。
控え室には名人戦の対局場として知られている羽澤ガーデンから応接の女性二人が和服姿で控え、万全の対策が立てられていた。
ところが、加藤十段はお茶も断った。数日前「おやつ類は一切必要ありません」と電話をもらったので、そのつもりでいたが、お茶もいらないとは。さては一切を拒否する厳しい姿勢か!と見えたが、昼食は皆と一緒(中原名人は自室)にとるなど、とり立てて構えたところもない。不思議な人だ。
一日目に決戦
一日目夕刻、中原名人が決戦に出た。もともと攻めの激しい人だが、土壇場での思い切りのよさは特別だ。第7局はその決断のよさで快勝している。
8六歩、同銀、同角、同歩。角を切っての強行手段は一日目には珍しい。次の手が封じ手だ。次の8五歩のツギ歩が厳しいという声、いや角銀交換の駒損は大きい、など控え室騒然のうちに第一日は終わった。
二日目再開
二日目朝、再び木村名人夫妻をホテルからご案内。封じ手開封のあと、引き揚げていただくことになっている。名人自身は終局後の検討までつき合いたいと希望していたが、会館は旅館、ホテルのような部屋数もなく、対局者も気を使うだろうということで、設営側でそうお願いしておいたのだ。
「わしが居なくては困らないか」
「強い者が居ては対局者も指しにくかろう」
さすがは大名人らしい言葉を残して、間もなくご夫妻は茅ヶ崎の自宅へ帰られた。車中で「中原名人の駒損は大きい。長引けば不利だ」と洩らした。その夜、結果を報告すると予期していたようだった。
それはさておき、二日目は姿を見せる棋士も多かった。加藤治郎名誉会長のほか、その夜、解説を担当する二上九段、石田八段、谷川八段、それに北村八段ら、石堂淑朗、斎藤栄の両作家も現れた。新聞、放送、雑誌の記者、カメラマンもふえる一方だ。中原十期名人か、加藤新名人誕生か。歴史的な一瞬へ向かって、時は容赦なく過ぎていった。
加藤の勝負手
昼食休憩をはさんで加藤十段は2時間20分の大長考で6一角。「ねらいをつけておかないと勝負にならないと思った」と非勢承知の勝負手だったようだ。
控え室も、このあたりでは中原防衛の声が高かった。加藤十段の玉は8筋を詰められていかにも姿が悪い。一方、中原名人のほうは、6一角がきてもビクともしない堅陣に玉が入っている。
名人防衛か
さあ、中原の猛攻が始まった。7筋の玉頭攻めだ。5六金から飛車を手に入れて、優勢は更に固まった。まさか、あの冷静沈着な中原名人がこの将棋を負けることは考えられなかった。あるとすれば第5局の必勝の局面で4一銀の勝負手に対して時間がありながら2三金上とした大悪手の再現である。しかし、それは思い浮かばなかった。
午後6時半、東京の会館で谷川八段の解説が始まった。道場に入り切れなくて、研修室を臨時会場にし、田中六段が臨時講師になった。毎日新聞の会場もすでに満員、新宿駅前では折悪しく雨となったが、去りやらぬ大観衆が二上九段の解説に聞き入った。
中原の大悪手
再開後、間もなく中原名人が5四同金と銀を取り、8二角成とさせたのが大悪手。5四同金では4二飛と回れば「優勢というより勝勢」(丸田九段)だった。
午後8時46分、名人は4一銀に対して5三金と引いた。加藤名誉九段が「こわい、こわい」と言っている。5三金と引くようでは詰みを見損じているに違いないから、これは加藤名人誕生だと言うのだ。
あっという間の出来事だった。加藤名誉九段の指摘した通り、中原名人の玉はトン死を食ってしまった。
残り1分の加藤十段は読み切っていた。中原名人は1時間以上残しながら読み切れなかった。
ついに新名人誕生
午後9時2分に終局、ついに悲願二十有余年、加藤十段は名人位を手中にした。
翌朝、NHKテレビで新名人は「9時1分に即詰み手順を発見した。それまでは負けを覚悟していた」旨、語っている。
終局後
対局室は10年ぶりの新名人誕生で、ごった返した。取材陣は何十人いただろうか。しばらくは、こんなに大騒ぎするタイトルの交代はないのではないかという感慨がおこった。
9期10年もつづいた将棋界最高のタイトル名人位を失った心中は想像もできないほどだが、中原名人は打ちあげの席でも淡々と振る舞った。さすがに元気はなかったが、悪びれず、見事に最後を飾った。
加藤新名人も控え目ながら、にこやかに顔を出した。この人を目標に、挑戦者決定リーグ戦が始まった。敗れた側には申し訳ないが、将棋界には大きな刺激となり、プラス面も図り知れないと思う。
雨の中を対局者は次々に車で将棋会館を後にした。全10局で日程的にもきつかった。対局者もそうだが、新聞社も休刊日の前日の対局で、読者からお叱りを受けた。それを承知だったと言えば、開き直りだと、さらに叱られそうだが、全くやむを得なかった。
記録づくめにつけ加えれば、指し直し第8局の寸前に臨時規定ができ、千日手は即日指し直しが決まった。これが今後、本規定にどう盛り込まれるか、関心の集まるところだろう。
(以下略)
————————
1持将棋2千日手を経ての名人戦最終局。千日手即日指し直しではない時代だったので、実質的には第10局。
そのようなこともあって、対局場は東京将棋会館特別対局室。
立合いが木村義雄十四世名人というところが凄い。
————————
「再開後、間もなく中原名人が5四同金と銀を取り、8二角成とさせたのが大悪手。5四同金では4二飛と回れば『優勢というより勝勢』(丸田九段)だった」の局面はA図。
この局面からの△5四同金が悪手で、△4二飛なら中原誠名人優勢だった。
————————
「午後8時46分、名人は4一銀に対して5三金と引いた。加藤名誉九段が「こわい、こわい」と言っている。5三金と引くようでは詰みを見損じているに違いないから、これは加藤名人誕生だと言うのだ」の局面はB図。
————————
そして、加藤一二三十段(当時)にとっての第40期名人戦の大団円。
将棋世界同じ号の「秒読みに名人を見つけた」(記:編集子、解説:加藤一二三名人)より。
控え室の高段陣の検討で、いち早く結論が出た。▲5二同角成で加藤の勝ち!▲5二同角成△同金の時に、ちょうどぴったり中原玉が詰んでしまうのである。
中原、加藤ほどの棋士なら、詰みがあるといわれてこの局面を出されれば、恐らくノータイムで詰ますはず。それが、この時点では二人ともこの詰みには気づいていなかった。
(中略)
すぐ▲5二同角成を発見するかと思われた加藤がなかなか指さない。
控え室でも加藤が詰みを発見できないでいることがわかってきた。一体どうなるのか。いろいろな期待といろいろな不安の混じった空気が充満している。
「天才加藤は見つけるよ」と声がした。河口俊彦五段だった。
加藤が1分将棋になった。
▲5二同角成△同金▲3二銀成△1二玉▲2二金△同銀▲同銀成△同玉▲3一銀まで、105手で加藤十段の勝ち
何時間にも思われるような8分間だった。加藤は詰みを発見した。ただし、▲5二同角成とした時ではなく、中原が△同金と応じた瞬間に詰みが浮かんだのだという。
終了の8手前、時間にすればわずか1分足らず前になって加藤は勝ちを見つけ、名人位を見つけた。
控え室では加藤が▲3一銀(投了図)の好手をなかなか発見できずにいたと見たが、加藤が発見できずに苦しんでいたのは▲3一銀△3三玉の時の▲3二金の変化だったという。難しい▲3一銀は見えても平凡な▲3二金が見つからない。それが名人位の持つ重さなのであろう。
————————
1982年7月31日午後9時2分、加藤一二三名人が誕生した。
20歳の時と33歳の時には名人奪取はならなかったが、42歳で名人位を獲得した。
————————
「おやつ類は一切必要ありません」と言い、お茶も飲まなかった加藤一二三十段。
これには理由があったのだが、それはまた明日の記事で。