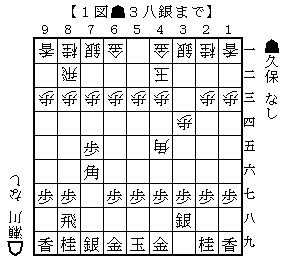将棋ジャーナル1984年2月号、才谷梅太郎さんの「棋界遊歩道」より。
棋士とは総体的に、楽観派が多い。それも天性の躁病患者と思われる者がごまんといる。
その正体を少々あばいてみたいが、この病名を聞いてまず目に浮かぶのは米長邦雄氏である。
まだ奨励会時代の米長氏に、あの「○○○事件」がある。
その日、米長氏は同期の桜の大内延介氏と、ネオンの新宿を出発点として呑み続けていた。二人とも20歳前後であり、体力はあり余っている。
若さにまかせて午前1時すぎまで呑んでいたが、それまで特に変わった素振りをみせなかった米長氏は、突然こう言い出した。
「大内君、これから芹沢先輩の家に遊びに行こう」
日頃から芹沢氏の舎弟分のような存在で、金がなくなると酒はむろんのこと、食事までごちそうになっていた米長氏だが、そんなやさしい先輩に、今日は常日頃お世話になっている御礼が言いたいという。
むろん大内氏は止めた。なんといっても時間が時間である。しかし米長氏は、
―だいじょうぶ、
だと言う。さらには、
「先輩にとっては、実弟のように可愛らしい僕ら二人を、あのやさしい芹沢先輩が追い返すはずがない」のだと言い張ってきかないのである。
―そこまで言うなら。
大内氏は、こう考えたかもしれない。さらには、
―またヨネのやつ、病気が出始めた。逆らうとウルさいから、しばらく話を合わせておくか。
と、こう思ったかもしれず、こちらの方がより人間臭い、楽しい想像ではある。
ともあれ二人は、店を出た。そして結婚後まだ間もない、芹沢宅へと向かったのである。
時刻は午前2時に近い。
二人はすでに芹沢家の近くに来ている。大内氏にすれば、これは意外だったかもしれない。
当然、こんなところまで来るつもりはなかった。店を出たところで、
―まあまあ米長君。もう遅いことだし、俺がおごるからもう一軒行こうや。
と言ったことであろう。
しかし躁状態に陥った米長氏は意外なほど執拗だった。どうしても行く、という。
冷たい夜風の中を歩けば、少しは頭も冷えるだろう、と大内氏は考えざるをえなくなった。それにこんな状態の米長氏を、一人放置するのは危険である。何をしでかすか判らない。
ともあれ、こうして今二人は芹沢家の近くに来た。
芹沢・大内両氏にとって不幸だったことは、そこに公衆電話があったことだ。
「大内君、10円玉を貸してくれ」
何を思ったのか、米長氏は突然おかしなことを口走った。
「まさか芹沢先輩のお宅に、電話をするんじゃないだろうな」
大内氏は、恐怖の念を体内に充満させながら反問した。
―そのマサカだよ。
ある程度予想していた返事だったとはいえ、これを聞いた大内氏は大いに狼狽した。
―こんな時間に電話……。しかも日頃…せ、世話になっている先輩の家に。
大内氏が、ここまで取り乱したのかどうか確証はないが、ともかく10円玉を貸さなかったことだけは間違いない。
しかし、対する米長氏は少しも困った素振りはみせず、
「なんだ貸してくれないのか、ケチ。それじゃ仕方ない、自分のを使うからいいよ」
と言うや、さっそくダイヤルを回しはじめた。
かたわらの大内氏は依然として心配顔ながら、それでもようやく腹をくくった様子である。
「あっ、芹沢先生ですか、おはようございます。米長です。これから先生のお宅に遊びにうかがいたいのですが。―えっ、ああ、もちろん酔っ払っています。えっ、何時だと思っているのかって?ええっと、ただいまから午前2時7分20秒を、お知らせします。―えっ、私はフザケてはおりません。―はあ。それもそうですね。それでは先生のお宅にうかがうのは、残念ながらとりやめといたします」
極度の緊張の中に、この会話の一部始終を聞いていた大内氏。
―どうやら最悪の事態だけは免れた。
と、ホッと安堵の胸をなでおろした時だった。米長氏は電話は切らずに、もうヒト言つけ加えた。
「とりやめにしますが、ここまで来ておいてこのまま帰るのも味気ないな。そうだっ、これから大内君といっしょに先生の家の庭に入って、芝生の上にオミヤゲを置いていきます」
そこまで一方的に喋りまくると、米長氏はようやく受話器をおいた。
そして翌朝……。
朝一番に庭に出た芹沢氏が、芝生の上に見たものは一塊の朝露に濡れた○ンコだった。
さすがの芹沢氏も、ただ唖然とするばかりであったとか。
追記―電話のあと米長氏は、嫌がる大内氏を無理矢理に芹沢家の庭に引きずり込み、芝生の上に○ンコをするように強要した。
仕方なく芝生の上にしゃがみこんだ大内氏であったが、酔いが吹き飛んでしまっているため理性が邪魔をして、どうしても事をなすことができない。
数分後、隣で踏ん張っているはずの米長氏はと見ると、すでに出すものは出して、サッパリとした顔でこちらを覗き込んでいた。
結局、大内氏は何もできなかったのである。
(以下略)
* * * * *
紙は持っていたのだろうかと心配になる。