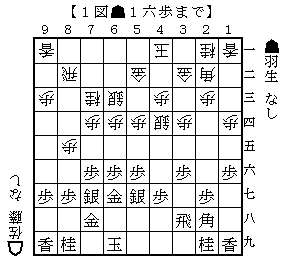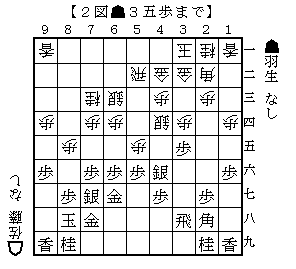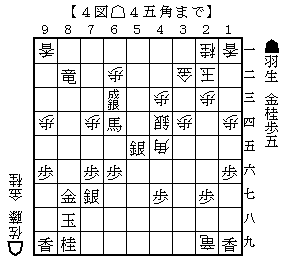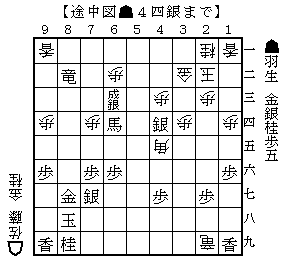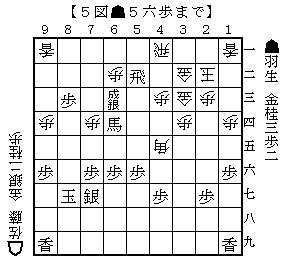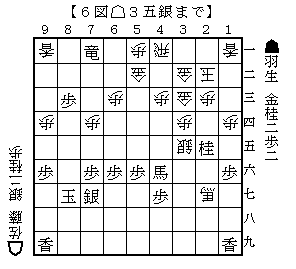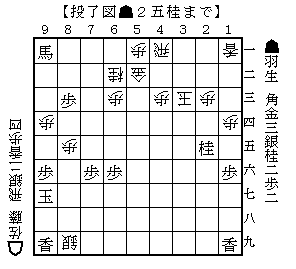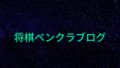将棋世界1996年2月号、中野隆義さんの第8期竜王戦第6局〔羽生善治竜王-佐藤康光前竜王〕観戦記「理をこえる闘志」より。
1日目夕刻。1図・羽生▲1六歩までの局面を前に、控え室は佐藤がどう出るかに注目していた。
飛車先不突き矢倉に急戦を目指す佐藤に対し、羽生は角を右翼に転換して後手の攻勢を徹底的に牽制しようという作戦を取った。
1図をご覧になれば、2八角のにらみが強く後手が容易に△6五歩を突けない形である事がお分かりいただけよう。これでは後手から撃って出るのは無理筋となる公算が高い、というのが控え室検討陣の一致した見解だった。過去のデータからも、急戦を挑んだ場合の後手側の勝率がかなり良くないことが分かってもいる。
控え室の面々は、正立会人・石田和雄、副立会人・塚田泰明にNHK衛星放送解説の森下卓、同聞き手の鹿野圭生女流初段ら、記者らにとって大変心強い顔ぶれである。
急戦を仕掛けようというのがうまくないのでは後手の作戦負けかと思えるところだが、ここで石田九段が提唱した後手の作戦に一同はうなった。
「△5一玉~△6二玉としてね。手損でつまらないようですが右玉はどうでしょうか」
先手が受け身に勝った駒組みであることを計算に入れた柔軟な指し方である。先手陣は、後手から攻めてくれば手厚さを利してのカウンターパンチが繰り出せて都合が良いのだが、自分の方から先陣を切っていくとなるとそれができにくい形なのだ。
「そうですね。右玉にすれば作戦負けどころか逆に作戦勝ちになる可能性までありますね」と、森下。
待ったの利く継盤ではさっそくいくつかの想定手順が並べられては崩されていった。なかなか先手良しの展開は現れない。後手の急戦を押さえた先手が、今度は打開に苦しむ流れになるのだった。
「千日手の恐れなきにしもあらずかあ」石田のつぶやきを受けて、読売新聞の観戦記担当の池崎和記さんが「ほんとですか。ちょっと待ってくださいよお」と悲鳴に近い声を上げた。彼氏は、明日の朝刊用の観戦記第1譜から翌々日用の第3譜までの原稿を入れ終え、さあこれから観戦一本に集中できるぞと一安心しているところなのであった。それが、この将棋が千日手になって観戦記に使われない可能性が出てきたというのでは心中穏やかならずは当然である。
(中略)
本局が、序盤で互いに手を出すことができずに千日手となり、せっかく池崎さんが書いた原稿がパーになってしまうのは、正直に言って当方にはなんの痛痒もなきところだが、ファンが固唾を飲んで注視している大勝負が駒もぶつからぬまま無勝負となってしまうという興ざめは、なんとしても避けて欲しいと祈っていた。
「佐藤くん、右玉にしないんじゃないかな。棋風からいっても嫌いでしょうし……」
自信なさげではあったけれど、この塚田の予想にしがみつくような気持ちでモニターに映し出されている盤面を記者は見ていた。池崎さんは棋士の気概を見つめる観戦記者だ。口では原稿がフイになることを気にしている風なことを言ってはいても、心の中は記者と同様の気持ちで盤上を見守っていたと確信している。
佐藤が唇を真一文字に結んで5二の金を4二に寄せるのを見たとき、記者は感動した。おそらく、佐藤の行く手には険しい茨の道が待ち受けていよう。それをあえて承知の上で金を寄り、この大勝負においてあくまでも攻めに出る策を貫こうとする棋士の姿を目の当たりにしただけでも、ここへ来た甲斐があったと思った。棋風には方向性があり、方向性があるがゆえに対応の限界もまた生じてくる。自分ではこう指したいと思っても過去のデータはそれを否定している時、棋士は決断の断崖に立たされるのだが、その時に自分の道を進めぬ棋士を、かの山田道美は不幸と断じている。
作戦的見地からみれば、佐藤の採った指し方は大いに疑問があると言われても仕方がないものと記者は思う。仮に1図の局面から、①本局のように攻勢を採る。のと、②右玉にしてチャンスをうかがい。という二つの指し方をそれぞれ千局ほどもプロ棋士同士でシミュレーションしてみれば、後手にとっての勝ち負けの確率はかなりはっきりと②の方が優ると出るであろう。しかし、これをもって佐藤は変なやつだとは、記者は決して思わない。むしろ、このような棋士がいることを誇りに思うものである。
最近、先崎が「これからは自分の好きな手を指しまくる」と宣言していた。頼もしく拝聴させてもらった。
右玉の作戦を採用せずに急戦指向を押し通そうとする佐藤に対し、衛星放送の森下解説は、
「△4二金右とした後手陣は、角の転換が利かないなど発展性がない形で、前に出るしかないという恰好です。佐藤前竜王は、すでに3敗を喫して七番勝負で後のない背水の陣に立たされていますが、本局でも前に出ようという背水の陣で臨もうという訳ですね」
(中略)
さて盤上。2図▲3五歩の際どい利かし一発に、羽生の危機感が現れている。
佐藤の攻めの強力さをしかと踏まえた上で理想的な迎撃の陣を敷き、駒組み段階では先手上々の首尾であったと言える。今、佐藤が△5五歩と牙を剥いてきたのは控え室でもっとも本命視された仕掛けであり羽生の予測にも十分入っていた展開であろうことが察せられる。つまりは模様が良いと見られる羽生が自然な流れに乗っているということで、控え室では盤上の形勢をかなり羽生寄りに見ていたのだが、実際の盤上、というより正確には羽生-佐藤戦においてというべきかもしれぬ優劣を吊るす天秤はそれほど傾いてはいないのであった。▲3五歩は、普通に指せばよいという感覚では到底なく、ぎりぎりを走り抜けなければ勝ちはつかめないという決意のこもった一手である。
(中略)
先に1分将棋に追い込まれたのは佐藤だったが、羽生の残り時間もみるみる減っていく。▲8五飛と回った辺りでは余裕が感じられた羽生の所作だが、それも指し手が進むにつれて頼りなさげなものに変わっていった。
佐藤の△4五角(4図)は、控え室に居並ぶ棋士の中から「えーっ、こんな角打たれて大丈夫なのオッ」と、声があがるほど強烈窮まりない一打である。
「50秒……」と、記録係が読む声に羽生は、ハッとしたように振り向く。まだ4分の余裕があるのだが、おそらくそれを一瞬忘れたのだろう。1分将棋なら「1、2……」と続くはずの声がしないことを確認し、羽生は再び読みに没頭すべく心を盤上に戻した。瞬時とはいえ、これほどに動揺している様を見たのは初めてだった。
「逆転だ」とカメラマンの弦巻さんの声。記者もそう思った。
4図以下の指し手
▲4四銀△8九竜▲9七玉△9五桂▲3三歩△同桂▲4一銀△8七桂成▲同竜△同竜▲同玉△8一飛▲8三歩△4一飛▲3三銀不成△同金▲5二飛△3二金打▲5六歩(5図)佐藤は確かな手応えを感じとっていた。逆襲のパンチはカウンターとなって羽生陣の急所に命中し、ガクッと敵の膝が折れるのが分かった。
しかし、ここで攻めの手綱を緩めるどころか、それをぎゅぎゅっと引き絞ったのが羽生の恐ろしいところだった。深手を負いながら▲4四銀(途中図)となおも踏み込む羽生に盤側は肝をつぶした。
△8九竜から△9五桂と、再び佐藤のパンチが羽生の顔面をとらえた。▲同歩なら△同歩▲8六玉△9四金と縛るハラである。難解ながらこれで勝負だ、と佐藤は思っていただろう。
しかるに▲3三歩から▲4一銀というのはなんたる態度であろうか。顔面を血に染めながら羽生はさらに前に出ていったのであった。記者が佐藤の席に座っていたら、殴っても殴ってもグイグイ近づいてくる羽生に、恐ろしさのあまり裸足で逃げ出していたに違いない。勝負の際は狂気の世界、と羽生は言ったが、確かにそうかもしれぬと思わされる。
△8一飛の王手銀取りで4一の銀を抜いて、佐藤は自軍の優勢を意識したという。その大局観に狂いはないと思う。
5図以下の指し手
△6三歩▲4六馬△5一歩▲6二飛成△5二金▲7一竜△2七角成▲2五桂△3五銀(6図)以下略△6三歩とおいしく成銀を取って後手は大きな駒得となった。これで十分と佐藤が見たのもむべなるかなである。
△6三歩で、△6三角と角で銀を取っていればおそらく佐藤が勝っていただろう。感想戦で、羽生は、△6三角には▲同馬△同歩▲2五桂を予定していたが以下△4二金打▲3三桂成△同金直と先手を取られて負かされそう、と思っていたと言っている。勢いとはいえ▲6三同馬と切って▲2五桂とはまた凄い攻めっ気だが、それよりも駄目そうだと思いながらも突っ張りまくろうとする羽生の勝負気合には目も剥くばかりである。
△5二金と竜をはじき、△3五銀(6図)と馬をはじいて、後手陣がどんどん堅くなっているように見えるのは実は錯覚で、真実は駒を投入させられることによって後手は指し切りに陥ってしまったのである。
切った張ったのやり取りが続いていただけに、折角薄くした敵玉の周りに金銀を打ちつけられる路線は先手側がイヤな感じがするところだが、ここに勝ち筋を見出した羽生の嗅覚はさすがであり、相手をそこに追い込んだ立ち回りはさらに見事であった。
自玉を安全にした羽生は、桂馬の爆弾で佐藤陣の金銀を一枚一枚吹き飛ばし、勝利に向かって確実に進んでいった。
まばたき一つ。続けてパパパパパパと6度のしばたきをした直後「あっ、負けました」と発して佐藤は投了した。
「羽生は、佐藤の勝ち筋を踏みつぶしてしまったですね。無理矢理に」
誰にともなく言って記者は胡座の中に身を沈ませた。
勝負所での羽生のすさまじい闘志に盤側のみならず本局では佐藤も圧倒された。戦いの勝ち負けとは、本来このようにして決するものではないだろうか。
* * * * *
「佐藤が唇を真一文字に結んで5二の金を4二に寄せるのを見たとき、記者は感動した。おそらく、佐藤の行く手には険しい茨の道が待ち受けていよう。それをあえて承知の上で金を寄り、この大勝負においてあくまでも攻めに出る策を貫こうとする棋士の姿を目の当たりにしただけでも、ここへ来た甲斐があったと思った」
1図から後手が右玉にすれば温暖な気候の世界が待っているところ、北極圏に突入するような気合いを見せた佐藤康光前竜王(当時)。
森下卓八段(当時)が話したように、「佐藤前竜王は、すでに3敗を喫して七番勝負で後のない背水の陣に立たされていますが、本局でも前に出ようという背水の陣で臨もうという訳ですね」という、正真正銘の背水の陣。
* * * * *
「しかし、ここで攻めの手綱を緩めるどころか、それをぎゅぎゅっと引き絞ったのが羽生の恐ろしいところだった。深手を負いながら▲4四銀(途中図)となおも踏み込む羽生に盤側は肝をつぶした」
▲4四銀(途中図)は「肉を切らせて骨を断つ」の数段上をいくほどの強手。
「顔面を血に染めながら羽生はさらに前に出ていったのであった。記者が佐藤の席に座っていたら、殴っても殴ってもグイグイ近づいてくる羽生に、恐ろしさのあまり裸足で逃げ出していたに違いない。勝負の際は狂気の世界、と羽生は言ったが、確かにそうかもしれぬと思わされる」の中野さんの表現が絶妙だ。
* * * * *
「△5二金と竜をはじき、△3五銀(6図)と馬をはじいて、後手陣がどんどん堅くなっているように見えるのは実は錯覚で、真実は駒を投入させられることによって後手は指し切りに陥ってしまったのである。切った張ったのやり取りが続いていただけに、折角薄くした敵玉の周りに金銀を打ちつけられる路線は先手側がイヤな感じがするところだが、ここに勝ち筋を見出した羽生の嗅覚はさすがであり、相手をそこに追い込んだ立ち回りはさらに見事であった」
羽生善治六冠(当時)の将棋があまりにも恐ろしい。
* * * * *
「羽生は、佐藤の勝ち筋を踏みつぶしてしまったですね。無理矢理に」
「勝負所での羽生のすさまじい闘志に盤側のみならず本局では佐藤も圧倒された。戦いの勝ち負けとは、本来このようにして決するものではないだろうか」
コンピュータの評価値など関係ない。これが勝負の本質だと思う。