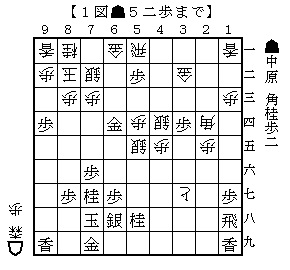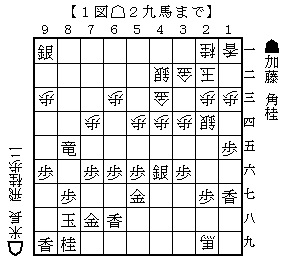将棋世界1983年1月号、金子金五郎九段の「将棋を考える」より。
われわれプロは感覚という言葉を使う。たとえば、同じ棋力の同士の対局がすんだ後、感想戦に移ったとき「この手は自分の感覚とちがっていた」などという。大局的な意味であるが、その手の持つ意味をいう場合もある。
手の意味を具象的に現せば<形>という図形的なものでしかないであろう。さて、この図形に対する感覚ということになってくる。それに対する形勢判断もまた”感覚”といっている。私の将棋論も感覚を基にして、すすめたいと思っている。
5、6歳の小児が成人を負かす例は案外多いようである。経験において絶対すくないはずなのに、これはどこに原因があるのだろうか。そのもとは知覚からであろう。考えることより抵抗すくなく外界(盤のマス目と駒)を受けとれるからである。
もちろん知覚だけで指せるわけはないからそれに「何か」加わるものがある。このようなものが或いは心理学でいうところの直観像というものかも知れない。
ゲーテだったと記憶するが、ある作品で、庭前にあるツタの葉の一つ一つを思い出によって明瞭に描写している。これは目の前で見なくては書けないものだといわれ、心理学者は「ゲーテは直観像の持ち主であったかもしれない」といっている。
しかし直観像の現象は小児の場合には多くみられるが成人になると薄れるか消滅するという例が多い(その点、ゲーテは例外であった)。なぜそうなのか、私は考えてみたことがある。たぶん、成人になると判断力などを用いる結果、直観像の必要が少なくなる自然の摂理のようである。
直観像のことは別として、将棋には写像という能力が思考以前に働いているように私には考えられるのである。
もう一つの実例になるとおぼしきものをあげてみたい。木村義雄さんや私などと同年輩の青年に根岸勇四段(脳を病んで早世した)がいた。早指しで特徴のある棋風の天才であったが、記憶力はきわめて低かった。タバコを買いに行って3種類のはずを1種類3個買ってくるということ、ザラであったという。これは金名誉九段から私が直接聞いた話である。推理能力も弱かった。だというのに早指しで強かったのである。
これなどを思うと、思考より抵抗がすくなくてもすむ感覚を主体にした将棋であることは、ほぼ間違いない。あるいは直観像というものかもしれない。
天はその人に必ず何かお与え下さるというが、根岸君はこのような人であったように思う。つつしんで御冥福を祈る。
この2つの例から推して、写像力というものの重要さが証明されると思う。プロが100手読むとしても、変化をふくめて25手を4つの場合と100手を一線にして読んだ場合をくらべれば、後者は先に読みが進行するにしたがって写像はかすんでみえるようになるし前者は25手でおわり、さらに改めて25手を読むのだから写像は明瞭のはずである。これは感度という度合いの問題として考えることができるかもしれない。
また記憶力の強い人は、かすんでみえる写像を記憶で補強するということは充分考えられるが、それは根岸君の例のような写像を主にする人の証明にはならない。
(以下略)
——–
なるほど、将棋の強さに記憶力はあまり影響していないということなのか、と思いながら金子金五郎九段の文章を読んでいるうちに、私が中学生の時に読んだ将棋世界に載っていたある投稿を思い出した。
将棋世界1972年7月号、読者欄「声の団地」より、増田永三郎さんの「駒を取る少年」。
両毛線前橋駅の将棋好き助役が、
「増田君一度来てみろよ。面白い小僧で皆んな駒を取っちゃうんだ」と私にいったのは、確か木村十四世名人が入段したかしない頃だから、もう50年以上も昔のことだ。
その頃国鉄桐生車掌区に勤めていた私は、専ら両毛線(小山、高崎間)を乗務したが、この沿線のアチコチの駅で、よく将棋が指された。というのは殆どの駅員は「徹夜」勤務で、朝出勤して翌朝退出するまでの24時間中一睡も許されなかった。随分酷い勤務だが当時の我々は「徹夜」とは夜を徹するものと割り切っていたからなんの不満も感じなかった。不満は感じなかったが、しかし人間生身であるのをいかにせん。午前零時過ぎともなれば濃厚な睡魔の襲来があり、余っ程しっかりしていないと、ついウトウトしてしまう。信号機扱いをウッカリして、入って来る列車を真っ暗な場外(駅入口)に停めたりするのは大抵そういうときだ。
そのウトウトを将棋でふっ飛ばそうというのである。私が夜の乗務で駅長事務室に入って行くと、テーブル上に板盤を乗せて指しているのを、5、6名が円く囲んで観戦してるという光景をよくアチコチで見たが、ときには傍から駅長が、
「増田君、居眠りよけはこれが一番だよ」などといって、すでに将棋大好きの私の首を大きくコックリコックリさせ、そうしてニンマリほくそ笑ましたものである。
―「面白い小僧」は将棋好き助役がいうには15、6歳。毎日駅待合室に遊びに来ていて、駅員が昼間でもヒマを見て休憩室でパチリパチリ始めると、必ずその仲間に加わる。将棋は断然強く、休憩室のザルにはなんとも歯が立たんが、オカシイのは小僧、頭金で詰んでいる敵玉はそのまま、一つ一つ片っ端から駒を取ってしまうのだ。
「……ここが少し悪いんだよ」と助役は我が頭を叩きながらいった。
小僧の、いや少年の対局振りを私も一、二度見たが、全く助役のいう通りだった。この少年こそ木村義雄少年と殆ど同時に関根名人の門下生となりながら、しかも天分木村以上と期待されながら、惜しやいくばくもなく脳を煩い家に帰されざるを得なかったN少年その人なのを、私は間もなく知った。私は思う。もし少年が健康だったら必ず木村名人と共に関根門の双璧となり、近世将棋界の図柄は実によい色合いになっていたろうに、と。そうして改めて、健康は人間最大の幸福なことを思うのである。
今、次代を担うと目される中原十段、加藤一二三、米長、大内八段等は健康そのもののようである。明日の棋界の発展が確約されているようで、私は嬉しい限りである。
——–
増田永三郎さんは埼玉県の上尾支部長を務められた方で、関東アマ名人戦でも活躍されている。
——–
調べてみると、根岸勇四段は木村義雄十四世名人と同じ歳で、木村十四世名人も認めるほどの天才少年だったということが分かった。
棋界における真の天才とは、根岸君の如きをいうのであろうと、私は今でも思っている。(木村義雄『将棋一代』) ※群馬県出身の根岸勇は、木村と同年で、木村の若き日のライバル。健康を害して、四段で亡くなった。
— 将棋パイナップル2.0 (@shogi_pineapple) June 25, 2014
1905年生まれの木村十四世名人が関根金次郎十三世名人門下になったのが1916年。1920年には四段、1921年に五段になっており、根岸勇四段が四段になったのも同じくらいの時期だったようだ。
「駒を取る少年」が駅に来ていたのは四段になった後のこと。
記録を見ると、根岸勇四段の棋譜は1925年まで存在しているので、群馬に戻った後も対局は数局あったようだ。
仕方がないこととはいえ、好きでなったわけでもない病気で故郷へ戻って、とても寂しい思いもしたことだろう。
また15、6歳だった当時の少年のことを思うと、胸が痛くなる。