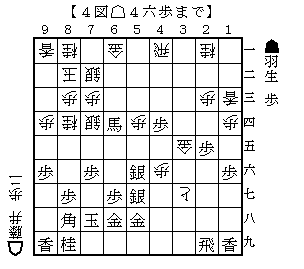将棋世界2002年2月号、内田康夫さんのエッセイ「『羽生マジック』ウィルス説」
昭和61(1986)年―に何があったかなど、大抵の人は思い出せないだろう。じつはこの年から羽生善治は日本将棋連盟の公式戦に出場している。前年の12月18日に13勝3敗で奨励会を卒業、弱冠15歳でプロ棋士になって最初の年である。
ちょうどその頃、僕は『王将たちの謝肉祭』というミステリー小説を執筆中であった。登場人物に升田幸三、大山康晴、中原誠、芹沢博文といった当時の将棋界に君臨する人々をモデルにした一風変わった作品で、8月には出版する予定になっていた。
その4月、NHKのトーナメントに羽生四段が登場した。その登場ぶりがまことに見事なものであった。われわれ素人はもちろん、既成プロたちが度肝を抜かれたに違いない。解説者が意表をつかれ、何度も絶句するような奇手妙手が飛び出した。僕は感動して、急遽、執筆中の『王将たちの謝肉祭』に羽生少年と升田九段の出会いのシーンを設定した。そうしないではいられない、心を震わせるようなオーラを、僕はこの、触れれば折れそうな華奢な少年棋士に感じた。大物の予感と言っていいかもしれない。
「羽生善治」を語るドキュメンタリーやエッセイや小説は、無数にあるだろうし、これからも続々と現れると思うが、その嚆矢となったのは僕のこの作品だったと自負している。その後の羽生少年の活躍ぶりはいまさら書くまでもない。そうしてちょうど10年後、羽生善治七冠王が誕生した。
それからさらに5年を経て、七冠ではなくなったはいえ、羽生はいぜん将棋界の頂点にある。昔と違ってパソコンによる研究が発達した現在、他の棋士がなぜ羽生の牙城を突破できないのか不思議な気もする。羽生といえども神様でないのは、先頃の棋戦で一手詰めをうっかりした大ポカを指したことでも明らかだ。それにもかかわらず―である。たとえば第4局の藤井システムなど、序盤から中盤にかけては成功したかに見えるのだが、終盤にきて何かが狂ったように破綻する。
僕はその理由を、羽生の思考回路が他と異なるのだと思っている。他の棋士のパソコンは、思考回路がひたすら効率的に最大の成果を目指して進むのに対して、羽生の場合は思考回路のどこかにウィルスが潜んでいて、思いもよらぬアクシデントを発生させるに違いない。前述の藤井竜王の終盤の「乱れ」も、そのウィルスの仕業としか考えられない。たとえば第5局の▲5四桂から▲4二桂成と、敵玉から遠い方へゆくのは、ヘボの僕ならそう指しそうな気がする手で、解説者も「ないでしょう」と言っていた。たぶんパソコンの頭脳にもなかっただろう。「羽生マジック」の正体はじつはウィルスだったと思うと、妙に納得できるのである。
—————-
昨日の記事「羽生善治四冠(当時)の一年がかりの雪辱」を見ると、内田康夫さんの羽生マジック・ウィルス説が本当に思えてくる。
▲4二桂成で藤井猛竜王(当時)のハードディスクにウィルスが仕込まれ、▲5三成桂でウィルスが起動するといった雰囲気。
—————-
『王将たちの謝肉祭』は電子書籍で出ている。
私も入手したので、感想などはまた後日に書きたい。