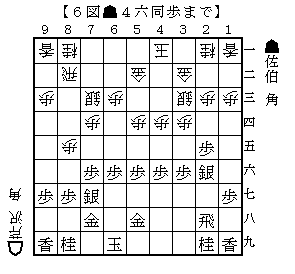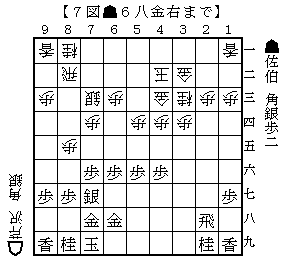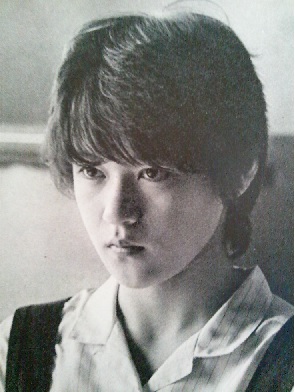将棋マガジン1984年1月号、川口篤さん(河口俊彦五段・当時)の「対局日誌」より。
午後3時
昇降級リーグ戦2組の対局美である。5回戦まで進み、板谷、前田、佐伯、芹沢といった全勝者が登場する。
顔ぶれを見ればみな一癖も二癖もあるし、その彼等が全力を尽くして戦うのだから、きっと劇的な場面が出現するだろうと思った。ところが、それが大違い。妙にシラけた一日になってしまったのである。
ま、釣りに行ったら一匹も釣れなかったり、野球を見に行ったら雨で中止になったり、デートの約束をすっぽかされたり、その他、予定していた印税が振り込まれなかったりと、人生アテが外れることはままある。そんなわけで、この日は雑談で頁をうめることにする。
とりあえず対局の模様をザッとお伝えしておこう。
(中略)
大広間と第二対局室のリーグ戦は例のごとく、どこも夜戦は必至の構えをしていた。中の、芹沢-佐伯戦は6図。芹沢が4筋で角を交換したところだが、ここで長考している。いうまでもなく攻め筋を組み立てているのだ。
しかし、78分考えて、結局急攻を断念した。芹沢がいうには「5筋と7筋をカラんで、サッサーとやっちゃうつもりだった。ところがどうしてもうまく行かない。△4三金右と上がる時には負けたと思っていた」
6図からの指し手
△4三金右▲3五歩△同歩▲同銀△3四歩▲2四歩△同歩
▲同銀△同銀▲同飛△2三歩▲2八飛△3三桂
▲7九玉△4二局▲6八金右(7図)右の手順が指されていた頃、私は盤側で芹沢と雑談を交わしていたのだが、まさか彼が負けと覚悟していたとは知らなかった。早いとこ勝負をつけなければ、もし11時頃まで引っ張られたら必ず体力負けする、という感じはよく判るけど、7図で「すでにいけない」とは芹沢らしい。
それにしても▲6八金右は勝ち方を知っている手だった。7図以下、芹沢は△4七角と打ち込み、自分から、まな板に乗ってしまうのである。
午後7時20分
食事に外へ出て、戻ったら4階の入口で、芹沢と板谷にバッタリ逢った。芹沢が「ちょうどいいところだった。どこかへ行こうじゃないか」と誘うので取材はお終い。小生甘い誘惑にはからっきしなのである。芹沢が行くのは、いつか紹介した青山のレストランに決まっている。あの時はとなりに多岐川裕美さんがいたっけ。今日もだれか美女がいるに違いない、と瞬間読んだのだが、これも当然ながらアテが外れた。
(中略)
さて、日本風に上品に、さっぱりと作られているイタリア料理とワインの食事をしながらの話だが、板谷がいると、どうしても将棋界のことになってしまう。心がなごむような、食欲が増すような話は出ないが、そのうち芹沢がうちあけ話をはじめた。
「深夜Aから電話がかかってきて、広島だけど代わりに講演に行ってくれないか、という話なんだ。それがいい仕事でね、なんでキャンセルするのかと調べたら、Aは将棋の日の出演を依頼されて、そっちを引き受けたんだな。オレは参った!と思った。将棋のことならどんな犠牲でもはらう、という将棋に対する想いがすごい。オレなんかとうてい及ばないね」
板谷が金額を確かめた。講演料は一般サラリーマンの平均月収をはるかに超え、一方将棋会館の出演料はその10分の1ぐらいか。それを知って板谷は「近頃まれに見る美談だな」とうなずいた。
そんな事情で、ここにちょっといい話として誌した。特にAとしたのは、実名だとご当人が照れくさいと思うからで、本欄の読者なら、それがだれかはすぐ判るだろう。
(中略)
さて、レストランでの話は延々と続き、アルコールが回るにつれて芹沢はますます昂揚してきた。一方勝った板谷はアクビをもらしはじめた。時刻は午前0時である。店が終わってようやく帰ろうということになった。
外に出てみると、いつのまにかどしゃ降りになっていた。ようやくタクシーをつかまえて乗り込んだが、車中でも芹沢は熱っぽく将棋界のことを語り続け、となりの板谷はいびきをかいていた。
—————
6図で後手負けというのだから将棋は恐ろしい。
たしかによく見てみると、後手が2手遅れている。
早見えだった芹沢博文八段(当時)にとっては、耐えられないような進行の将棋だったのかもしれない。
—————
Aは米長邦雄王将(当時)のことだと思われる。
—————
青山のイタリアンレストラン。
私は東京に長年住んでいたのに、青山で酒を飲んだり食事をしたことは二度しかない。
これは青山が嫌いなのではなく、行く機会がなかなかなかったことが大きい。
青山の周辺である六本木、赤坂、千駄ヶ谷、渋谷は数え切れないほど行っていたのに、青山にある店に入るという機会がなかった。
そういう意味では、私にとって青山は神秘性を持った街のままになっている。
隣の席に多岐川裕美さんがいたら、それはビックリするだろう。
—————
私も六本木のある店で、隣が志村けんさんだったことがあり、こういう時は知らんぷりをするのが礼儀ということで、隣を見たいのを我慢して酒を飲んでいたことがある。