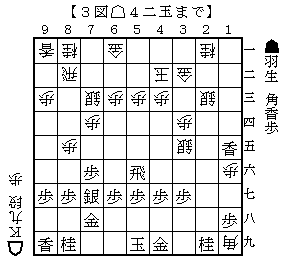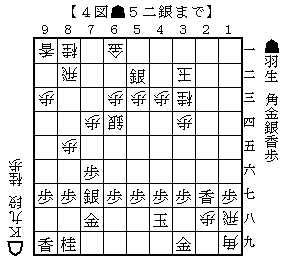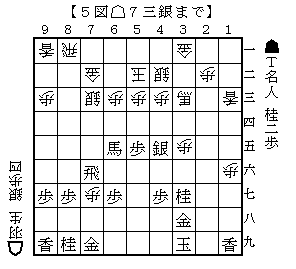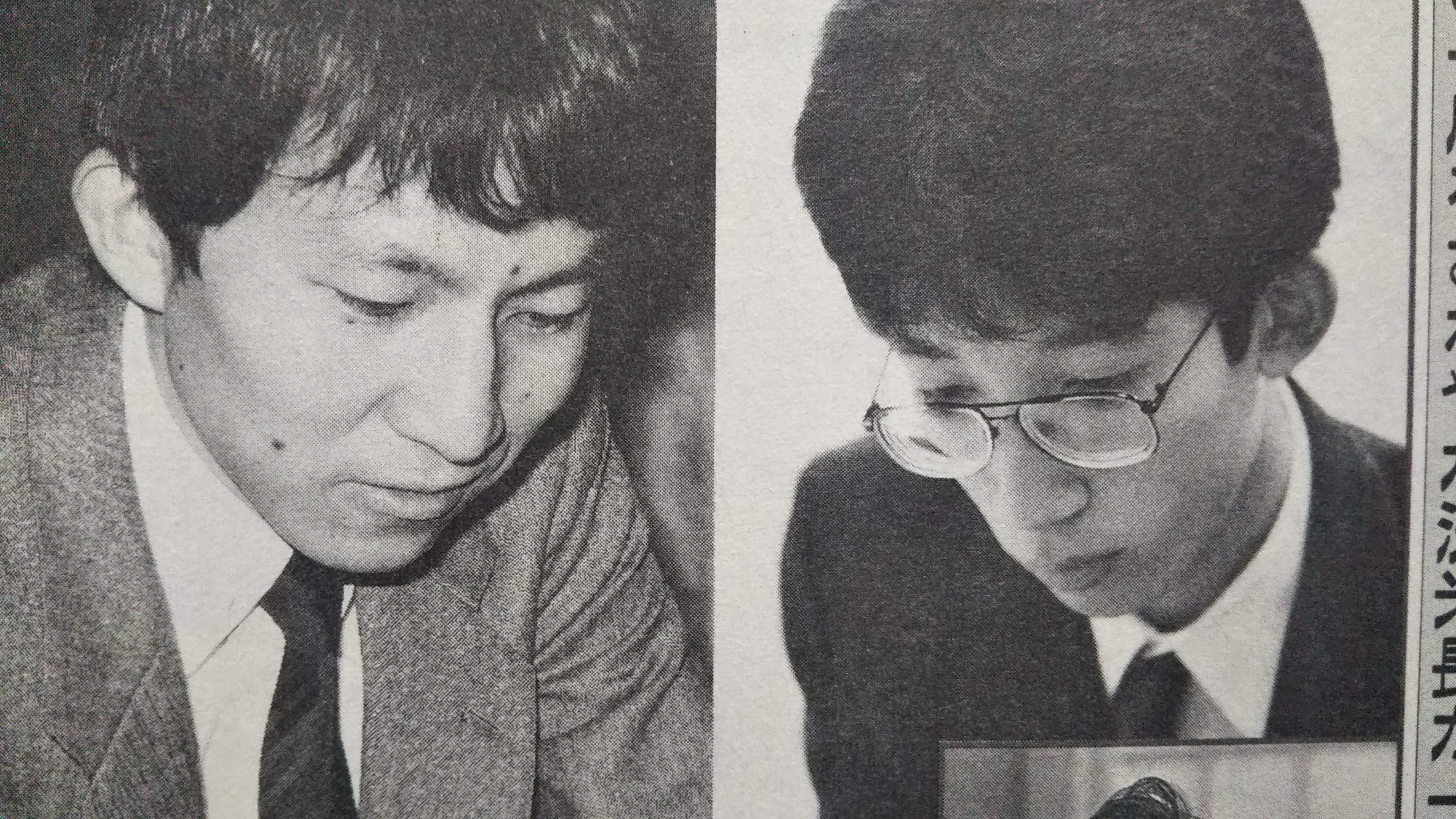将棋世界1989年6月号、二上達也九段の「ハブの世界」より。
お断り
師弟といっても名ばかり、技術的に何を教えたわけでなし、むしろ教わったらと言う皮肉な声を聞かされる。
第一教えたから強くなれるものではない。たとえ少々強くなったところで師匠以上になれるはずがない。
独自の自分なり工夫するものを持っている者が先達を乗り越えられる。
羽生将棋の分析を編集部から依頼され何気なく引き受けたものの、よく考えれば分かっちゃいないことを書かねばならないのだから無茶なはなしだ。
自分の肌で感じるものがあれば、多少なりと論評ができよう。成長段階にあるものをとらえたところで、翌日は見当外れになる。
いささかやっつけになることを断っておきたい。
珍事にあらず
今、将棋界は10代棋士、いわゆるチャイルドブランドに席巻されている。
この現象について質問を受ける機会が多く、いやおうなく考えざるを得ないわけだが、はたして昨今だけの特異な状況であろうか。
曰くパソコン棋士、コピー将棋、グループ研究の成果、いずれもしかりと言えるし、しからずもである。
確かに社会構造の変化と時代の流れに応じての発現であると言える。
時代を読む手法として歴史を学ぶのがよかろう。
印達、宗銀、宗看、看寿など若き俊英の輩出した時代を見るまでもなく、近くは若き日の大山十五世、中原誠の活躍、18歳八段の加藤一二三。
何も今の時代だけの珍しい現象ではなかろう。
将棋というゲームの持つ特質が若くして頭角をあらわす者達を育む要素を持っているのだ。
名前が出て喧伝されるのは要するにシステムの問題であろう。
シード権の配慮こそあれ、全員参加の制度下のもと、可能性が結果に出たのである。
いずれにしても10代棋士の活躍度の高さは大したものだし、代表される羽生君の将棋について考察を巡らすのは意義なしとはすまい。
独特の雰囲気
羽生将棋を最初目にしたのは、小学生名人戦でのものだったと思う。
将棋の作り方は記憶にないが、きわどい頑強な受けが印象に残っている。
その後入門前に飛車落ちと二段のときだったか香落ちを私は指している。
勿論両方とも上手の楽負け。ただ下手の指し方として無理気味が感じられ、それを力で補うように思えた。
とにかく相手の間違いを誘う独特な雰囲気は天成のものであろうか。
いつも順当に勝つばかりでは高い率を残せないはずである。
1図はA八段とのもの。これが千日手になる。
(中略)
粘らせた方も悪いが、▲4九銀~▲5九銀の頑張りが目につく。後手方も▲3二竜のトン死筋が気になったのであろう。△3九角では△4五桂を利かし、それから△6八歩だろう。譜の順とてまだいくらでも勝ち筋がある。
これをしのいだのだから、次の指し直し局は勝てる確率が高い。
実際勝つには勝ったが内容が悪い。
2図から△8六角▲同金△7五銀に出ているが、以下▲8三歩△8四香▲7三歩成△8六銀▲7六玉△7五歩▲6七玉△7七銀成まで。
▲8三歩では▲2三銀にて先手勝ち。追いかけて7三桂を手順に取り▲8五桂打の筋になって7五銀が取れるから安全に勝てる。△7七銀成が見えていなかったのだろうか。
極言して必敗を2局続けて勝てたわけである。いやでも勝率が高くなるはず。
なぜ相手が間違えるのか、どうしたら間違えさせることができるのか、特別に終盤だけの逆転術があるわけない。
中盤での攻めたり受けたりのタイミングがよく、奔命に相手を疲れさせる。
相手は時間に追われるだけでなく、精神的疲労が重なりミスにつながるのである。
これは明らかに大山タイプだと言えよう。
攻防緩急の才
棋風について考えてみる。とかく攻めタイプと受けタイプに大別するが、どちらかと言えばのはなしで、よほど極端でない限り明確に分けられない。
受けの強さがあって攻めは生きるし、攻めの強さが受けをカバーする。両様兼ね備えて高手に達するのである。
羽生君はどちらかと言えば受けタイプだと思う。
つまり受けの場面で、より特性を発揮していると見る。
3図K九段との一戦、早指し戦なので深みはないが、名だたる秒読みの神様も攻防の綾を見られては最善を期し難い。
▲3九金△2八歩▲4八玉の推移は、あとで▲2七香の痛打を生んでいる。
終盤の▲5二銀(4図)ばかりが一般受けしているようだが、それに至る道程に注目したい。
5図も同棋戦での局面図、
△7三銀は辛い手に見えて、以下▲5四歩△8五飛▲5三歩成△同銀▲5四歩△4二銀▲3四歩△5五馬まで、テレビ放映の画面でもT名人の動揺ぶりはありありであった。
実は数手前、端攻めを逆用した△1五歩と△1六歩ののばしが、焦りをよんでいたに違いない。
その場になっての好手順は決して偶然ではなく、ある伏線をともなっているはずである。
手元の乏しい資料だけからでも、攻防緩急に抜群の才を感じとれる。
私自身の対戦経験から言って、その有名なハブにらみはとにかく、神経をゆさぶる将棋だと言える。
攻めて来るかと思って構えるとやってこない。ホッとしたところへどんと指し込む。それだけしまったの思いが強くなるわけだ。
弱点ありや
彼とて弱点がないわけじゃない。攻めなら攻め、受けなら受け、一方に偏ったとき敗局の危機がある。
対T八段(6図)は攻め過ぎ、結局2四銀が只取りの運命になり、あとの強襲も空しい。
7図、S七段との局面図▲9八桂は何たる手か、反発の余地なく敗れる。これは受け過ぎの一局。
まあしかし、めったにこんなことにならないから、それだけ高い勝率を保てるのである。
もう一つ注意してよいのは時間の使い方だ。
概して今の若い人達は時間の使い方が上手である。時間も勝負のうちだと認識している。
奨励会から時間制にもまれている。自然上手になって当たり前かもしれない。
そう言えば私の奨励会時代は時間制がなかった。故・山田道美九段は一日一局を標榜、私は何局も指したい、ついあせり負けした記憶がある。
秒読みで有名な加藤一二三九段も、やはり時間にたたられ敗苦をなめる場面が多い。
羽生君とて時間に追われれば最善を続けられない。持ち時間配分は相当に意識しているようである。
現在は勝ちまくって、それはそれで嬉しいことであろう。
気掛かりは対局過多になること、制度上の問題か本人次第か、現状は多分に本人任せである。従って自己管理能力が問われよう。
これだけ勝ってリーグ戦に登場できない。順位戦でも不運がある。どこか無駄足を使っていないか。
順位戦だけしか勝たなかった、いや勝てなかった筆者だから、ことさらそう思うのかもしれない。
ポイントの一局と言うものがある。将棋に見られる緩急を勝負の上でも示してもらいたい。
リーグにも強い男として一段の脱皮を望むものである。
* * * * *
「第一教えたから強くなれるものではない。たとえ少々強くなったところで師匠以上になれるはずがない。独自の自分なり工夫するものを持っている者が先達を乗り越えられる」
これは、教えられても教えられなくても、自分で解決しながら、自分の道を切り開いて強くならなければならないということ。もちろん、プロの世界の話。
* * * * *
「とにかく相手の間違いを誘う独特な雰囲気は天成のものであろうか」
羽生マジックの土壌は、子供の頃からできていたということになる。
もともとが想像を絶するほど強いのに、更にこのような雰囲気を発しているわけで、とにかく凄い。
* * * * *
「いつも順当に勝つばかりでは高い率を残せないはずである」
言われてみればなるほどと思えることだ。
* * * * *
「中盤での攻めたり受けたりのタイミングがよく、奔命に相手を疲れさせる。相手は時間に追われるだけでなく、精神的疲労が重なりミスにつながるのである。これは明らかに大山タイプだと言えよう」
棋風をはじめとして、羽生善治九段と大山康晴十五世名人はだいぶタイプが異なるが、大局的には、相手を疲れさせる将棋というところが共通点ということ。
二上達也九段の分析は、いつも鋭い。
* * * * *
「受けの強さがあって攻めは生きるし、攻めの強さが受けをカバーする。両様兼ね備えて高手に達するのである」
相手がどう攻めてくるか読めなければ受けは強くならないし、相手がどう受けるか読めなければ攻めは強くならない。
「攻めが強い」と「受けが強い」は同義ではないかと思っている。
* * * * *
「彼とて弱点がないわけじゃない。攻めなら攻め、受けなら受け、一方に偏ったとき敗局の危機がある」
この弱点を知ったからといっても、実戦的にはこの弱点をつくのはなかなか難しい。
そもそも、頻度が少なく、なおかつ羽生五段(当時)自身で解決できる問題なので、弱点とは呼べないことかもしれない。