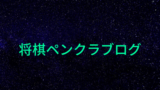将棋マガジン1994年3月号、高橋呉郎さんの「形のメモ帳 丸田祐三 小太刀も冴える職人気質」より。
将棋会館の大広間は、対局が多い日には6局が進行する。棋士が12人、記録係が6人、観戦記者が数人。20人以上の男が一室に会する。定刻10時。対局開始を告げる記録係の声が、あちこちから聞こえてくる。それを合図に、いっせいに駒音が響く。
ここまでは、むかしもいまも変わらないのだが、ここから先は、ずいぶん変わった。最近は、対局室が静かになった。盤上はのどかな時間でも、雑談する棋士がほとんどいない。サラリーマンが職場で朝礼を終えて、黙々と仕事をしているような雰囲気さえ漂っている。
むかしは―私が知っているかぎりでも、10年前は、もっとにぎやかだった。大広間が満席の日など、すくなくとも午前中は、談笑する声が一組か二組かはあった。合いの手を入れる棋士もいれば、席を立って話に加わる棋士もいる。話がはずんで、大爆笑が起こることもめずらしくなかった。
(中略)
あのころは、盤側に坐っているだけで退屈しなかった。対局者の顔ぶれから、きょうは、おもしろそうだぞ、という予感さえした。そう、芹沢博文九段も元気だった。
某日、米長邦雄名人が特別対局室で対局していた。大広間の笑い声が聞こえてくる。声の主が芹沢であるとわかると、米長が盤上に目を注いだままつぶやいた。
「また、あの先生か。声を聞くだけでも、香一本は弱くなる」
やがて、ハナ唄を歌っているような声が近づいてきて、芹沢が現れる。米長が「これは、これは」と丁重に出迎える。芹沢が腰を下ろして、掛け合い漫才でもはじまるかと思ったら、そうではなかった。ふたりで手帳を出して、会合の日取りを決めている。おたがいにいそがしい身で、対局のときでもなければ、ゆっくり打ち合わせをする時間がないらしい。ふたりのまじめくさったやりとりが、かえっておかしかった。
また某日、花村元司九段の対局で、巡回してきた芹沢が盤上を一瞥して、
「あっ、腰掛け銀ですか。(私のほうを向いて)まあ、見ててごらんなさい。花村先生の将棋は、すぐメチャクチャになりますから」
「メチャクチャとは、ひどいことをいうねえ」
そういいながらも、花村は楽しそうに笑った。ほかの対局者からも笑い声がもれると、芹沢は、左手で右手をたたいていった。
「私なんざあ、メチャクチャに指そうとしても、この腕が”イヤヨ、イヤヨ”といって、しぜんに筋へ筋へと行っちゃう。なんて、小生意気なやつなんだろ、この腕は……」
こうなれば、チャチャを入れる棋士もいるから、時間にすれば、ものの1分もないはずだが、私は余得に恵まれたような気分になった。
対局者同士のやりとりも、掛け合い漫才調あり、コンニャク問答調ありで、組み合わせによっては、相当に熾烈なものもあった。
田中寅彦八段が五段か六段のころだったと思う。相手は森雞二九段。私は、べつの将棋を観戦していたが、大広間の反対側から発する森の声が、いやおうなく耳にはいった。
「そんな手でやってくるの。じゃあ、こっちはこうだ」
「おっ、なかなかやるじゃない。危ない、危ない。用心しなきゃあ……」
「それじゃあ、カンキレ(完全な切れ筋)だよ。カンキレ……」
わざわざ見にいかなくても、将棋は田中のカンキレで終わったらしい、と察しがついた。感想戦も森の陽気な声ばかりが聞こえた。検討もすんで、田中がこちらの盤側にきた。肩を怒らせ、目は吊り上がっている。腰を下ろすと、だれにいうともなくいった。
「弱い!なんて弱いんだ」
手玉に取られた負けた悔しさを、本気で自分に怒っていた。そのころ、私は田中と言葉を交わしたこともなかったが、この男は根性があると思った。
私が観戦した回数は高が知れている。最初の数年間は年に5、6局で、いまでも10局前後にしかすぎない。観戦記者としての年季も、大先達諸兄にくらべれば、新参者の部類に属する。だから、あまり口幅ったいことをいうつもりはないけれど、対局室の雰囲気が変わったことは否定すべくもないように思う。
もっとも近いところでは、昨年の11月、大広間が満席の日に観戦した。私の担当は南芳一九段対佐藤康光七段(現竜王)の一戦。寡黙で知られる南は、昼食休憩前に手番が回り、ささやくような声で記録係に「休憩にしてください」といったきり、ついに終局まで口を開かなかった。佐藤は質問されれば、ふつうに答えるけれど、対局中に自分からしゃべるようなタイプではない。記録係に持ち時間の残りを告げられて、「ハイ」と答えた以外は、こちらも無言で通した。
隣では現役最年長の丸田祐三九段が、石川陽生五段と対戦していた。かつて、同じように隣の丸田対花村戦を見たことがある。気心知れた同士で、掛け合い漫才よろしく、丸田がツッコミ役、花村がボケ役を演じていた。
早指しで有名な花村の指し手が止まると、すかさず丸田が「おどろいたねえ、よく考えるじゃない」とかいってツッコむ。やがて、終盤にさしかかったあたりで、「なんだ、受けるの?ハナちゃんが、こんなところで受けるかねえ。その年になって、棋風が変わったんじゃないの」
1993年の某日は、こんなふうにいかなかった。相手は40歳以上も若いから、話しかけるには勝手がちがいすぎる。ほかの4局は中年と準中年がひとりずつで、いずれも若手と対戦している。そちらも、やはり勝手がちがうらしく、雑談をする気配はなかった。午前中から、大広間は静まり返っていた。丸田は、なんとなく手持ちぶさたのようにみえた。
丸田・石川戦は夕刻に持将棋が成立した。丸田の半分はテレかくしのボヤキが聞こえた。
「駒数が足りているのに、まさか”負けました”ともいえないしねえ」
現役最年長の大ベテランが、若手棋士相手に持将棋を指したというのは、敢闘賞ものだろう。あいにく、私が観戦している将棋を残して、ほかの4局は終わっていたので、大広間には人気がない。盤側に駆けつけ、老雄の労をねぎらい、ついでに、衰えぬ体力に冗談の一言もいう棋士がひとりもいなかった。
このへんも、10年前とは変わったような気がする。当時は、持ち時間が全般に現在より長かったせいもあって、明るいうちに終わる将棋がすくなかった。夕刻ないしは夜にはいって終局すると、大方の棋士が控え室に残って、まだ進行中の将棋を検討する。また、対局がなくても、なんとなく連盟に立ち寄って、そのまま控え室に腰をすえる棋士もいた。
やがて終局の報がとどくと、そういう棋士たちが検討に加わる。だから、対局室が閑散としていても、いったい、どこにいたのかと思えるほどの人数が集まった。
丸田も、そんな棋士のひとりだった。連盟の理事をつとめていたので、対局とは関係なく将棋会館にくる。理事の仕事が終わっても、すぐには帰らず、対局室を一巡するのが修正になっていたらしい。感想戦になって、日中はいなかった丸田の顔をよく見かけた。
(以下略)
* * * * *
東京・将棋会館の4階。入口から向かって右側の一番奥に特別対局室があり、その手前に高雄、棋峰、雲鶴の3つの部屋がある。高雄、棋峰、雲鶴の3部屋の襖を開けた状態にすると大広間になる。
* * * * *
昔の職場も、業種や社風によっては、雑談を含め今よりも会話が多かったと思う。
1990年代後半からの電子メールの浸透があったとはいえ、業務時間中の軽い雑談が激減したのは、対局室も職場も同じような傾向となるのだろう。
* * * * *
対局室での雑談が減ったのは、世の中の流れということもあるが、序盤から神経を使う将棋の時代に変わったからという大きな理由もある。
* * * * *
昔は、面白い会話や可笑しい会話だけれども、対局の流れとは関係なくて、観戦記に載せたくても載せることができなかったものも多かったことだろう。
* * * * *
はるか昔には、このような対局室の風景もあった。
1990年代でも、石田和雄九段が登場すると、このようなこともあった。
1990年代の関西は、昔の雰囲気が濃厚だった。