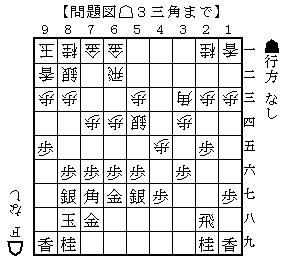将棋世界1988年9月号、故・福本和生さんの「検証・素顔の棋士達 大山康晴十五世名人」より。
現在の東京・将棋会館は昭和51年に完成した。地下1階、地上5階のビルの骨組みが出来あがったころ、大山康晴会長の案内で内部を見学させてもらった。
階段を昇って4階の特別対局室を見ていると、大山が「ベランダの塀、どうだろうか」と問いかけてきた。ベランダにそって15メートルほどの塀があって、大山はこの塀が高すぎないかというのだ。外界をさえぎるほどの高さである。
対局中、とくに午前中の対局では、外の景色が目に映ったほうが気持ちが落ち着くだろう。
「(塀の高さを)半分ほど削ってもらいましょう」
コンクリートの塀はほぼ完成して、すでに仕上げの段階であったが、大山の即決で数日後には半分の高さに削られた。
特別対局室のガラス戸を通して、済んだ青空や新宿の高層ビル群の景観を見ると、塀を削らせたのが”正着”であり、それを工事中のビルを歩きながら一目で見抜いたのは大山の活眼である。
***
麻雀にまつわる話を思いだすままに二つ三つ…。
部屋の照明がよくなかった。麻雀牌が暗くて見えにくい。大山はそばの計算用の白い紙を折って、並べた牌の手前に置く。光が紙に反射して牌が見やすくなる。長時間の麻雀になると、このちょっとした工夫で目の疲れがかなり違ってくる。
大山は麻雀でなく、盤上を見る目をいたわっていたのだろう。
川端康成著「名人」にこんな一節がある。
「麻雀の時、名人は懐紙を細長く折って、その上に牌を並べていた。紙の折り方も、牌の並べ方も。きちんとていねいなので、私は名人の潔癖かと思ってたずねてみると、『へえ、ああやって、白い紙の上に並べると、明るくて、牌が見やすいんです。ためしにやってごらんなさい』と、名人は言った」
文中の名人は、囲碁の本因坊秀哉名人である。引退碁に命を削っていた秀哉名人も、視神経の疲れをいたわっていたのかもしれない。
大山家で麻雀をやっているとき、電話がかかってきて大山が受話器をとった。
「病気はガンの疑いがあるらしい。入院して手術を受けます。あとはお医者さんまかせです。あわててどうこうなるものではないですからね」
そばで聞いていて、こっちがドキッとした。淡々とした口調で、第三者のことを話しているようだった。すごいひとだと思った。
千葉の銚子で棋聖戦があったとき、麻雀開始となった。ひどい麻雀卓で、みんながぶつぶつ言ってると、大山は押し入れから敷布を取り出し、さっさと麻雀卓の修復にかかった。台の外枠をはずして、白い敷布をきちんとかけて、周囲がその鮮やかな手ぎわに見とれているうちに、きれいな麻雀卓が完成した。
フロントに電話して卓を取り替えてもらえば簡単なのだが、大山流は自分ができることはさっさとやってしまう。
それと麻雀が終わったあと、大山は使った牌を箱に入れ、点棒、サイコロも元どおりに納めて、そのケースを卓上に置いて終了となる。疲れていると牌も点棒も放置したままでの引きあげとなりがちだが、大山流はそれをゆるさない。マナーのよさであるが、それよりも根が几帳面なひとなのだ。
「小学校にはいる前後のある日、大山は、父の自転車の荷物台に乗せられて、数町離れた平井長之丞二段という土地で有名な棋客の自宅へ連れて行かれた。平井さんは、大山の父の同業の花筵商でもあった。
その日から、大山は平井二段に将棋を教わることになった。
最初の日は二枚落ち。7歳の大山は完敗し、泣きたくなった。
すると、平井さんが言った。
『この子は将来大物になる器ですよ』
しかし、平井二段は、幼い大山に棋才の閃きを認めたと言うより、大山が行儀よく高さが自分の首くらいまである盤に向かう態度、最初に駒を並べる時にも、また対局中の駒の取り替えっこの際にも、枡目の真中に一分一厘狂いのないように駒をきちんと置く子供の律儀さと丁寧さが深く気に入った様子だった。この子は地道な努力型で、根気よく教え込めば、あるいは物になるかも知れない、と思ったのかもしれない」(藤沢恒夫著「小説棋士銘々伝」から)
将棋の強い少年は、お父さんの自転車の荷物台にちょこんと乗せられて、学校の授業が終わると平井家に日参した。
平井先生は、どんな教え方をしていたのか。藤沢先生の著書からさらに引用させていただく。
「平井先生の教え方はこうだった。木村義雄八段の名著『将棋大観』を教本として、六枚落ちから教えるのだが、その日教える部分を、先ず先生が少しずつ読んで聴かせる。そして、大山に復誦させる。昔の寺小屋の先生が、子供たちに、『孝経』や『大学』の素読を教えるやり方に似ている。
口述の反復がすむと、それから盤に駒を並べる。そして、その日口述した部分の攻防や、定跡の変化を、大山が憶え込むまでやらせる。大山は憶えは速い方だったので、殆ど間違わずに反復出来た。
翌日は昨日習った分をおさらいしてから、次の定跡に進む。(中略)
そして、幼年期からの毎日のこのような修行が、大山が小学校を卒業する直前まで、実に6年間もつづけられたのである」
見事な英才教育である。
大山将棋の基礎の骨格は、この6年間に形成された。そして血肉となったのは、内弟子に入った木見門下での錬磨である。
***
新聞の健康面の取材で、大山に健康法を聞いた。10年ほど前の話である。
「そうね、食べることかな」と大山。
食事をしているところを写真に撮ることになった。場所は将棋会館地下の食堂である。
カメラマンの注文で、ごはんを山盛りにした器がテーブルに出された。大山は対局中で、その昼食休憩を利用しての取材だった。ハシをつけてもらって、食べる形だけでいいと、カメラマンもわたしも思っていた。
ところが大山は、そのどんぶり2杯分はたっぷりあるごはんを食べてしまった。
取材のあとでカメラマンが驚いていた。
列車の旅で駅弁を買った。ごはんとおかずが別になっている駅弁である。わたしが膝の上におかず、手にごはんを持って食べていると、前の席にすわっていた大山が「それでは食べにくいでしょう」と言う。
二つの入れ物を少しずらして重ねる。おかずを上にして、下のごはんを食べ、食べた分だけ容器をずらしていけばスムーズに食べられる。
その方法で大山はあっという間に駅弁をたいらげた。わたしは手品を見ているような気がした。
冬の棋聖戦が熱海の見晴館で行われた。対局のあと打ち上げの小宴があって、いつものように麻雀となった。深夜、「おなかがすいたね」と大山。フロントに電話したが応答なし。「おじやを作りましょう」。
大山はごはんを鍋に移し、調味料をいれて、おじやを作った。みんなで食べたが、味の濃いおじやは、なかなか美味だった。
***
”大山語録”には、勝負の場で鍛え抜かれた人生観がこめられている。
「私は何事にせよ、勝ち負けのはっきりするものが好きだ。性分であろう。ただ、そのせいか、物事を白黒にわけ、単純に考えてしまって困ることもある。
私の場合は、名誉も地位も財産も、すべてが将棋の勝敗にかかっている。少年の日からコツコツと研究に研究を重ね、やっと到達したのが現在の私の姿である。
私は色紙によく『己勝』と書く。何事も、まず自分に勝たなければ成功しない。何かを身につけて世に出ようと思うなら、まず己に勝つことだ。少年時代、恩師木見金治郎先生に教わったのは、このことであった」(大山著「大山将棋勝局集」から)
「勝率が落ちた場合、私は一日も早く悪い状態から抜け出すように努力する。周囲から『スランプじゃないか』と注意されて初めて気がつくようでは、もう手遅れだ。私は他人から注意されないうちに、平素から自分のペースをきめておき、自分の調子が落ちていないか、どうかと気を配っている。スランプは避けがたい病根だが、要は苦しくとも耐えしのぶことだ。じっと耐えてチャンスを待てば、道は自ら開ける」(同)
「わが家の宝物のなかに二枚の陶板があります。一枚は『助からないと思っても助かっている』 もう一枚は『一灯破闇』という文字が書いてあります。
二枚とも、倉敷レイヨンの社長の故・大原総一郎氏が私のために書いてくださったもので、故・河井寛次郎氏作のものです。いただいたのは30年も前のことですが、今でも教訓としています。(中略)
終盤になって形勢が悪く、つい弱気になってあきらめようかと思ったとき、この陶板の文句を思い出します。『助からない』という弱気を吹きとばして『助かっている』という気持ちで盤上を見直します。不思議なもので苦戦のなかから『一灯闇を破る』手が浮かんできます」(「大山、中原激闘123番」から)
(以下略)
——–
「助からないと思っても助かっている」が、倉敷レイヨン(現在のクラレ)の社長の故・大原総一郎氏によるものだったと初めて知る。
大原総一郎氏(1909-1968)は、大原財閥を築いた大原孫三郎氏の長男として生まれている。
大原総一郎氏の経営者としての業績は数々あるが、その中でも特筆されているのが、戦後まもなくの「ビニロン」の開発・工業化と、国交のなかった中国へのビニロンプラント輸出。
「ビニロン」は世界初の画期的な新繊維だったが、工業化・生産のためには多くの資金を要した。
しかし、当時は銀行の貸出が抑制されていて、どの銀行を渋い返事ばかり。
国民生活の復興に寄与することと国産合成繊維の工業化という強い使命感のもと、大原総一郎社長は「法皇」と呼ばれていた実力者・日銀の一万田尚登総裁に掛け合い、資本金の6倍である14億円の協調融資を得ることに成功する。
大原総一郎氏にとっての「助からないと思っても助かっている」は、まさにこの時だったのかもしれない。
中国へのビニロンプラント輸出の際も、様々な困難に見舞われ、結果として「助からないと思っても助かっている」という展開になったが、これは大山康晴十五世名人に二枚の陶板を贈った後のこと。
大原総一郎氏は故・松下幸之助氏から「迫力を持つ美しい経済人」と称されている。
[amazonjs asin=”4122032431″ locale=”JP” title=”大原総一郎―へこたれない理想主義者 (中公文庫)”]