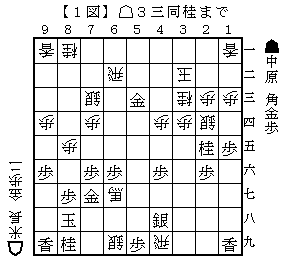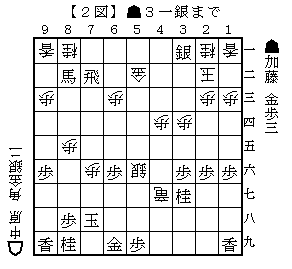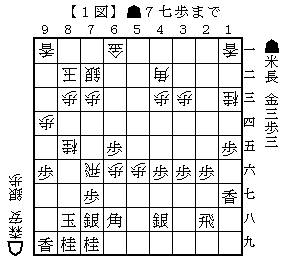将棋世界1982年12月号、毎日新聞の加古明光さんの「異次元の間で」より。
「本職はどちらで?」と問われることがある。正直なところ、こう尋ねられると、困ってしまう。やむを得ず「新聞記者だから多国籍なんですよ」と答えるしかない。
新聞社の学芸部で将棋と音楽が私の担当だ。音楽は、おカタイ、カラヤンやモーッアルトでなく、歌謡曲からロック、ジャズまでのいわゆるポピュラー分野。だから、聖子チャンや伊代チャンを聴いた翌日、将棋会館の盤側で観戦記取材にと、しかつめらしく座っていることもある。
かつては村田英雄の「王将」ぐらいしか接点のなかった将棋と音楽。内藤國雄王位の「おゆき」からやや両者の付き合いは深まったが、異次元の世界であることには変わりがない。
大体、歌の世界は夜でも「オハヨウゴザイマス」に「よろしくお願いしまあす」だ。だが将棋界で「よろしく」なんて言う棋士は一人もいない。盤側にいると、食いつかれかねない雰囲気がある。
キャリアでは音楽の方がちと長い。それなのに某レコード会社社長などは「観戦記は読ませてもらってるけど、音楽の記事も書いてるの」なんてトボけたことを言う。異次元の世界にはさまれた私は、ここでウツになる。ウツになるから酒を飲む……(何を言ってるんだ、こりゃ……)
もとい―。真面目な話、この両分野は結構忙しい。とくに将棋の方がしんどい。観戦するだけで一日どころか深夜の間で及ぶ。今でこそ幾分慣れてきたものの、ヒザがガクガクしてくる。おまけに対局室は酒気帯び厳禁。大変な世界に来たもんだ、というのは偽らざる実感だった。
だが、水になじむにつれ、この世界も面白くなってきた。第一、気分的にチャンネルの切り替えが出来る。この切り替えは教育テレビと民放のアチャラカ番組ぐらい違う世界を見せてくれる。歌の世界では、垣間見ることすら出来ない赤裸々な勝負の瞬間がある。
一匹狼の集団、強烈な個性の集合体としてけったいな世界ではあるが、そのためにかえって強い印象を与えてくれるところだ。このインパクトの度合いは、誰それがレコード大賞をとった瞬間など比較にならない。
タイトル戦について各地を転戦する。対局者に比べれば気楽だ。設営、観戦、送稿の三つ。ヘボはヘボなりに将棋を楽しんでおればいい。だが、プロの盤面では「ドキッ」とさせられることが多い。それもなぜか「銀」。
1979年の4月27日。所は愛知県西浦温泉「銀波荘」。舞台は第37期名人戦七番勝負の第4局。
この年はリーグ戦も大荒れで二上、大山、米長、森が四者同率になり、パラマス方式で米長が挑戦権をつかんだ。
米長は走った。1、2局に連勝、3局目は敗れたものの米長のリードで第4局を迎えた。ここで中原名人が負けるとカド番になる。難解な矢倉のまま、二日目の夕方、寄せ合いに入った。1図が△3三同桂までの局面。
控え室では板谷四郎、進父子が検討していた。進八段のダイナミックな解説に、四郎大先生が静かに応える。親子でも全く対照的。
進八段が言う「名人の方が苦しいんじゃないの。▲5四角でも△3一玉で、ヨネさんの方からは、いつでも△4八飛成がある。これはきびしいよ」。プロの高段者が評するのだから間違いはない。
夕食休憩直前、天井のライトをまぶしそうに見やった中原が、ひょいと▲5七銀と上がった。わずか2分くらいだったと思う。「タダじゃないか」と叫ぶわけにはいかない。この一手を持って控え室に走った。▲5七銀―この時のどよめきを忘れることは出来ない。「ヘェー」という声。「フーン」と感嘆と疑問のまじった声が賞賛に変わった。
米長は△5七同馬とせざるを得ない。△5九飛成では▲6七金がある。それにしても、この感覚をどう評したらいいだろう。馬筋をかわすためのタダ捨ての銀。進八段が「こりゃ、史上に残る妙手だ」とうなり、この銀一枚が、にわかに光彩を放ってきた。
米長は30分以上を投入してこの対策に苦しんだ。しかし、▲5七銀を境に、流れは中原に向き始めた。△5七同馬▲5四角△3一玉▲3三桂成△同銀▲6二銀△4八飛成▲5八桂と進み、結局、中原がタイに持ち込んだ。▲5七銀はシリーズの流れすら変えた。中原の防衛につながったのである。
プロはプロを知る―投了後、米長がすぐに「▲5七銀はいい手だったね」と認めた。悔しそうな顔ではなかった。この光景を見ていて、プロの恐ろしさに戦慄すら感じた。「よろしくお願いしまあす」どころではないプロフェッショナル感覚。ジス・イズ・ザ・プロである。
3年後、今度はその「銀」が中原から名人の座を奪うとは―。いうまでもなく、第40期名人戦の最終局、105手目の▲3一銀(2図)である。
この数手前、加藤が「ヒャー」と奇声を上げたと私は記事にした。そして「▲3一銀の詰みを発見した喜びだ」と……。しかし、これは送稿時間に追われたヘボ記者の読み違いだったらしい。
「ヒャー」そして「ウムウム」は、その数手前、▲5二角成からの変化手順を発見した時で、▲3一銀は瞬時に浮かんだという。だが▲3一銀だって名手である。直感で指しそうな▲5二飛成では詰まないのだから。
▲3一銀とされた瞬間、中原は投了した。文字通りのノータイムだった。名人の座にこだわるなら、しばし考えてからの投了だろうにこのノータイムの意味は何だったのだろう。
ドラマは敗者の方にある。▲5七銀とされた時の米長の光った目、▲3一銀の中原の白い顔がまだ脳裏から離れない。それにしても―異次元の世界だなァ、ここは。
—————
毎日新聞の故・加古明光さんは、将棋と音楽を30年間担当、日本レコード大賞審査員も務め、酒を飲みだすと水割りオンリーで、棋士からは愛されて”水割りおじさん”と呼ばれていた。
—————
現在ではだいぶ変わってきたが、この頃の「将棋」のイメージは、暗くて地味。
音楽・芸能界とは180度違うイメージの世界だった。
普通なら、将棋は必要最低限にとどめて、音楽・芸能界の取材を優先的に進めたくなるところだが、「水になじむにつれ、この世界も面白くなってきた。第一、気分的にチャンネルの切り替えが出来る。この切り替えは教育テレビと民放のアチャラカ番組ぐらい違う世界を見せてくれる。歌の世界では、垣間見ることすら出来ない赤裸々な勝負の瞬間がある」と加古さんが書かれている通り、それまで畑違いだった加古さんが将棋や棋士に魅了されたことが分かる。
—————
「暗くて地味」のイメージの奥には、今と変わらない将棋と棋士の魅力が存在している世界だった。
「暗くて地味」のイメージが半分ほど取り払われたのが、1996年前後の羽生善治七冠フィーバーによるもの。
そして、今回の藤井聡太四段の活躍により、そのイメージは完全に取り払われたと言っても良いだろう。
そういった意味でも、今年は1996年と並ぶ、将棋史的に歴史的な年と断言できそうだ。
—————
升田幸三実力制第四代名人の1971年名人戦第3局の△3五銀、羽生善治三冠の1988年NHK杯戦の▲5二銀など、有名な絶妙手は銀によるものであることが多い。
理由があるのか、あるいはたまたま偶然なのか、あるいは集計してみると他の駒の方が多いのか、時間がある時にいつか考えてみたいと思っている。