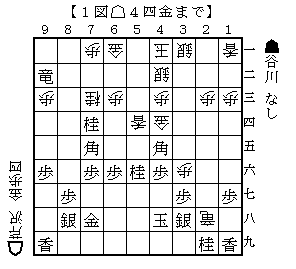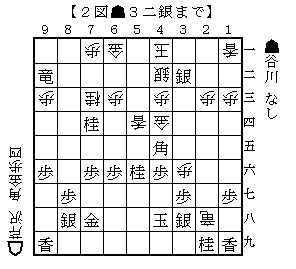将棋世界1988年3月号、福本和生さんの「検証・素顔の棋士達 故・芹沢博文九段の巻」より。
「少年は夢を見ていた。”鶴”の舞う夢を見ていた。幼き頃、少年は鶴になりたいと思っていた。少年はそのあと盲目になった。鶴の姿だけが脳裡に残った。鮮明に残った。
少年は必死に鶴になりたいと思った。美しく気位高く舞う鶴になりたいと思った。
少年は夢から醒める。鶴になれない己を知る。だが何とかと何回か思う。思っては行い、挫折して三十年、少年は只の老人になった。しかし、不思議なことに老人は今だに鶴になりたいと思っている。心に燻り続けているのである。もし鶴になれたら、腕一本と言わず、一年もし鶴を許してくれるなら命もいらぬと鶴を希っているのである。老人は思う、いつ鶴になり損ったのかと」
芹沢博文九段が雑誌に連載していた「歩がいのち」と題するエッセーの文章である。
去年の十月、女流棋戦の解説で芹沢家を訪れた。仕事が終わって、ふたりで一杯やっているうちに、芹沢さんが手もとのスクラップを開いて、低い声で読みだした。
「歩がいのち」の中の”鶴になる夢”であった。
「もし鶴になれたら…」うめくような声で、涙ぐんでいるようだった。
鶴は名人位である。
芹沢さんとの出会いは、昭和四十四年の第十五期棋聖戦であった。中原棋聖に内藤八段が挑戦したときで、第二局が十二月二十七日に「銀波荘」で行われた。芹沢さんは総務担当ということで来ていたが、新聞原稿の解説役を一手に引き受けていた。この解説が見事であったが、わたしが強く印象に残っているのは終局間近の光景である。
間もなく投了となると、芹沢さんは控室の継ぎ盤にさっと局面を並べて、白紙に”さわるな”と書いて、それを盤の上に置く。終局と同時に何手かの追加手順を並べて投了図が完成する。鮮やかな手ぎわに感服した。
「大阪の新しい将棋担当と聞いて、えらく若いひとなので、将棋指しとつきあえるのかと心配だった。ところが私より年上なんでびっくりした」
後年、初対面の話をするたびに、芹沢さんはこう言ってわたしを冷やかしていた。それから長いおつきあいが始まった。
芹沢さんの五十一年の人生は、その著書にくわしく書かれている。少年時代は「ぼくんちは萌黄色」に、プロ棋士を目指しての内弟子のころから九段までは「破天荒盤外記」などに語られている。芹沢流とでもいえる”男の美学”を貫いた人生で、言いたいことを言い、やりたいことをやって、うじうじと暮らしているわたしの目からはうらやましいかぎりであった。芹沢さんの急逝が報ぜられたとき、マスコミは”生きいそぎ”というコトバでその死を惜しんだ。そんなに忙しくしなくてもよかったのに、自分で自分を追いたてながら、弱った体をムチ打って仕事にたち向かっていた。つらかったと思う。
「ホトホト厭になった。厭になっても将棋にくっついていなければテレビ、ラジオ、講演、随筆等の依頼がなくなるのは判っている。将棋に感謝している。将棋は好きだが将棋指しは数人しか好きな者はいない。将棋指しの心が余りにも私から見て腐っているからである(後略)」
将棋ペンクラブの会報に載っている芹沢さんの文章である。
ホトホト厭になりなから将棋にくっついて生きねばならないことのジレンマ、神経はくたくたに疲れきっていただろう。
生死の境をさまよう大手術のあと、頭を丸めて三年間の”休酒宣言”をした。そして一年間、一滴の酒も日にしなかった。こんど飲んだら命取りになることはわかっていた。ケーキを食べ、安倍川餅をほおばりの豹変ですっかり元気になった。三年間の休酒が守られていたら、それは五年間の休酒へと続いて健康になると周囲は喜んでいた。
ところが、この壮挙も一年間で幕をおろし”休酒あけパーティー”が、日比谷の松本楼で開催となってしまった。にぎやかなことの好きな芹沢さんらしく、このパーティーには各界の方が顔をみせて盛大なお祝い?の会となった。自重してのワインであったが、やがては愛飲の日本酒”八海山”となり、量も次第にふえていった。
十年、いやもっと前になるか。棋聖戦の本戦で芹沢―内藤戦という珍しい顔合わせがあった。対局場は大阪の古色蒼然たる旧将棋連盟で、芹沢さんとわたしは東京駅から新幹線に乗った。グリーン車にちょっと腰をおろして、食堂車があくのを待ちかねて一番乗り。ウィスキーのストレート。そのまま新大阪駅まで動かずに飲み続け、ホテルに入ると荷物を部屋に放りこんでバーへ直行。そこでもウィスキーのストレート。芹沢さんは悠然たるものであるが、こっちは六時間ぐらい飲み通しで参ってしまった。翌日、わたしは宿酔でふらふらだったが、芹沢さんはしゃんとしていて、対内藤戦を勝った。
”鶴”を夢見ていた少年が”盲目”になったのはいつだったのかー。
芹沢さんが「名人位」への挫折感をもったのは、仲間内でもさまざまな論がある。”神武以来の天才”加藤一二三九段の鮮やかな天才ぶり、有名な中原さんとのA級入りを賭けた一番、いろんな説があるが真相はわからない。何かのきっかけで芹沢さんは”鶴”になる夢を断念した。六段当時、勝とうと思った将棋は簡単に勝てた、と豪語するほどの才能の持ち主が、である。
その気になればタイトルの一つや二つは取っているはずなのに終生無冠のまま。わたしは、芹沢さんは将棋だけでなく他の分野でも才能があって、その才にのめりこんでいったことが”将棋の芹沢”にとっては不幸だったと思っている。
「中原は名人になった。立派なことだ。しかし、人生の幸福という点では、ひょっとしたら中原は私をうらやんでいるかもしれない」
酔ったうえでの自嘲まじりのコトバであったが、いかにもさみしそうであった。
中原が大山名人に初挑戦したとき、”名人候補”であった芹沢さんの胸中は揺れていた。
「名人位を強烈に恋い焦れている私にはショックであった。中原ガンバレ、名人を取れの気持より、名人位を中原が取ったら二階級どころでなく、途轍もなく差が付くと思い、中原が負ければいいと云う、何とも恥かしい妬み心が日に日に膨れる。己が心を卑しいと思いつつも、どうしたらいいか判らず、酒、博打と荒んだ生活に拍車がかかった」(「歩がいのち」から)
このとき、芹沢さんは三十七歳の男盛りであり、将棋も指し盛りであった。少年時代から自分が鍛えた”弟”が、いつの間にか自分を追い抜いて、わが悲願である”鶴”になって大きく飛翔しようとしている。”荒んだ生活”が自分を傷つけることはわかっていても、そうしなければ荒れる魂を鎮めることができない。命がけの遊びであった。
二十年前、将棋界はまだそれほど社会的な評価を受けていなかった。新聞観戦記に棋士の名前が出ていると、その棋士の奥さんに隣家の主婦が、お金をいくら払っているのかと聞いたそうだ。将棋を指してお金をもらっているということがわからないひとがいた。そんな将棋界の地位を押し上げ、棋士という職業の魅力を広くPRするのに功績のあった一人に、芹沢さんの名前をあげるのにだれも反対しないだろう。卓抜した企画力で世間をあっといわせる大PR作戦を展開して将棋界を強く印象づけた。
「将棋連盟は滅んでも将棋は残る」
将棋の話をするとき、芹沢さんは語気を強めて、現制度の悪平等を批判していた。ぬるま湯にひたっている、そのために勝負師としての峻烈さを見失っている、それは文化である将棋に対しての冒涜である。
このことを書き、しゃべり、遂には”全敗宣言”という思い切った行動にまででた。そこまでしなくてもと、わたしなどは思っていたが、芹沢さんはとどまらずに突っ走った。将棋が好きで、将棋に深い愛着をもっていただけに、全敗宣言は芹沢さんにとってきりきりと胸を刺されるの思いだったろう。
当然のように芹沢発言について反発があり批判の声が高まった。いろんな話を聞いているが、当事者がいるので今はペンを抑えておく。
芹沢さんは引退を考えていた。健康のためには、わたしも引退に賛成である。現役で戦っていて、黒星を重ねるたびに自分を責めていては神経がすたすたになってしまう。
去年十二月、中原さんと会ったとき、芹沢さんの引退のことについて話をした。
「相談したいことがあるという連絡がありましたから、そのことかもしれません」と中原さん。理想をいえば、今年の順位戦を全勝で飾って、そこで引退というのが芹沢さんらしくかっこよくていいのだが、残念ながら芹沢さんの体は弱り切っていた。最強といわれるB級2組で白星を重ねることは無理だった。あることで芹沢さんに電話して、そのとき引退の決意を聞いたら「考えています」との返事であった。
「未練というのであろうか、老人は今も夢を見る。鶴、名人になった夢をみる。見えない目で夢を見続けているとは、何と業深きものか。そう思う理性は幾らかはあるが、夢で鶴を追い求めているとは、何ともはやである」(「歩がいのち」から)
去年十一月三十日、芹沢さんは滝六段を同道して拙宅にみえた。いつもなら、二、三時間わいわいしゃべって帰っていくが、この日は五時間ぐらいいた。お酒を飲みながらいろんな話をしたが、そのなかで昨年夏に亡くなったわたしの母のことが話題となり、芹沢さんは真剣な口調でこう言っていた。
「おふくろというのは、離れていて会えなくても、元気で居るというだけで子供としてはうれしいもんです。ふっと恋しくなれば、飛んで行けば会えるんですからね。それが、いなくなるというのはさみしい。たとえ病気で寝てても居るだけでいいんだ。しかし、福本さんは親孝行をしたよ。親の彼岸への旅立ちを見送ったんだから…。子供として最大の不孝は、親を残して死ぬことだよ。これだけはしてはならない」
しんみりとした話に滝さんもわたしも、酒杯を、下に置いて無言でうなずいていた。
してはならない、とあれほど強く言い切っていたことを芹沢さんはやってしまった。
残念であり無念だったと思う。
「正明は母に向かってきっぱりといった。
『母ちゃん、おいらは将棋をやめない。授業中、将棋の本を読んでいたのはおいらが悪かった。でも将棋は悪くない。だから将棋はやめない』
『将棋は悪くなくたって、それをやっているうちにだんだん怠け者になっていくんだよ。将棋なんか始めたら人間、額に汗して働くってことを忘れちまうのさ。お前は小学生だろう。今の仕事といったら一生懸命、勉強することじゃないか』
母も負けていない。お互いに強い調子でいいあいが続いたが、どちらも折れようとはしないから、いつまでたっても結着がつかなかった」(芹沢博文著「ぼくんちは萌黄色」から)
正明は少年時代の芹沢さんである。
これはお通夜の席で聞いた話だが、芹沢さんは亡くなる直前に沼津の実家を訪れている。
「東京と沼津、車を飛ばせば一時間半で行く。だが年に二、三度しか会えない。法事とか静岡県内の仕事のときとか、そんな折りだけだ。会うと時間にかまわず酒になる。たわいないことを言ってはゲラゲラ笑い、お袋に少しバカにされ、それをまたおかしいといって笑い、そんな光景を兄貴が少し妬いているような表情で見ているのをからかって怒らす。そしてまた笑い飲む。ただじゃれ合っているみたいな酒である」(「破天荒盤外記」から)
お父さんの話では、このたびの芹沢さんはほとんど酒を飲まなかったそうだ。
「お袋の暖かい心が腹に入っていくようで、たとえようもないほどうまい」と書いている鰯の醤油干しは口にしただろうか。
十一月三十日の午後九時ごろ、芹沢さんはわが家から去っていった。玄関で軽く手を上げて、そのまま帰っていった。元気な芹沢さんを見たのは、これが最後であった。
「運良く谷川との一局が来た。谷川十九歳、七段と時、順位戦の良き時に来た。心を込めて戦ってみようと体調を整えて臨んだ。
1図はその終盤である。中盤谷川に一失あり、その差がジリジリと開いてもう勝ちである。そう思い、ヒョイと谷川の顔を見ると朝十時の時と”同じ顔”をしている。
如何に勝負の修羅場を潜りし者でも、勝ちを思えば緩んではいけぬと、気を引締め、負けを思えば、その口惜しさを顔に出さぬようになる。何れにしても表情は変わる。それなのに十九才のガキが、何事もないように”スッ”としているのである。アレ、俺は何か見損ったのか、精神に混乱が来たのを今でも鮮明に憶えている。
終局まで、この子は何故表情が変らぬのか気味悪く思っていた。未だに何故だか、シカとは判らぬ。”境界値”であろうか。
局面は1図から▲4二角成△同銀▲3二銀(2図)と動いて△5一玉と逃げ、普通に筆者の勝ちで終った。
2図で△3二同玉とすると▲4四桂△同歩▲5四角△4三銀打▲3五香で逆転である。
こんな易いの、瞬時にして判る、谷川も判っている。だが、こう攻めて来るのが作法である。勝つに作法あり、負けるに作法ある。
谷川は作法通り負けに来たのである。表情も変えずに作法通り負けに来るなんてこと、子供に出来ることではないと思っていたが、谷川はいと易く行うようである。
2図以下、△5一玉▲2三角成△3九角▲5九玉△2三竜▲同銀成△5六香▲6九玉△5七角成▲6八金△5九角までである。
子供の頃より名人になるだけを思いとして将棋指しになったが、思い上って夢は破れた。思い上ったとは言え、名人になれぬことを残念で、将棋指しなんぞにならなければよかったと思ったこともある。だが、谷川と同じ時代に生き、一局でも指せただけで将棋指しになって良かったと痛切に思う」(「歩がいのち」の”天才の顔”から)
* * * * *
芹沢博文九段の名人に対する思いに胸が締め付けられる。
生き急いだとともに、死に急いだような感じがする。
「歩がいのち」は小説新潮に掲載されていた。
* * * * *