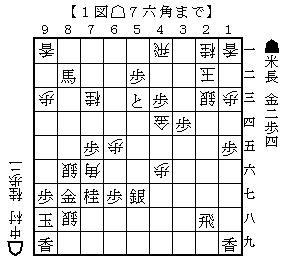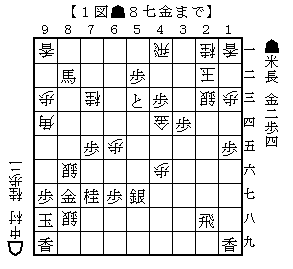将棋マガジン1985年3月号、川口篤さん(河口俊彦六段・当時)の「対局日誌」より。
59年も、もう終わりである。だれでも言うことだが、年を取るにしたがって月日のたつのが早く感じられる。
さて、そのアッという間にすぎ去った59年を振り返ってみれば、大きな動きのなかった一年と言えるだろう。名人位は交代しなかったし、米長の三冠王も前から予想されていたことであった。
そんななかで、わずかに目立ったのは、中村の棋聖位挑戦であった。もっとも、棋聖位を奪ってこそ事件であって、単に挑戦したに終われば、どおってことはないのだけれど。
それはともかく、中村の特異な棋風は、将棋ファンの目に新鮮なものとうつっただろう。たとえば第1局の投了の場面など今までのプロ将棋になかったものであり、私は59年のエポックな出来事として書きとめておきたいのである。
1図が棋聖戦第1局の投了図。
9四にいた角が△7六角と出て米長投了となったのだが、この図を見るたびに私は不思議な気持ちになる。
話を判りやすくするために一手前の局面を2図として掲げるが、この米長が7八の金で8七の歩をはらった形は、いわゆるもとが抜けた形で、指し切りと思いがちである。それがプロのカンで、何百年かの将棋の歴史がそれを教えている。
と、大きく出たが、ようするに2図の局面は、指し切り形に決まっていたのだ。だから米長もその形になればよし、と読んでいたわけで、すなわち勝ったと思っていたのである。それが、△7六角という見たことがない筋で逆転。これは一つのドラマといえるだろう。△7六角という筋があるのなら、もともと中村の勝ちで、逆転という言い方はおかしいが、流れはやはり逆転なのである。
中村のこういったところが、私の言う、土俵ぎわでクルリ身を入れ替わる持ち味で、それが現在の最高レベルの技に対して通用するかどうかが、米長-中村対決の見所なのである。第1局の結末は、それに解答を与えたことになる。
後日、そういったことを芹沢に話したら、彼は「いやそれはちがう」と言う。
「強い強いというから、第3局の立ち会いのときよく見たが、あれはたいした将棋じゃあない。あんな将棋指していたんじゃ、ろくなものにならないね。だから、終わったあと中村君に言ったんだ。君が弱すぎるから米長が負けたんだと。もし君に中原の六段時分の強さがあったとすれば、君はフッ飛ばされていた、とね」
口調がむやみやたらきついが、これは私が超一流だなどと口をきわめて褒めたのに対する反論だからで、実は中村の強さは認めているのである。その証拠に、「今度中村君と順位戦で当たっているが、そのときは私も本気で指すぞ、と宣言したんだ。1月23日にやるが、21、22日の仕事は全部キャンセルしたよ」と言った。
数年前、七段時代の谷川と対戦したとき「どのくらい強いか試してやる」といったのと同じせりふである。芹沢は、中村を谷川と同格の素質と見ているのだ。さて、終わったあとなんて言うか、楽しみなことである。
* * * * *
昨日の記事でも出てきた中村修六段(当時)の△7六角(投了図)。
棋士が体で覚えている「これで相手を指し切らせることができた」という形、を奈落の底に落とした絶妙手。
中村修六段は後に「不思議流」と呼ばれるようになるが、この△7六角も不思議流のイメージにピッタリの一手だ。
* * * * *
今でも印象に強く残っている次の一手は、1988年の中村修王将(当時)による次の一手。
不思議流とはこういうことか、と実感できる素晴らしい次の一手。
* * * * *
芹沢博文九段は、羽生善治四段が登場した時もその将棋に対して厳しいことを言っている。
基本的には非常に筋の良い将棋を指す若手棋士に対する評価は高かったが、そうではない若手棋士には厳しかった。
* * * * *
この後に行われたB級2組順位戦、芹沢博文九段-中村修六段戦は中村六段が勝っている。