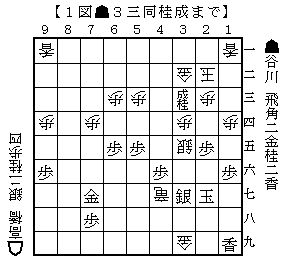将棋マガジン1991年1月号、高橋呉郎さんの「谷川浩司 ”怒れる若者”への変身」より。
谷川浩司が史上最年少の名人になってほどなく、3時間以上もインタビューした。この人には、いまだに借りがあるような気がしてしようがない。
当時、私は「週刊文春」の名将戦の観戦記を年に6、7回、書く程度で、棋界情報にも暗かった。青年名人とも面識はなかったが、故・芹沢博文九段から、その才について前々から何度も聞かされていた。
だいたい、芹沢が若手の有望棋士に下す評価は決まっていた。
「八段にはなれるだろうけど、名人になれる将棋じゃないね」
それが谷川の話になると、「タマがちがう」と一変する。
「二十年にひとりの素材ですね。私なんかとくらべたら、石ころとダイヤモンドくらいのちがいがある。谷川が凄いのは、わからないところで、平然として踏み込んでいく。将棋のスケールがケタちがいに大きいんです」
さらに、こうもいっていた。
「こいつに負けるならしようがない、と思われるようじゃないと、名人にはなれません。負けたほうが、コンチクショウと思うようじゃダメなんです。これは、将棋の強さだけじゃなく、人柄もふくまれます。中原(誠・現名人)の若いころが、そうだった。中原に負けても、だれも悔しがらない。谷川も、そうなりつつあります」
そこまでいわれたら、多少は将棋界に関係する身として、興味をもたざるをえない。新名人にインタビューする仕事も、二つ返事で引き受けたが、いささか気が重かった。
”谷川ブーム”にあやかって、福武書店が若い読者向けにムック調の「谷川浩司読本」を出すことになった。その一本の柱がインタビュー記事で、これが、なかなかの難物だった。
名人戦とか、順位戦とか、将棋界のことは、ほかのページで解説する。インタビューでは、将棋を知らない人でも興味をもてるように、できるだけ将棋以外の話を訊く。若い読者を対象なので、谷川浩司の”青春グラフィティ”みたいなものにしたいという。
そういわれても、子どものころから、将棋一筋の道を歩いてきた青年に、そんなにおもしろい話があるはずもない。おまけに仕上がりの原稿枚数から計算すると、最低三時間のインタビューが必要だった。とにかく青年名人に付き合ってもらうよりしようがない、と覚悟を決めた。
当日は、将棋連盟近くの喫茶店で会った。初対面の第一印象をいえば、けっして美男子ではないが、いい顔をしていると思った。
インタビューは、すでに将棋雑誌やマスコミで紹介されたことを、復習する部分が多かった。谷川にすれば、またか、とうんざりしたはずだが、ていねいに答えてくれた。
谷川は五歳で将棋をおぼえた。兄の俊昭氏と喧嘩ばかりしているので、父の憲正氏が将棋なら仲よく遊べるのではないかと思って、将棋の駒を買ってきた。将棋を知らない父は、百科事典を読みながら、兄弟にルールを教えたーこの話は、週刊誌に書かれている。
将棋をおぼえる以前から、谷川は、ほとんど外では遊ばなかった。将棋をおぼえて、さらに輪をかけた。少年時代を通して、ヒザ小僧にスリ傷をつくった記憶はないという。これには、いささかおどろいた。
つまり、将棋で純粋培養されたようなものだが、それにしては、ひ弱さを感じさせない。たぶん、この男は、将棋を通じて自分の運命を切り拓く、天性の強靭な意志力を備えているのではないかと思った。もっと俗っぽく、将棋を指すために生まれてきた男、といえばわかりやすいかもしれない。
案の定というべきか、二時間も経つと、質問の弾薬がつきかけてきた。将棋の話でつないで、質問をつづけたけれど、あとでテープを聞いたら、まことにくだらない、冷汗ものの質問もあった。それでも、谷川は終始、いやな顔ひとつせずに付き合ってくれた。ほんとうにご苦労さままでした。
ヘタなインタビューでも、三時間もかければ、ヘタな鉄砲と同じで、けっこう、いいセンをいった部分もある。すくなくとも、私には、谷川浩司という人物を知るうえで、たいへん参考になった。
たとえば、加藤一二三から名人位を奪った最後局で、勝ちを見つけたときの気持ちをこういっている。
「あんまりおぼえていないんですけど、やっぱり落ちつかなくなりました。いや、落ちつかない、というのでもないのかな。すぐその手を指してもいいんですけど、指すと手がふるえて、駒がうまくマス目に入らないんじゃないかな、というような感じがしたんです。ちょっと、まあ、二分ぐらい、座り直したり、メガネのレンズを拭いたり、いろいろやったんですが、それでもダメでしたね。手がふるえて、駒が斜めになっていました(笑)」
これだけでも、谷川の人柄がよく出ていると思う。インタビューをしながら、ずっと感じたことだが、谷川の答えには、背伸びしたところがない。二十一歳という年齢を考えれば、どこかで背伸びしたくなってふつうなのに、つねに自然体の答えが返ってきた。
こちらも商売だから、背伸びをすれば、すぐにわかる。それはそれで、青年らしくていいのだが、そこをちょっとつっついてみたくもなる。じつは、そういう場面を期待していたのだが、ついに、そんな気は起こらなかった。
(中略)
その後、私は谷川の対局を何局か観戦する機会があった。将棋雑誌の読者なら、よくご存知のように、谷川は対局中、まったくといっていいくらい表情を変えない。また、ほとんど駒音を立てない。駒音についてはインタビューのときに、こういっている。
「ぼくは、わりにゆっくり指すほうですから。あまり音は立てないですね。これで勝ちだ、というときなんか、感情がはいることがあって、あとで恥ずかしい気がします」
この”恥ずかしい気がする”という一言が、まことに新鮮だった。二十一歳の青年の言葉とは、とても思えない。
ここで、また芹沢の話になる。谷川に関する私の基礎知識は、その大半が芹沢から仕込んだものなので、こうならざるをえない。芹沢は谷川の将棋の才と同時に、風格ある態度に瞠目していた。
「あの若さで、あれだけ落ちついているというのは、まともじゃないですよ。谷川の家はお寺でしょう。子どものころから、人間の生死を身近に体験したからじゃないのかな」
その点をたしかめると、本人は、あっさり否定した。
「自分じゃ、まったく意識したことないです。お経を読むのも、年に数回しかないですから。大晦日と元旦ぐらいは、家族揃って読んだりしますけど。ぼくは感銘を受けたこともあまりないし……失礼ながら、父もけっこうナマグサですから(笑)。説教めいたことをいわれたことも、ほとんど記憶にないですね」
私も、その場では、芹沢の指摘は、大袈裟だったかな、と思った。が、いまでは、それが的外れでないような気もしている。
そんな谷川が、対局で感情を表に出した場面を、私は目撃したことがある。
昭和六十二年の棋王戦で、谷川は当時の棋王・高橋道雄に挑戦した。谷川が一勝して、広島で行われた第二局を、私は観戦した。
将棋は終盤にはいっても、まったくの形勢不明。控え室の検討陣も、サジを投げたようすなので、私は、ずっと盤側に陣取った。
どうせ私には盤上のことはわからない。せめて表情の変化でもとらえようと思ったのだが、両者とも、ちらりとも変化をみせない。
やがて谷川が王手をかけた。詰みかどうかはわからないまでも、終局まぎわの緊迫感は、いやでも伝わってくる。そのとき、谷川の顔が真っ青になり、表情も歪んだ。高橋は王手の成桂を金で取り、飛車の王手を待っていたように、静かに投了を告げた。と同時に、谷川が体をよじり、絞り出すような声でいった。
「ひどい将棋を指して、申し訳ありません。それ、詰まないんです」
高橋は、すぐにその意味を悟ったらしく、しばし呆然としていた。つまり、両者とも錯覚していたが、谷川は直前に錯覚に気がついた。その気持ちの乱れを、抑えることができなかった。
翌日、帰路の車中で、谷川は同行した将棋雑誌編集者に「よほど投了しようかと思った」ともらしたという。これほどまでに谷川が感情に揺り動かされたのは、このときが、最初にして最後かもしれない。見方を変えれば、対局で谷川が見せた、もっとも人間くさい場面ということもできる。
しかし、最近の谷川を遠望すると、大人の風格さえある、この青年にも、まだ感情で動かされる素地が充分に残っていたように思える。中原に名人位を奪われて、自分の不甲斐なさに猛烈に腹を立てた。その怒りが消えないままに、王位戦で佐藤康光の挑戦を受けた。
前評判では、佐藤が勝ちそうだ、という声が強かった。谷川はカチンときたにちがいない。従来の谷川なら、それを逆手にとって、冷静になることもできた。が、こんどは、そうはいかなかった―。
以後の戦績は説明するまでもない。怒り狂ったように勝ちまくった。あれは、胸中深いところで、なにかが弾けたとしかいいようがない。
将棋が変わったかどうかは、私のあずかり知らぬところ、谷川浩司は、いまや”怒れる若者”に変身した、と私は解釈している。
この調子がつづけば、期待できるのは将棋だけではない。ノッている男に女が惹かれるのは、古今東西、不変の法則であります。その道では、なんとなく引っ込み思案になりがちにみえる青年が、”怒れる若者”の勢いを駆って――数年来の懸案事項が、一気に解決しそうな予感さえする。
* * * * *
芹沢博文九段の「私なんかとくらべたら、石ころとダイヤモンドくらいのちがいがある」。
升田幸三実力制第四代名人は、この言葉を聞いて芹沢九段に、「石ころの中にも良い石がある、お前は石ころというよりもセメントだ」と言ったと芹沢九段の著書に書かれている。もちろん笑い話。
* * * * *
「こいつに負けるならしようがない、と思われるようじゃないと、名人にはなれません。負けたほうが、コンチクショウと思うようじゃダメなんです。これは、将棋の強さだけじゃなく、人柄もふくまれます」
負けても仕方がないと思わせる圧倒的な強さ、それに人柄が加われば、永世名人間違いなしということ。
* * * * *
谷川浩司九段が、小さい頃にお経を読むことがあったとは初めて知った。
たしかに家がお寺なら、あっても不思議はないことだ。
* * * * *
谷川浩司王位(当時)が終局時に言った「ひどい将棋を指して、申し訳ありません。それ、詰まないんです」。
1図がその対局の最終盤、△1三玉と逃げられると詰まない。しかし着手は△3三同金。
▲5二飛までで投了となった。
1図の直前は▲3三銀△同金寄▲同桂成。谷川王位が王手をかけはじめたのは▲3三銀から。▲3三銀と打った直後に詰まないことに気がついたのかもしれない。
「よほど投了しようかと思った」は、▲5二飛を打たずに投了しようかと思ったということになるのだろう。
* * * * *
谷川浩司九段は、このすぐ後の竜王戦で羽生善治竜王(当時)から竜王位を奪取、さらにその1年後には結婚をしている。