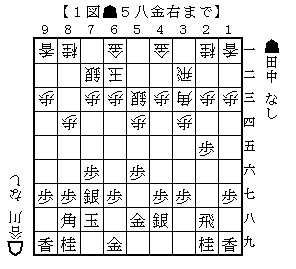将棋マガジン1990年6月号、河口俊彦六段(当時)の「対局日誌」より。
マスターズゴルフと名人戦が始まると、春たけなわという感じになる。
毎年その二つを見比べて、一方はますます盛んになり、一方は淋しくなる、ということはないんでしょうな。
それはともかく、痛切に感じるのは、マスターズゴルフにおける、パトロン(観客)とプレーヤーの素晴らしい一体感である。一打一打に声援を送るのはもちろんだが、ときには、選手の気持ちを動かすことさえある。
たとえば、選手が無理をしまいと思ったとする。しかし、観客はトライを要求する。声には出さねどそういう雰囲気はテレビの画面からも伝わってくる。そして、成功すれば大歓声だし、失敗しても勇敢な行為を讃える拍手が起こる。
競技の性質が違うから、言っても仕方がないことだが、我が将棋界も、プロがつまらない将棋を指したらブーイングが起こり、アマチュアが真似できる将棋を指してくれ、の声が、対局者の耳に入り、戦型も変わる、ということにならないものだろうか。
大内が対局室に入って来て、ポツリと言った。
「広告代理店の人に、将棋界をどう見ていますか、と聞いたんだ。そうしたら、自分達でやりたいことをやっている、と言っていたよ」
御説ごもっとも。
(中略)
特別対局室では、羽生-先崎(週刊朝日)の特別棋戦が行われていて、それを、テレビ2局が取材中だ。スタッフは一般社会のルールで取材しようとするから、いつもの妙に気を遣っておどおどしたところがない。お好み対局でもあるし、うるさいことを言う棋士もいないから、対局室に遠慮なく入り込んでカメラを回す。羽生も先崎も面食らったろうが、文句もいわず、いやな顔もしなかった。そう、こういうことになれた方がいい。ただ先崎が「参りましたよ。カメラがトイレまで追っかけてきた」とボヤいたのにはみんな大笑い。
取材陣の熱気に高揚したのか、将棋は素晴らしかった。最後に先崎が奇跡的な詰みを発見して逆転勝ち。もう人を遠ざけて対局をする時代ではない。
(以下略)
* * * * *
「アマチュアが真似できる将棋を指してくれ、の声が、対局者の耳に入り、戦型も変わる、ということにならないものだろうか」
この河口俊彦六段(当時)の文章が書かれたのは矢倉全盛期だが、アマが真似できない将棋だからこそ、見ていて楽しいという面もあると思う。この辺のバランスは難しいところだ。
歴史的には、升田幸三実力制第四代名人が、アマチュアが真似したくなるような振り飛車やひねり飛車の新しい形を多数指していた。
* * * * *
「広告代理店の人に、将棋界をどう見ていますか、と聞いたんだ。そうしたら、自分達でやりたいことをやっている、と言っていたよ」
大内延介九段は、1990年代後期、広告会社をパートナーとして、「国際将棋フォーラム」を実現させている。
* * * * *
「もう人を遠ざけて対局をする時代ではない」
このような言葉を見ても、河口俊彦八段の感覚は非常に先見性のあるものだったことがわかる。