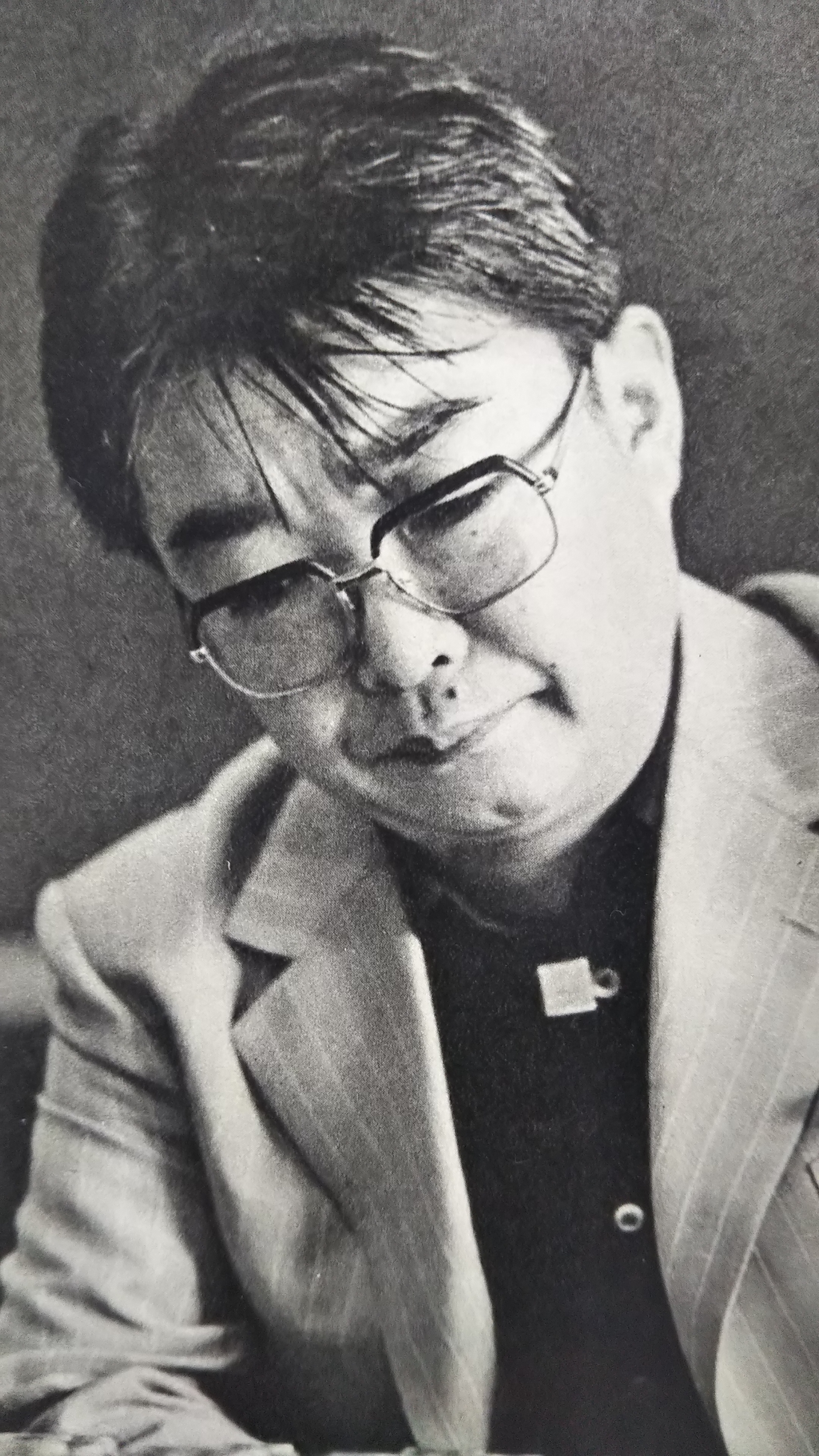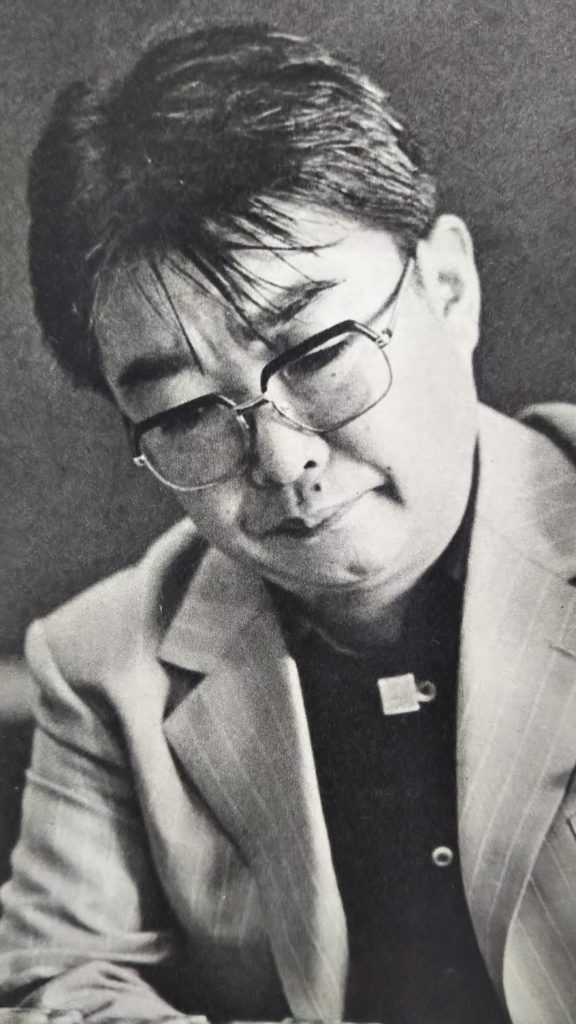将棋マガジン1991年4月号、高橋呉郎さんの「小林健二 体力将棋の継承者」より。
板谷には「将棋は体力なり」という有名な台詞がある。板谷の将棋を見ていると、その一端に触れたような気がしてくる。
最初に観戦したときの相手は、松田茂役九段だった。松田はアゴをなぜると、どこかアラカンの”むっつり右門”に似ていた。中盤の佳境にはいって、板谷の駒音がだんだん高くなった。腰が坐っているとでもいうのか、モーションは小さいのに、バシッと重い音が響いた。サウスポーの松田が、負けじと発する駒音も、”むっつり”どころではなかった。オーバースローのように振りかぶり、思いきりよく駒をたたきつける。間髪を入れずに、板谷がさらに力をこめて打ちつける。
こうなると、手こそ出さないけれど、雰囲気は殴り合いそのものといっていい。まだ観戦慣れしていなかった私は、その迫力に圧倒された。そこへ花村元司九段が現れ、しばし戦況を眺めて、呆れ顔でつぶやいた。
「よく盤が割れんもんだねえ」
また、ある対局で、体力将棋のべつの一面を垣間見た。その将棋、板谷は寄せをまちがえた。控え室の棋士は、もうサジを投げていたが、板谷の闘志は、いささかも衰えない。
夜の十時を過ぎて、残り時間もすくない板谷が、つと立ち上がり、小走りに部屋を出ていった。やがて、タバコを二箱つかんで、駆け込むようにして戻ってきた。それから五十手以上、板谷は、およそ勝ち目のない白兵戦を挑んだ。最後は満身創痍、頼朝の大軍の前に単身、立ちはだかって、矢ぶすまにされた弁慶を彷彿させるものがあった。
感想戦も終わって、新宿で一緒に飲んだ。東京で対局があるときは、東京の大学にきている息子さんのアパートに泊まるという。息子さんの話になると、「親の苦労も知らないで、よく遊んでますよ」といっていたが、口とは裏腹に、顔はたるみっぱなしだった。
板谷と飲んだのは、あとにも先にも、このときしかない。
最後に会ったのは、芹澤博文の通夜の晩だった。その日、東京で対局があった板谷は、弔問客もほとんど帰ったころに駆けつけた。帰りしなに、私を見つけて「新宿にでも行きましょうや」と声をかけてきた。私も行きたいのは山々だったが、通夜の裏方を手伝っていたので、残念ながら同道できなかった。
それから三月と経たないうちに、板谷は急逝した。訃報に接したとき、なぜ、あの晩、むりをしてでも付き合わなかったのか、とまっ先に悔やんだ。
芹澤と板谷は、古きよき時代の先輩後輩の関係を、そのまま受け継いでいた。板谷は、年齢からいえば、たいして差がない芹澤を、つねに「先生」と呼びつづけた。といっても、堅苦しい付き合いとは程遠く、むしろ、気の合った遊び仲間といえば、いちばん当たっている。
芹澤の晩年、酒びたりの生活に陥ったころ、板谷は本気になって心配した。新宿で飲んだときも、真剣な表情で私にいった。「私らがなにいっても、ぜんぜん効き目がない。高橋さん、なんかいってやってくださいよ。あなたなら、効き目がありそうだから。このままだと、名人(中原)やヨネさん(米長)も、だんだん先生をかばいきれなくなっちゃいますよ」
私なら効き目がありそうだというのは、買いかぶりもいいところで、たまたま、私は芹澤よりいくつか年長というにすぎない。すでに私の出番も、とうに終わっていて、芹澤の知人仲間では、色川武大氏に最後の望みをかけていた。
それはともかく、芹澤のことを話すほどに、板谷は、本当に困った、という顔になった。律儀な男だから、芹澤が酒びたりになった、何十分の一かの責任は自分にある、と感じていたらしい。
私が小林健二という棋士の名前を記憶したのも、芹澤を介してだった。王位戦の観戦記で、芹澤は四段時代の小林をコテンパンにやっつけた。それを読んで、あまりの痛烈さに小林の名前まで印象に残った。
小林も、その観戦記について、本誌の「忘れ得ぬ局面忘れたい局面」に書いている。最初に、観戦記を読んだときは、なんてひどいことを書くのだろう、と芹澤に腹を立てた。半年後、切り抜きが出てきて、読み返したとき、自分に足りないものがなんなのかに思い到った。以下、引用すると、
< そして芹澤先生の気持ちが少しずつ、わかりかけて来た。私は考えた。「棋士が棋士たるゆえんはプロとしての誇りと、そして将棋を愛する気持ちを持ち続ける事ではないか」と。そう考えられるようになった時、「ああ、自分はあんな将棋を指して恥ずかしい」と思った。芹澤先生には、それ以後もいろいろ教わることができ感謝の気持ちでいっぱいである >
芹澤がそこまで激しく書いたのは、それだけ小林に目をかけていたからだろう。親しい板谷の弟子となれば、なおさらそうだったにちがいない。さらにカンぐれば、板谷が芹澤に「最近、健二のやつ、すこしテングになっているから、叱りつけてください」と頼んだとも推察できる。
小林は昭和五十年十二月に十八歳で四段に昇段した。当時は最年少の棋士だった。五十二年に王位戦リーグ入りして、敗れはしたものの、米長邦雄と挑戦権を争った。いまとちがって、若手棋士の活躍はめずらしい時代だったから、二十歳の小林四段は一躍、脚光を浴びる存在になった。前述した一局は、翌五十三年の王位戦リーグの対花村元司戦。小林はこういっている。
「あのころ、ぼくらからみると、米長先生は雲の上の人でした。地位だけじゃなく、技術的にも雲の上だと思っていましたし、尊敬もしてました。だから、もう米長先生と指せるだけで、うれしかった。ところが、花村先生と指したころには、そういう謙虚さが、いつのまにか消えていたんでしょうね。芹澤先生は、いちども対局室にこられなかったんですが、ちゃんとお見通しで、怒られたんですね」
(中略)
小林にほぼ一年遅れて、谷川浩司が四段に昇段した。小林は、尻に火がついた感じがしたという。「名古屋に住んでいると、どうしてもハンディがある。対局のたびに、三日も費やさなければならない。小林は板谷に「大阪で修業させてください」と直訴した。板谷も即座に賛成してくれた。
小林の大阪生活がはじまったが、そのために師弟の関係が疎遠になるはずもなかった。小林が本当に板谷の影響を受けたのは、むしろ、独立して棋士生活を送ってからである。たとえば、
「将棋は体力なり」という名言について、こういっている。
「たしかに、師匠はよくいってましたが、言葉じゃなくて、全身から溢れ出ているというか……。将棋を指してシンドイとか、アマチュアの人のお稽古で疲れたとかいうと、師匠に”怠けとる”と叱られたものです。将棋指しが将棋を指すのは、いちばんありがたくて、しかも、いちばん楽なことをしているんだ、というわけですね。ですから、師匠の前では、疲れたとはいわないことにしたんです。同じようなことですが、将棋ファンを大事にしろ、と口が酸っぱくなるほどいわれた。プロとアマがあっての将棋界なんだ、と。じっさい、師匠をみていると、それを肌で感じましたね」
小林の話を聞いて、私も思い当たるフシがあった。いつか板谷がいっていた。
「マスコミが将棋界のことを、なんでもいい、とりあげてくれただけで、私は感謝しますよ。私で役に立つなら、いくらでも協力する。将棋を普及させるのに、こんなにありがたいことないですもの。そのへんがまだよくわかっていない、頭の古い将棋指しがいて困るんです。最近の若い棋士は、ずっとさばけてきましたけどね」
周知のように、板谷は中京将棋界の育成と繁栄に生涯をかけた。ファンを大事にするのも、マスコミに積極的に協力するのも、だれに教わったわけでもなく、自らの体験から生まれた教訓だろう。小林の言葉を借りれば、全身から溢れたものだった。
私は板谷とそれほど深く接したわけではないけれど、おそらく板谷は浮気ができない性分だったにちがいない。好きになったら、とことんのめり込む。
将棋がそうだった。ハートで愛するだけでなく、全身で愛した。惜しむらくは、体力に自信をもつあまり、無防備になりすぎた。「将棋は体力なり」という信条が、かえって仇になったともいえる。
名古屋に将棋会館を建て、奨励会をつくり、公式対局も行なう―板谷は志半ばにして倒れた。小林に胸中を訊くと、
「大阪に行くとき、いずれ名古屋に帰ります、と師匠に約束したんです。師匠が亡くなって、ぼくらは師匠の夢を引き継ぐ役目がある。ぼくらの世代ではむりでも、とにかく引き継いでいきたい。ただ、そのためにも、”並八”じゃダメなんです。幸い、こんどA級に帰ってきましたから、基礎体力をつけて、タイトルも取れる棋士になりたいですね。そのあと、引退してからになるかもしれませんが、名古屋に帰りますよ。ぼくにとって、名古屋は第二の故郷ですから」
* * * * *
(中略)の部分は、この記事に→東海の若大将
* * * * *
板谷進九段の人情味と温かさ。そして、将棋とファンと弟子に対する限りない愛情。
これらの思いは、弟子である小林健二九段、杉本昌隆八段に受け継がれている。
* * * * *