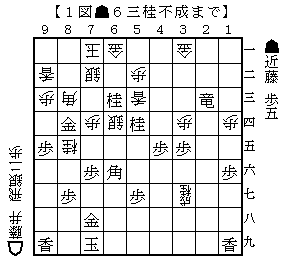株式会社フジテレビジョン代表取締役社長で日本将棋連盟非常勤理事、そして作家の故・遠藤周作さんの長男である遠藤龍之介さんのエッセイ。
将棋世界1990年12月号、遠藤龍之介さんの「打てなかった金」より。
母に手を引かれて私が小学校の入学式にいった時、父は丁度3回目の結核の手術の直後で病院のベッドにいた。週に2回、学校が終わると日当たりの悪い病室で私は暗くなるまでの数時間を、その日起きたたわいもない出来事を一方的にしゃべりながら過ごすのだった。
外に出てリハビリする程体力の回復していない父から私は沢山のゲームを習った。最初は花札とドボン(今でいうブラックジャックの変形)を教わったのだが、これはどうしても何かをのせる事になってしまい、当時月50円だった私の小遣いを結果的に父が全部巻き上げてしまう事になり、それが母にいつの日か知れる事となり逆鱗に触れ中止のやむなきにいたったのである。不思議な事にいわば被害者である自分も、バクチの正当性というのを心のどこかで納得している部分があり彼女の裁断に何かやり場のない怒りを感じた事を覚えている。
然し考えてみればたかだか6,7才の子供が一人前に花札をもてあそんでいるのは今にして思えば一種異常な状況であったのは確かで、そういった意味では奇妙な幼児体験であるのかもしれない。
退院してから私ははじめて将棋を教わったのだが、ご承知の様にこれは何ものせなくても面白いものだから私はたちまち夢中になってしまった。ようやく体が快方に向かい、徐々に仕事を再開するようになった父は週に一度か二度きまって夕方のある時間、私の相手をしてくれるようになった。いつもはピリピリしていて何か話しかけるのもはばかられるような父もこのときばかりは軽口をとばしながら駒を手に持つので、そんな時にはとても親しみやすく、私は妙に安心してしまい、勝負そのものよりも、ある時間を親子で共有することを楽しみにする様になっていた。夕食の時間になっても勝負が続いていることがまゝあって、いつもは口うるさい母も生返事ばかりの亭主には強くはいえず、必然的に私の方もお目こぼしとなる訳で、そんな時、何か自分も大人の仲間入りが出来た様で、私は当時まさしく只々そういう雰囲気を味わいたいがために将棋を指していた様な気がする。
父との手合は私の二枚落ち下手というのがパターンであった。今から考えると上手の棋力というのは甘く見積もってもせいぜいアマ4~5級程度なのだから、こちらの方は全く想像もつかぬ程の弱さだったのだろう。然し二枚引いてもらっても入るのは5番に1番位で、おまけに負かされた後で「そんな頭じゃ、いくら勉強しても成績なんか上がる訳がない」「オレの子供なのにこんなに馬鹿な奴はもう育てる気がしない」等を軽口をたたかれると生来勝負に淡白な自分もいい様のない悔しさを覚えるのだった。
そんなある日、マンガ本を買いに行った本屋の片隅で私は一冊の将棋入門書を見付けた。将棋の本、というものがあることすらその時まで知らなかった私は以来、母に教材を買うからといって金をせびっては何冊も何冊も将棋の本ばかりを買いに走るのだった。
私の棋力は急速に上昇して1年後には父と平手で充分互角に戦える様になっていた。元々我流で固まった技術と、基礎から一歩一歩学んでいった技術の差は驚く程急速に接近しつつあった。平手で3番に2つは勝てるようになってくると、向こうも滅多に私の相手をしてくれなくなっていた。私には何となくその理由がわかっていたのだが、自分が失いつつあるものの大きさにようやく気付きはじめていた。
珍しく泥酔して帰ってきた父が久し振りに盤を持ち出して来たのはそれから更に1年後位だったと思う。3番、4番と棒に負かすうちに酒もすっかり抜けてしまった様で、早く寝なさいという母の声に最後の1番を戦ったのは、多分もうかなり子供にしては遅い時間だったのに違いない。
眠い目をこすりながら指し始めた一局は中盤過ぎから私の必勝形になっていった。終盤になって相手の玉に簡単な詰みが生じていた。金を打って桂を打つという3手詰だとわかった時、私は思わず安い源平駒の金を手に持っていた。盤に打ちつけようとしたその刹那、その駒は単にその一局のトドメの駒だけではない事をようやく私は気付き、思わず駒台に戻してしまった。然し修正しようにも夢中で指していた局面は今やどうにもならない程の大差になってしまっていた。こちらの玉は覚えたばかりの銀矢倉という囲いの中に入っていてもう手もつけられない状態であった。私は呆然と盤に目を落としていた。父はしばらくすると私の気持に気付いたのだろう。顔を真赤にして駒を崩し、無言で自分の部屋に入っていった。
父にとっては多分それは一晩過ぎれば忘れてしまうささいな出来事だったのかもしれない。けれども子供の私にはその夜は確実に何かを失った忘れられない夜だったのである。
* * * * *
遠藤龍之介さんは、この頃、番組のプロデュース、企画などを行っていた。
また、夕刊フジで詰将棋欄(出題と解答)も担当していた。
* * * * *
以前も書いたことがあるが、1989年、渋谷の道場で手合がついて、遠藤さんと一度対局をしたことがある。
その時の道場での遠藤さんの段位は四段。
もちろん私が負けたが、強い四段だった。
* * * * *
「いつもはピリピリしていて何か話しかけるのもはばかられるような父もこのときばかりは軽口をとばしながら駒を手に持つので、そんな時にはとても親しみやすく、私は妙に安心してしまい、勝負そのものよりも、ある時間を親子で共有することを楽しみにする様になっていた」
「父にとっては多分それは一晩過ぎれば忘れてしまうささいな出来事だったのかもしれない。けれども子供の私にはその夜は確実に何かを失った忘れられない夜だったのである」
父と子。多くの家庭で、将棋に限らず、このような局面は違った形で起きてくるものなのかもしれない。