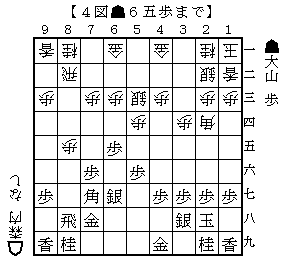将棋マガジン1991年11月号、高橋呉郎さんの「形のメモ帳:屋敷伸之 さらば、はにかみ笑い」より。
近くに住む縁者が、クルマで伊豆へ行くと聞いて、熱海まで便乗する気になった。その日、屋敷伸之棋聖に南芳一王将が挑戦する棋聖戦五番勝負の最終局が、熱海で行われていた。申し分なく暑い日で、家にいても、どうせぐうたらするに決まっている。ならば、棋聖戦でものぞいてみよう、と発心した。
ひとつには、勝っても負けても、屋敷がどんな顔をするか興味があった。
この一月ほど前に、屋敷の対局を観戦して、いい顔になってきたな、と思った。盤上を見つめていないときでも、青年の苦悩とでもいったものが、表情をかすめる。やはり、伊達にメシは食っていないな、とも思った。
少年、少年といわれながら、屋敷も、いつのまにか19歳になっている。19歳なら、りっぱな青年である。これまで、屋敷は、局後の感想もふくめて、たいていの場面は、はにかみ笑いですませてきた。自己主張が皆無だったといってもいい。
顔つきからみても、そろそろ、はにかみ笑いだけでは通せない年ごろになっている。大勝負を終えたとき、たとえ寡黙ではあっても、なにがしか大人の表情をのぞかせるのではないか、と期待した。
(中略)
夕食休憩が終わり再開後、なぜか屋敷は勝負手を指さなかった。指し手は、控え室でも検討した南勝ちのコースをたどった。検討陣が首をかしげていると、入口のほうから、「投げました」という声が聞こえた。
対局室に行くと、勝者の南が主催紙の記者にボソボソ感想をもらしていた。つづいて、屋敷も一言二言、感想をもらした。両者とも口数はすくなく、声も小さかったが、それは、いっこうにかまわない。勝負の決着がついた直後に、多くを求めるのは、人それぞれの性格もあるし、むりというものだろう。
屋敷の表情からも、私が期待したほどのものは、なにも得られなかった。すくなくとも、悔しさに耐えた顔ではないように思えた。記者の質問に答えるときも、ごくすなおにはにかんでいた。
昨年の竜王戦で、羽生善治は谷川浩司にタイトルを奪われた。あのとき、テレビに映った羽生の顔は、あきらかに、なにかを抑えている顔だった。感想も、一語一語、慎重に言葉を選んでいるように見えた。
それにくらべると、屋敷は恬淡としているというのでもない。そんな境地に達するには、いくらなんでも若すぎる。かといって、タイトルを手にしただけで儲けもの、と割り切っているふうでもない。そこまでドライに徹しているなら、ふだんから、もっとあっけらかんとしているはずである。
察するに、この青年は目の前にある現実を、つねに抵抗なく受け入れることができる、スポンジのような吸収力をもっているらしい。
(中略)
屋敷は昭和63年、16歳で四段に昇段した。私が最初に観戦したのは、その翌年の春ごろだから、まだ、外観からして、れっきとした少年だった。
少年はダブルの背広をきていた。当時流行のたっぷりした仕立てなので、よけいにしっくりしない。なんとなく高校生の学芸会を見ている気分になった。念のためにいえば、いまはもう、そんなこともない。ダブルだろうが、なんだろうが、ちゃんと着こなしている。
その将棋、対戦相手は森下卓六段で、屋敷が負けた。屋敷が盛り返した局面もあったが、感想戦で、ご当人は森下の感想にうなずく程度で、ほとんどしゃべらなかった。
終わって、両対局者に数人の若手棋士も加わり、近くの一杯飲み屋に行くことになった。歩きながら、屋敷が私におずおずと話しかけてきた。
「あそこは、やっぱり◯◯がよかったです」
◯◯とは、感想戦で私が質問した素人好みの超俗手のことをいっている。その場でも、いちおう手順は並べられたが、深くは検討されなかった。少年は、それを気にしていたらしい。私のほうは、わるい気のするはずがない。心やさしき少年であるぞよ、と好感をもった。
飲み屋では、屋敷はグラスこそ前に置いていたが、ほとんど飲まなかったように記憶する。まだ、酒の味を知らなかったのだろう。
当時、屋敷は鎌倉に住んでいた。時間が経つほどに、森下が屋敷の帰りの電車を気にしはじめた。少年が終電の時間をいうと、森下は「もう、帰ったほうがいいよ」と懸命にせきたてる。少年は逆らうことなく、ニコニコしながら席を立った。私は、そんな屋敷を眺めながら、あらためて、まだ子どもなんだなあ、と思った。
すでに、そのころから屋敷は勝ち星を重ねていた。「屋敷強し」の声も高まってはきたけれど、周囲が、その強さの正体をつかみかねて、戸惑っているような趣があった。名前にちなんだ”お化け屋敷”という呼称も、相手によって化ける、という意味がこめられている。
四段に昇段した翌年には、早くも棋聖戦挑戦者に名乗りを上げた。史上最年少、最低段のタイトル戦登場と注目を浴びたが、いぜんとして評価は定まっていなかったようだ。
もっとも、いちばん戸惑ったのは、屋敷自身かもしれない。気軽に話のできる仲間は、まだ奨励会にいる。自分ひとり脚光を浴びて、身の処し方がわからなくなったのではないかと思う。口数すくなく、はにかみ笑いで通すのも、その窮余の一策といえないこともない。
たしかに、羽生も10代で大スターの座を占めたが、佐藤康光、森内俊之、先崎学といった仲間がいた。ライバル意識も生まれてこようし、みんなで渡れば怖くない、みたいなもので、孤立感を味わうこともなかったはずである。
屋敷には、そういう仲間がいない。性格のせいもあってか、将棋会館にいても、対局室以外は、身の置き場所に困っているようにも見受けられる。
若手棋士たちがたむろする控え室にも、めったに姿を見せない。たいていは、玄関の上がり口で、立ったまま奨励会員たちと談笑している。食事も棋士と一緒に行くことは、まずない。
それかあらぬか、屋敷は自戦記を書くと、将棋のことはそっちのけで、散文詩みたいな文章になる。中身は、つきつめていけば、青春は自分ひとりで楽しむしかない、といっているようにも聞こえる。
といって、屋敷は”孤独のプリンス”を気取っているわけでもない。本誌の棋聖戦観戦記にも、打ち上げで美人の女将にかじずかれ、キャッキャッと笑い声を上げていた、と書かれてあった。
まだ屋敷は未成年だから、あまり大きな声ではいえないけれど、相当に飲んだにちがいない。それ以前、やはり棋聖戦の打ち上げ会で、升酒を8杯だか飲み、翌朝は二日酔いで起きられなかった、という話もある。
あるパーティで、屋敷はひとりぽつんとしていたので、雑談をしながら、酒のことも訊いてみた。いちばんおいしいと思うのは、日本酒の冷やだという。この年で冷やのうまさがわかるとは、これはホンモノです。それを本人にいったら、猛烈にテレていた。
成人に達して、天下晴れて飲むようになれば、まちがいなく、酒の腕は上がる。では、肝心の将棋のほうは、どうなるのか―。
もちろん、私に答えられる問題ではない。が、確実にいえることが、ひとつだけある。
これまでの屋敷は、多少、言葉はわるいけれど、成り行き任せでよかった。なんでもすなおに受け入れる、スポンジのような吸収力のおかげで、史上最年少のタイトル保持者にもなった。
こんどの棋聖戦の敗戦も、しぜんにコヤシにしていくだろうけれど、なにかが足りないような気がする。
最近、長部日出雄氏の『まだ見ぬ故郷』を読んだ。キリシタン大名、高山右近を主人公にした歴史小説で、教えられるところが多かった。
高山右近は信仰心の厚いキリシタン大名として知られているが、同時に、軍略に秀でた武将でもあった。海外に目を開いた信長は、キリスト教の布教を大目に見て、右近を重用した。秀吉も右近の軍略の才を高く買ったが、キリスト教の普及に危険を感じて、信仰をとるか、領地をとるか、と右近に迫った。右近は前者の道を選んだ。その後、前田利家に抱えられるが、家康の代になって、右近は国外に追放される―
たまたま、長部さんに会う機会があったので、もし高山右近がキリシタンでなかったら、どんな運命をたどったか、愚問を発してみた。長部さんは、しばし考えて、
「右近は欲がなかったですからね。信長も秀吉も家康も、ものすごく欲望が強かった。権勢欲がものすごかったんです。やっぱり、どんな社会でも、競争になったら、最後は欲望の強いやつが勝ちますよ。右近は脱落したんじゃないでしょうかね」
そう、これまでの屋敷には、欲のかけらもみられなかった。権力欲でも、金銭欲でも、名誉欲でも、なんでもいい。ちらっとでも、欲望に目を輝かせたら、それは、屋敷が大人の社会にはいる切符を手にしたときではないかと思う。
* * * * *
* * * * *
屋敷伸之棋聖(当時)が2期就いていた棋聖位を失冠した時のこと。
* * * * *
「たしかに、羽生も10代で大スターの座を占めたが、佐藤康光、森内俊之、先崎学といった仲間がいた。ライバル意識も生まれてこようし、みんなで渡れば怖くない、みたいなもので、孤立感を味わうこともなかったはずである。屋敷には、そういう仲間がいない。性格のせいもあってか、将棋会館にいても、対局室以外は、身の置き場所に困っているようにも見受けられる」
この部分は非常に大きいことで、羽生世代棋士大躍進の原動力でもある。
1985年奨励会入会の屋敷伸之九段と、1982年奨励会入会の羽生善治九段、森内俊之九段、佐藤康光九段、郷田真隆九段。
屋敷九段と佐藤九段を除く羽生世代棋士の学年差は1年のみだが、屋敷九段は羽生世代とは言われない。
やはり奨励会入会時期が3年違うと、中学1年と高校1年のようなもの。付き合う仲間なども変わってくるので、このようなことも起こってくる。
* * * * *
「それかあらぬか、屋敷は自戦記を書くと、将棋のことはそっちのけで、散文詩みたいな文章になる。中身は、つきつめていけば、青春は自分ひとりで楽しむしかない、といっているようにも聞こえる」
屋敷九段の自戦記は非常に味があり、面白い。
→屋敷伸之四段(当時)「将棋の棋譜は書きたくない。けれど何かが書きたかった」
→屋敷伸之五段(当時)が「笑っていいとも!」を見ているうちに思いついた一手