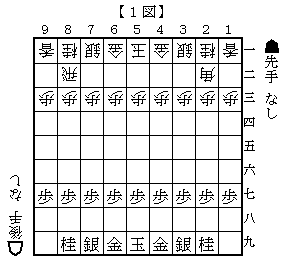将棋マガジン1992年10月号、高橋呉郎さんの「形のメモ帳:林葉直子 大人になった天才少女」より。
松本清張が亡くなった。大山康晴十五世名人につづいて、また巨木が倒れた。
存在が偉大すぎたこととはべつに、両者には、大きな共通項がある。清張さんも、大山さんも、生涯現役を全うした。だから、老木が朽ち果てたという感じがしない。
清張さんは4月に倒れたとき、週刊誌に2本の連載小説を書いていた。壮年期ならともかく、80歳を超えて、週刊誌に2本も連載した作家は、松本清張以外にいない。しかも、2本とも、盆栽をいじくるような小説ではなかった。未開の荒野に大上段から鍬を打ち下ろすような、エネルギーをぶつけた。
訃報に接した日、NHKのニュースで、生前のひとこまが映された。そのなかで、清張さんは「枯淡の境地を求めるような生き方は、私は嫌いだ」といっていた。風貌にこそ老いは隠せなかったが、老境に安じている気配は、みじんも感じられなかった。
(中略)
私は、昭和30年代の半ば、女性週刊誌の駆け出し記者のころに清張番になった。最初のうちは、まったくの使い走りだった。たいてい、締切り時間は、とうのむかしに過ぎていたから、原稿をもらうと一目散に社に帰る。ごくたまに直接本人から手渡されたときでも、ほとんど言葉を交わしたことがなかった。
何ヵ月か経って、初めて2階の書斎に通された。冬の夜で、書斎のなかは暖房が効いていたが、それが尋常な暖かさではなかった。大先生とサシで会うというので、それでなくても上気しているところへ、暖房の暑さに当てられて、私は頭がクラクラした。
巨匠はといえば、肩で息するようにして、話しかけてくる。その迫力にも圧倒されて、こちらは、しどろもどろの受け答えしかできなかった。ものの10分ほどしか話をしなかったはずだが、なにをしゃべったのか、ぜんぜん記憶にない。
(中略)
正直いって、私は清張さんが苦手だった。いつまでたっても、肩の力が抜けないので、敬して遠ざけたい気持ちが強かった。編集者としては落第ですね。
私なんかより、電話の交換手嬢のほうが、ずっと気楽に清張さんと話をしていたようだ。清張さんは、電話をかけた相手がいないと、交換手に伝言を頼みながら、冗談をいったりする。交換手のあいだでは「清張先生って、やさしいわね」と人気があった。
大山さんにも、似たようなところがある。男のプロ棋士からみれば、大山さんは近寄りがたい存在だった。これは、とうぜんだろう。大山さんのほうも、頂点を極めた人間は孤独なものだ、とわきまえているから、自分から気安く声をかけたりしない。
ところが、女流棋士との関係は、がらりと変わってくる。大山さんにすれば、女流棋士を相手に気を張る必要もない。むしろ、孫と遊ぶようなつもりで、楽しんでいたふしさえある。
女流棋士のほうでは、大山ファンの急先鋒は林葉直子女流五段がつとめた。林葉は、こともあろうに「ヤスハルちゃんって可愛い」といいだした。それに感染して「大山先生って可愛いわね」と同調する女流棋士がふえた。林葉はいっている。
「4年くらい前から、私のほうから一方的に”大山先生って可愛い”とか、ギャーギャーいいはじめたんですね。男の人に”可愛い”っていうのは失礼かもしれないんですけれども、”可愛い”のなかには、”愛”という字もはいっているし、お許しいただけるんじゃないかと思ったんです」
ことしの3月、林葉は10年間保持していた女流王将位を失って無冠になった。「やはりショックだったでしょう」と愚問を発したら、即座に答えた。
「大山先生が亡くなられたほうが、ずっとショックでした。ケタがちがいますね。私のことなんか、どうでもいいんです」
この7月10日、林葉は、前田外科に入院している大山さんを見舞った。翌日は日本シリーズの仕事で岡山に行くというと、大山さんは笑顔で答えた。
岡山は大山さんの出身地である。岡山で林葉は、なにかいいみやげはないかと思案したすえに、岡山の水と元気よく咲いているひまわりに決めた。13日に、そのみやげをもって東京に舞い戻り、前田外科に駆けつけた。大山さんが千葉県柏市の国立がんセンター分院に移る直前だった。最後になった対面の模様を、林葉はこう語っている。
「ちょうど奥様が荷物をお運びになっていて、先生と二人きりになれたんですね。私は、将棋会館でお会いしたり、仕事でご一緒させていただいたときに、いつも大山先生に”握手させてください”とお願いしてたんです。先生と握手すると、ふしぎに将棋に勝つんですね。そのことを、私は、あっちこっちで書いたり、しゃべったりしていたので、大山先生もご存知だったんです。”困った子だね”とおっしゃりながら、握手をしていただいたり…。最後にお会いしたとき、先生は、もう声がかれていました。”1週間、食べていないんだよ”とおっしゃって、右手を出してくださったんです。そういう握手をしたのは、私だけだろうな、と思っています」
(中略)
林葉が「ヤスハルちゃんって可愛い」というまでには、やはり、それ相応の歳月を要した。女流棋士になってから、しばらくは、大山名人は、はるか雲の上の存在だった。そのころは「可愛い」どころか「怖い人」という印象をもちつづけた。
4年前の正月、高齢の札幌・東急の将棋まつりに、林葉も参加した。大山さんは、この種の催しには欠かさず一役も二役も買って出て、ファンとの親睦をはかった。
札幌に着いて、林葉は、大山さんが大きな荷物を下げているのを目にとめた。だれも、そばに近づこうとしない。林葉には、それが異様な光景に映ったという―。
「大山先生は、時間があれば、色紙をお書きになったり、つねにファンのことを思われている。あの荷物のなかにも、ファンへのおみやげがはいっているにちがいないと思ったんですね。それなのに、ひとりで荷物をもって、スタスタ歩いておられる。どこか近寄りがたい雰囲気があるんでしょうね。そのとき、よけいなお世話なんですけど、大山先生はさびしいんじゃないか、孤独なんじゃないかと思ったんです。ふつうのおじいちゃんが大きな荷物をもって歩いていたら、もってあげますよね。やっぱり、大山先生でも荷物をもってあげるべきだと思って、さーあっとそばにいって”荷物をもたせてください”といっちゃったんです。荷物をおもちして、ドアを通るときに、先生がお開けになって、”どうぞ”っておっしゃるんです。その一言で、すごくうれしくなっちゃいましてね。それまでは一線を引かれていたのに、それがなくなったみたいに感じられたんですね」
この日を境にして、”最強の棋士で怖い人”が、林葉にとっては”もっともやさしいおじさん”になった。それがきっかけになって、大山さんと女流棋士たちの距離も、いっきにちぢまった。その先導役は、林葉が果たした格好になった。林葉自身は「私が、それだけ大人になったせいかもしれない」といっている。
いわれて、なるほど、と思った。林葉が10代の終わりころ、札幌で行われた女流王将戦を私は観戦したことがある。林葉も挑戦者の中井広恵現女流名人・王位も、ともに少女の面影を残していた。
こちらは、立派なオジンで、両対局者は、はるか彼方の存在に思えた。結局、前夜祭のときも、感想戦のときも、一言も口をきかずに終わった。
その後、林葉は少女向けのミステリーを書きはじめた。”とんポリ”シリーズ(講談社)は、すでに17冊を数え、延べ300万部売れている。この数字は、出版社にすれば、ちょっとしたドル箱を意味する。
小説なら、多少は私の商売に近づいたけれど、少女向けミステリーでは、手を出しかねた。今回、参考のために、最新刊の『キッスは死の香り』(集英社刊)を読んでみた。題名でもわかるように、少女向けより、やや上の層を狙っている。大胆なストーリーで、善玉のカップルが、悪玉を何人も殺す。劇画のようにテンポも速い。
将棋会館で林葉と顔を合わせて、会釈を交わすようになったのは、ここ数年のことである。そのころから、林葉は将棋連盟に新しい空気をもちこんだように思える。
(以下略)
* * * * *
「頂点を極めた人間は孤独なものだ」
たしかにそういうものなのだろう。
周りが気を遣うようになるので、どんどんと孤独さが加速されるのかもしれない。
* * * * *
林葉直子さんとは何度かお会いさせていただく機会があったが、本当に真面目で礼儀正しく、思いやりのある人柄。
「そのとき、よけいなお世話なんですけど、大山先生はさびしいんじゃないか、孤独なんじゃないかと思ったんです。ふつうのおじいちゃんが大きな荷物をもって歩いていたら、もってあげますよね」
そうは思っても実行にまでは至らないケースも多いが、それを成し遂げるところに、林葉さんの優しさが表れている。
* * * * *
「ヤスハルちゃんって可愛い」
なかなかインパクトのある言葉だ。
大山康晴十五世名人も、最初は面食らったろうが、大正生まれで一度もこのようなことは言われたことがなかったはず。嬉しかったに違いない。
→林葉直子女流名人・王将(当時)「大山先生ってば、ほんとうに可愛いんだわ」
→林葉直子「私の愛する棋士達 第1回 大山康晴十五世名人の巻」
* * * * *
「”困った子だね”とおっしゃりながら、握手をしていただいたり…」
林葉直子女流五段(当時)はこの頃、1981年度に初タイトルを獲得して以来、初めての無冠となっていた。
翌年、倉敷市出身の大山十五世名人の功績をたたえ、大山名人杯倉敷藤花戦が誕生し、林葉女流五段は優勝して初代倉敷藤花となる。
林葉女流五段にとっては、最後のタイトル獲得となった。
→「林葉さん、あんたが心配だから、もう一度、握手してあげようと思ったの。早く元気出して、しっかりしなさいよ」