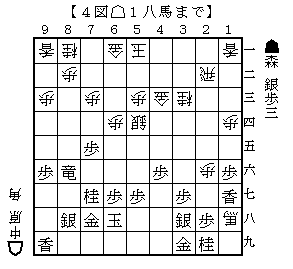将棋マガジン1984年10月号、川口篤さん(河口俊彦六段・当時)の「対局日誌」より。
私が後に兄弟子となる津村三段(当時)に会ったのは14歳の頃のことだが、その時の印象は今も鮮明である。
一人で道場へ行き、入口でもじもじしていると
「坊や、どのくらい指すの」
じろり上眼遣いに見つめられて、思わずすくんでしまったものだ。そんな眼つきははじめて見るものだった。
その後奨励会に入り、記録係をするようになると、升田、大野、花村から、若手のエリートであった原田、五十嵐に至るまで、みな対局中はじろりじろりとむきだしの眼つきで、相手を見つめることを知った。それは、刑事の眼つきともちがうし、力士が立ち会いの時、相手を威圧するかのようにじっとにらみつけるあの眼つきともちがうもので、やはり将棋指し特有のものだった。
しかし、全部の棋士がじろりじろりとやっていたわけではない。塚田、大山といった人達は、いつも相手の視線をさけるように、伏目がちに盤面を見ていた。人間の内面のことはなにもわからない子供の眼には、一方はひよわでたよりなく見えた。
それから三十数年、私の眼つきも将棋指し特有のものになっているだろう。そして少年をぞっとさせているのかと思うと、我ながらいい気持ちはしない。
さて、最近はじろり派がめっきりすくなくなった。加藤(一)、米長、中原などは、対局中、いつも目を伏せている。しかし、そう見えるが、実は相手の表情や気配をしっかりと見ているのである。この日の対局で、中原はちらりとそうもらしたが、それは私にとって、一つの新しい発見だった。
(中略)
中原-森(雞)戦は4図。△1八馬と引かれたところで森が動かなくなっている。
後手には△5五銀と立って馬を自陣に引きつける手、△2五桂と駒得をはかる手などがあり、形勢は後手よしと、記者室の見方は一致していた。
となると、森の長考は苦しがっているものと判る。たしか前期の順位戦も同じだった。どうも森は中原との相性がわるい。
86分、森は▲9五歩と伸ばした。これは記者室のだれもが思いつかない手だった。どう見てもよさそうな感じのしない手である。森だってそれは判っていたが、指す手がなかったらしい。
感想戦で「まいったよ」といいながら▲1五歩△同歩▲1四歩△同香▲1三銀、という手まで考えたと告白していた。
それを聞いて中原はにやりとした。「端の方ばかり見ていたので、そんなことを考えているのだろうと思った」
やっぱり中原も相手を見ているのだ、と知ったのはこの場面である。相手の読み筋はもちろん、気持ちのありようなどを探りつつ指すという点では、大山や米長とちがわない。ただ、中原は指し手にその気配を表さないのである。例えば大山だったら、相手のいやがっている手、恐れている手、あるいは読んでいない筋、などを見つけたら、それが盤上最善の手でないと知っていても指す。逆に、最善手であると判っていても、それが相手の読み筋に入っていると判れば指さない。つまり大山はまず相手にまちがえさせようとする。そのために相手の気持ちを読むのである。中原は、そういうことをしないように思われる。
さて、4図からは▲9五歩△5五銀▲9四歩△同歩▲9三歩△6三馬と進み、中原はジリジリと差を広げていった。
(以下略)
* * * * *
棋士と会っていても、目つきが気になったことはない。
やはり、川口篤さんが書いている棋士独特の目つきは、対局中にのみ発動されるのに違いない。
* * * * *
羽生善治竜王の若い頃、「羽生にらみ」が有名だったが、温厚なことでは棋界トップクラスの原田泰夫九段にも「原田にらみ」があったということだから、長い歴史の中では「羽生にらみ」が特別なことではないことが分かる。
* * * * *
「例えば大山だったら、相手のいやがっている手、恐れている手、あるいは読んでいない筋、などを見つけたら、それが盤上最善の手でないと知っていても指す」
昔読んだ『ザ・シェフ』という漫画。外務省からの依頼で、主人公の味沢匠が、非常に気難しくて偏屈で料理に厳しい中近東の国王だったか大富豪向けに料理を作るという回があった。
味沢匠は、この大富豪の生まれ育った土地へ行って、現地の香草を採集、この香草を入れた料理を作る。
この料理は、普通の人が食べれば特に美味しいものではなかったが、この大富豪にとっては極貧の少年時代に母が作ってくれた料理の香りと味。大富豪は涙を流しながらバクバクと料理を食べる。
大富豪も外務省も大満足という結末となったが、大山康晴十五世名人の将棋も、人の心を読む味沢匠流。
ただし、相手が涙を流すほど喜ぶものを出してくれるのではなく、その逆のことをやってくるから対局相手は辛い。