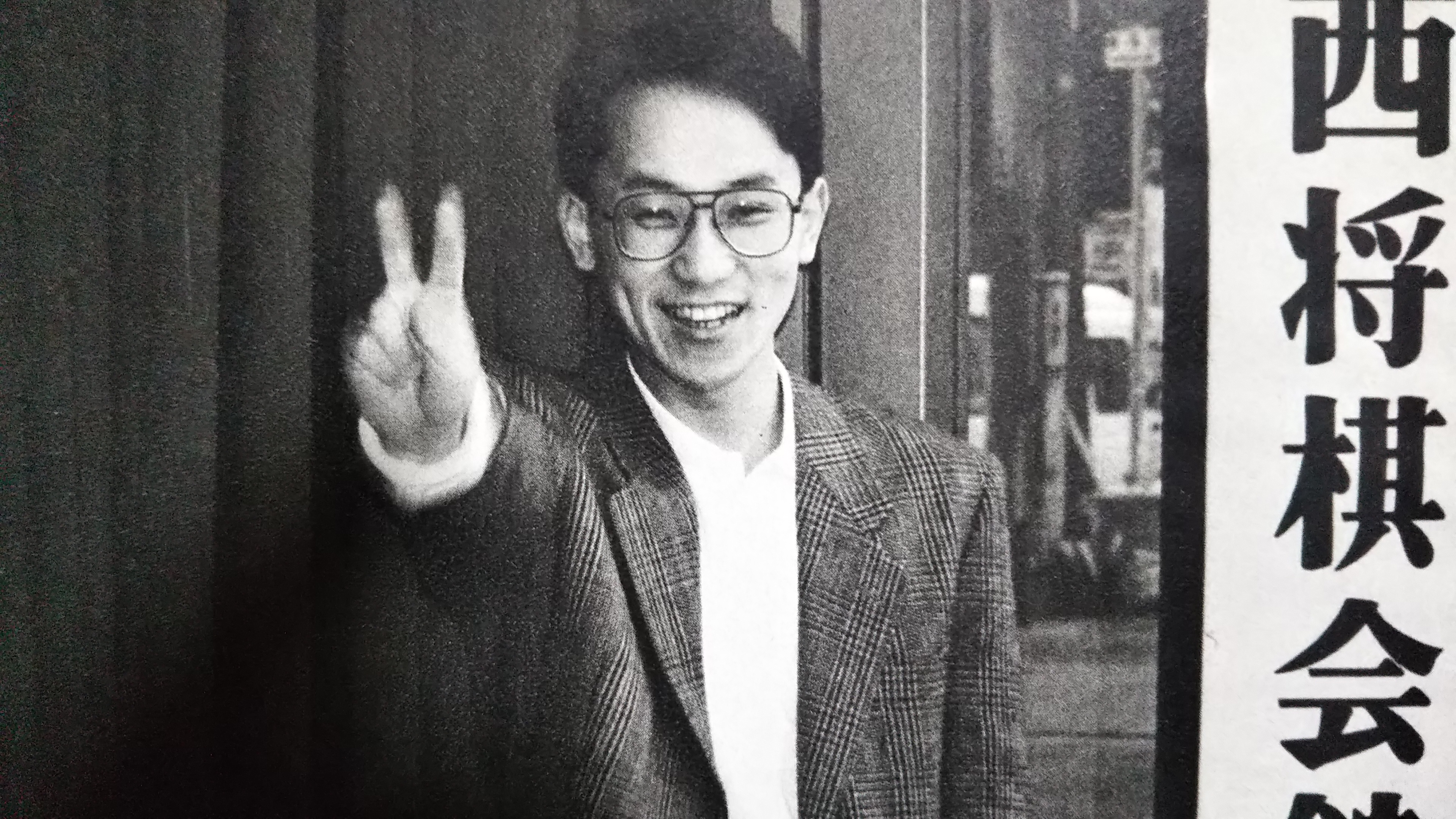将棋マガジン1987年7月号、川口篤さん(河口俊彦六段・当時)の「対局日誌」より。
【5月8日・名人戦第3局】
名人位の重み
名人戦の権威は、由緒ある名称だけにあるのではない。常に最強の者同士が戦ってきた歴史にもよる。だれもが認める最強の者でなければ名人になれなかった。そこに、名人位の比類ない重みがある。
木村から、塚田・大山・升田・中原と続いた歴代の名人を見れば、それがはっきり判る。
ところが、加藤が名人になったあたりから、ややおかしくなり、以後名人の権威は下落しつつ現在に至っている。かつては、名人が負ければ事件だったものが、今は話題にならなくなってしまった。
一方、順位戦にしても、Aクラスの権威は、ここに来て急速に落ちている。タイトル保持者は、名人かA級かにかぎられていたのが、今はご存知の有様である。A級順位戦を勝ち抜いた者が、名人に次ぐ強者とはいえなくなった。
今、名人位の第一席を守るべきかいなかが議論されているが、そういった形式的なことよりも、内容が第一席にふさわしいかどうかの方が問題であろう。順位戦形式にしても、タイトル保持者はA級に入れる、などの処置をとらないと、最強の者によって名人位が争われる、の伝統が失われてしまう。順位戦は、C2組だけでなく、上の方も、考え直さなければならない点が生じているのである。
さて、将棋界は、実態が語られることのすくない世界である。正の部分はしっかり伝えられるが、負の部分はおおいかくされてしまう。
たとえば名人戦なら、いつも名局、好局であり、戦いは、手に汗にぎる激闘でなければならなかった。すなわち、将棋界は、アンデルセン童話の、裸の王様なのである。
そんななかで、注目すべき記事がある。石堂淑朗さんが、「将棋世界」の第一局の観戦記で、
「あまりの呆っ気なさに、中原は弱い、何たる弱さか、これ書いていいよ、もう、と、森九段は口走る」
と書いているが、これこそ「王様は裸だ」と叫んだ子供の一言と同じである。名人戦の真の姿を伝えている。
余談になるが、本誌6月号にも同じ森九段の解説がある。それには、中原が弱い、なんて書かれていないので、編集部にたしかめたら、「森先生はそう言いましたが、ちょっと書くわけには……」ということだった。
第1局にかぎっていえば、あまりにひどいは、森だけが言っているのではない。ほとんどの棋士が同じことを言っているのである。中原に対してだけでなく、米長にも同じで、あの序盤を見て「米長先生は、今の将棋を知らない」と言いすてた若手棋士もいたとか聞いた。
また、第2局のときも、2日目の午後、将棋会館にいて、若手棋士達が、入って来る指し手を並べているのを見ていたが、あの攻め方は名人らしくない、と首をかしげていた。そして、中盤の戦いで、中原の竜が追い返されると、「角損に近いよ」とか言って盤上を崩し、10秒将棋で遊びはじめた。そりゃあないだろう、いやしくも名人戦ではないか、もうすこし敬意をはらったら……。せめて、見る価値がないというのなら、集った機会に、読売の契約問題でも話し合ったらどうだ、と言いかけてようやくこらえた。実戦はその後大熱戦になったが、それだけのことと片づけられてしまった。
こういった有様を内藤に話したら「タイトルも取らん者が、なに言うとる」と顔をしかめた。
内藤の気持はよく判る。しかし、言っていることには、なにをバカなことを、と聞き流せばすむが、そのように甘く見られることが問題である。中原、米長なんてたいしたことがない、と思われては、勝てる将棋も勝てなくなる、ということもあろう。
ファンの方々も、なんとなくそういった雰囲気を感じ取っている。若手棋士に同感の人もいれば、内藤に賛成の人もいるだろう。素人に玄人の将棋が判るか、とは言えないのである。いずれにせよ、新名人誕生かという状況なのにもかかわらず、もうひとつ盛り上らないのは、将棋の内容のわるさに原因がある。
将棋界のため、はもちろんだが、中原、米長自身のためにも、いい将棋を指して見せなければならないのである。
2連勝の後の第3局の勝敗が、米長にとってどんな意味があるかは、書くまでもあるまい。それよりも、はたして、名人戦にふさわしい将棋を見せてくれるか、そこに第3局を特に取り上げた理由があった。
(中略)
ところで、米長の穴熊だが、この趣向もかならずしも、よいというわけではなかった。うそかほんとか知らないが、こんな話がある。
谷川が対局場に見学に来るという話があった。ところが、穴熊を見て来るのをやめた、というのである。なんとなくありそうな話で、作り話とすれば、作った人はセンスがある。
(中略)
ここで昼休み。だれもいない対局室に入って、しばらく盤面を眺めた。なんだか暗い気持ちになった。間もなく一方的に終わりそうではないか。つまらぬときに、見に来てしまった、の後悔もあった。それはいいが、この将棋のこの内容で、10頁をどううめようか……。
恥をさらすが、本当にそんな心配をしたのである。うれしいことに、この読みは見事にはずれた。新聞、雑誌は、例によって、大熱戦、名局と書くだろうが、第1、2局と同じと思われては困る。前2戦とは段違いの好局となったのである。
(中略)
感想戦を終え、部屋へ帰る途中、小林は「いい将棋だったですね」と自分が指したみたいに喜んでいた。
「ウン、だけどまだまだだね」
「河口さんは辛いんだから」
と小林は笑った。
望蜀の嘆をいわせてもらえば、前2局よりはるかにいい将棋とはいうものの、まだ70パーセントの出来である。二人の将棋はこんなものじゃない。だいいち、内藤の直感がすべて的中したということは、内藤がいくら強いといっても、異常である。いままでだったら、だれも予想しない好手が、かならず出たのである。本局は、さすがに対局者だ、よく読んでいる、と感心させられる手がすくなかった。
しかし、ともかく、二人とも銚子が上昇気配にあることはまちがいない。後半戦に、あの「▲5七銀」の一局に匹敵するような名局があらわれそうな気がする。打ち上げの席でも、帰りの車中でも、二人はなんとなく会話をさけているような様子があった。そういったこだわりこそ、名局を生む兆しなのである。
* * * * *
なんとも厳しく、容赦のない世界。
棋士でなければ書けないような内容だ。