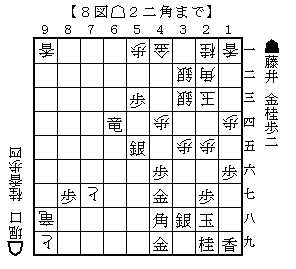将棋マガジン1991年10月号、高橋呉郎さんの「高橋道雄 マイホーム・パパの挑戦」より。
高橋道雄九段が、まだ四段になりたてのころに観戦した。それまでは、高橋の顔さえ知らなかった。将棋は、相手の某ベテラン七段を「高橋君は強い!」と感嘆させるほどに、新四段が快勝した。
それとは関係なく、対局中から高橋が本当に大男に見えた。標準サイズとおぼしき某七段より、頭ひとつぶんくらいは大きい。観戦記にも、そんな描写をした。
ところが、その後、たまたま将棋会館で両者が並んで立っている場面にぶつかって、あれっと思った。心なし程度に高橋のほうが大きいだけで、とても頭ひとつ大きいどころではない。いったい、どこを見て、なにを書いているのか、とわがことながら呆れた。
しかし、いま考えると、やはり高橋の落ちついた態度が、実物以上に体を大きく見せたような気もする。なにより姿勢がよかった。指で突っついても、びくともしないと思わせるほど、腰がすわっていた。
感想戦で、高橋は必要最低限しか口をきかなかったが、とりたてて無愛想という感じはしなかった。世の中、チャラチャラした若者がふえていたので、口数がすくない高橋から、かえって爽快な印象さえ受けた。ほんのちらっと、これは、もしかすると大物ではないのか、と思ったりもした。
対局がふえるにつれて、高橋は、西の新鋭・南芳一四段(現王将)とともに、寡黙な棋士の代表と目されるようになった。負けると、感想戦もしないで席を立つ、という話も伝わってきた。
そのころ、私も、高橋が負けた将棋を観戦したが、高橋は、ぶすっとしながらも、感想戦に付き合った。勝ったときでさえ、あまりしゃらないのだから、ほとんど感想らしきものを口にしなくても、あまり気にならなかった。
じつは、高橋が負けて、一言も発せずに席を立つ場面を、私は、ひそかに期待していた。相手の棋士もいるし、観戦記は、なんとでも書ける。高橋が憮然として、感想戦を拒否する場面に、いちどは立ち会ってみたいと思っていたので、いささかがっかりもした。
もっとも、当時から、私は、高橋が本当に寡黙なのかどうか、疑問をもっていた。たしかに、口数はすくないけれど、程度の問題で、寡黙というほどではない。なんとなく、天性の寡黙ではないようにも思えた。
(中略)
作家では、生前、川端康成の寡黙が伝説化されていた。目だけが異常に大きい、あのミミズクみたいな顔で、一言も発しないで、相手の顔を二十分でも、三十分でも見つめる。川端康成を担当した編集者たちは、だれもが、この沈黙の視線に泣かされた。
私は幸か不幸か、いちども会ったことがなかったけれど、女性週刊誌の編集者だったころ、ごく身近に被害者がいた。編集長みずから乗り出して、川端康成に連載小説を頼みにいったことがある。まだノーベル文学賞は受賞していなかったが、女性週刊誌からみれば、川端康成は、はるか雲の上の存在だった。ちなみに、そのころ、超人気作家でも、原稿料は一枚(四百字詰原稿用紙)一万円に達していなかった。もし、川端かウンといったら、おそらく最低一枚一万五千円は払ったにちがいない。この数字は、当時の大卒の初任給よりも高い。
面会の約束は、意外に簡単にとれた。編集長は勇躍、鎌倉の川端邸を訪れた。
初対面の挨拶をすませ、さっそく用件をきりだした。雑誌の現況を説明し、若い女性読者が、いかに先生の小説を待ち望んでいるか、熱弁をふるった。その間、大作家は、うなずくでもなく、質問するでもない。ただ、じっと編集長の顔を見つめている。話が終わっても、ロを開く気配はなかった。編集長は、こんなふうにいっていた。
「いつ果てるともなく、黙って、こっちをにらんでいるんだ。噂には聞いていたけど、あそこまでとは思っていなかった。なにしろ、あのギョロッとした目で、にらまれるんだ。おれも、自分じゃ、相当、図々しいつもりだけど、だんだん、いたたまれなくなった。すると、ようやく一言、”いいですよ”って。しめた、と思って、いつごろからお願いできるか聞いたら、ウンでもスンでもない。また、ずーっとにらまれて、”そのうちにね”といって、腰を上げちゃった。それ以上は、どうしようもなかった」
その連載小説の話は、いつのまにか立ちえになった。
川端と学生時代から親交のあった今東光によると、何度も川端のダンマリを見せつけられたという。川端が東大生のとき、一緒に菊池寛を訪ねた。川端は菊池寛の顔を見るなり、「百円要ります」といった。月給百円なら、高給取りといわれた時代である。川端は、貸してくださいともいわないし、理由もいわない。一言だけいって、あとは菊池寛の顔をじっとにらんでいる。
大文豪のほうは、もう慣れているらしく、川端には声をかけない。今東光とばかり話をする。川端はダンマリをつづけている。やがて菊他寛が懐から財布をとり出し、十円札を数えて手渡すと、川端は黙って札をしまい、礼もいわずに帰っていったー。
今東光は「カネもらいにいくのに、借金取りにいくようなもんだ」と呆れていた。卒業論文も、主任教授を一時間近く黙ってにらみつけ、書かなくていいようにしたそうだ。
こうなると、ダンマリの天才としかいいようがない。それが川端の盛名とともに、いっそう威力を発揮したらしい。
(中略)
比較する対象がわるいけれど、高橋の寡黙は、ノーベル賞作家のダンマリとは、かなり趣がちがう。高橋は本来、それほど無口ではないのに、むりやり口から出る言葉を封印してしまったように思える。あるいは、対局後に迸りそうな感情を抑えこむことを、自分に課したといってもいいかもしれない。
プロ棋士には、負けず嫌いが多い。なかでも高橋は最右翼に位置するといわれている。それを証明するような逸話にも事欠かない。
某棋士が将棋会館にいくと、高橋が玄関から出てきた。その日、高橋は対局があったので、勝敗を訊ねたら、高橋は、やにわにもっていた紙袋を地面に叩きつけたという。順位戦の将棋を負けて、深夜、土砂降りのなかを、タクシーに乗らず、カサもささずに歩いて帰ったという有名な話もある。
高橋は、そういう自分の性格をよく知っていた。どんな将棋でも、負ければ悔しい。感想をもらせば、言葉が感情を誘発して、激情に駆られるおそれがある。それを抑えるために、まず口をきくまいと決心した――私は、そう解釈している。
だから、敗局後に口をつぐむのは、ひたすら感情の動きを抑えている時間といえるだろう。そこさえしのいで、ひとりになれば、土砂降りのなかを歩いて帰ろうが、なにをしようが、勝手なことができる。
悔しさがつのって、感想戦にも耐えられそうもないときは、やむをえず席を立つ。対局室で感情を暴発させてしまうのが、なによりも怖い。根が慎重な性格だから、あらかじめ危険を避ける。
言葉というのは、やっかいなもので、負けて悔しいときだけ、内に秘めておけばいいというわけにはいかない。勝ったときも、しぜんに口数はすくなくなる。ふだんの言動も無意識のうちに控えめになってくる。こうして鬱積した言葉は、文章を書くときに発散されるらしい。高橋は、およそ重厚な棋風とは似つかない、饒舌体の文章を書く。あれは、抑えつけている話し言葉の恨みを晴らす、仇討ちにちがいない。
高橋の饒舌体の文章は、劇画雑誌の影響を受けたともいえる。奨励会時代に劇画雑誌を耽読して、三万冊だかたまったという。文章のなかに突如、出てくるおしゃべりは、漫画の吹き出しの感覚に近い。
しかし、より正確には「饒舌体の文章を書いた」と過去形にすべきかもしれない。最近は、重厚とはいわないまでも、だんだん文章が落ちついてきた。
いや、変わったのは文章だけではない。負けて席を立つようなことはなくなった。ポツポツながら、ちゃんと感想ももらす。ときには、自分の指手に苦笑することさえある。
最近は、寡黙ぶりよりも、マイホーム・パパぶりのほうが注目されているといっていい。もともと棋士仲間と付き合いがないので、いっそう家庭にのめり込んでいるようにみえる。『将棋年鑑』の「棋士名鑑」にも、座右銘は「家庭円満」、世の中で一番恐いものは「カミさん」、今一番興味を持っているものは「子供の成長」とくる。相手かまわず、娘自慢をするタイプではないけれど、いざとなると臆面がない。
「近代将棋」が月がわりで棋士に編集長を委嘱した。高橋の番になったとき、この編集長は、家族三人がディズニーランドで遊んでいる写真を表紙にしたい、と提案した。さすがに編集スタッフが難色を示し、グラビアに自宅でのスナップを載せることで折り合いをつけたという。高橋に悪気があったはずもないが、マイホーム・パパの面目躍如たるものがある。
感想戦で笑みさえ浮かべるようになったのは、マイホーム・パパになったのと無関係ではないらしい。
* * * * *
特に21世紀になってからの高橋道雄九段を思い浮かべると、高橋呉郎さんの洞察力が非常に鋭いということがわかる。
* * * * *
高橋呉郎さんは1933年生まれ。1959年に光文社に入社。「女性自身」「宝石」の編集にあたった後、1970年に退社。1971年から1974年まで、梶山季之氏主宰の月刊誌「噂」の編集長を務め(1974年に「噂」が終刊)、その後はフリーに。将棋ペンクラブ大賞最終選考委員も務めていただいた。
* * * * *
「噂」は、文壇・マスコミ界の埋もれた逸話を記事にしていたので、高橋呉郎さんは作家のエピソードにも詳しい。
川端康成氏のエピソードはとても面白いが、どのような好奇心旺盛な人でも、その場には同席したがらない思う。