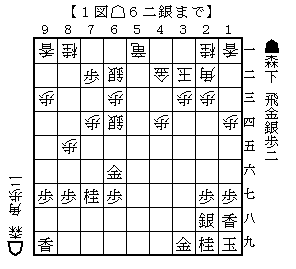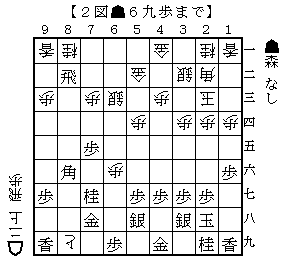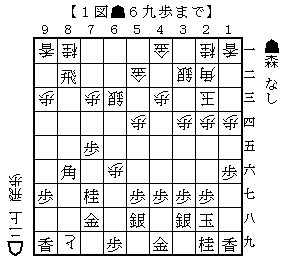将棋世界1989年1月号、福本和生さんの「検証・素顔の棋士達 森雞二王位の巻」より。
昭和60年7月、第46期棋聖戦の五番勝負第2局は、ロサンゼルスのホテルニューオータニで行われた。
米長邦雄棋聖に挑戦者が勝備修八段(現九段)で、米国本土での初の対局とあって将棋連盟は「口ス棋聖戦フェスティバルツアー」を募った。定員60人がたちまち満員となった。このツアーに森雞二八段(現王位・九段)が参加した。
森の狙いはツアーコースに入っているラスベガスである。口スに到着するやいなや森はラスベガスのカジノへまっしぐら。
わたしたちは対局をすませて翌朝ホテルを立ってラスベガスに向かった。
ここからはだれかの創作と思うので、そのつもりでお読みください。
森は二日間ぶっ通しの激闘で、持参したン百万円の資金がほとんど底をつく状態だった。さすがのギャンブルの鬼も連戦連敗で憔悴の極に達していた。
そこに大山十五世名人らの一行が到着した。森にとっては救世主とみえたのだろう。大山さんのそばにかけよって「会長、お金を貸してください」。森の切迫した顔をみた大山さんは即座にこう答えた。
「森クン、落ち着きなさい!」
ここからは眉につばをつけてお読みあれ。
”生か死か”といった森の思いつめた顔をみた大山は、ここでドルを渡せば傷はさらに深まると咄嗟に判断、突き離すのが最善策とみての”落ち着きなさい!!”である。脈なし、と思った森は、一行のなかに”かっちゃん”はいないかと捜した。親友の勝浦八段に懇願しようとした。ところが勝浦八段はいない。聞くとツアー連より遅れて来るという。一日でなく一時間千秋の思いとはこのことか。森は親友の到着をじりじりしながら待ちわびていた。
勝浦九段の証言。
「ギャンブル場に入ると、森さんが歓喜の表情でかけよってきました。持ち金はすっからかん、このままでは無念で日本に帰れない。もう一勝負で必ず挽回するから資金を貸してくれ。戦いすんでラスベガスを出発するとき、手もとに残ったのは、わたしが残していた百ドルだけでした」
翌朝、早く起きたわたしは、何気なくギャンブル場をのぞいてみた。だれもいないと思ったら、なんと森が一人でカードを配ってもらっていた。一縷の望みに賭けて徹夜で闘い続けていたのだ。
森のタイトル戦初登場は、昭和52年の第30期棋聖戦であった。
大山棋聖に挑戦したが、31歳の森はさっそうとしていた。
このシリーズ、第2局が八戸市の「はちのへ・ハイツ」、第3局が出雲市の「武志屋山荘」と遠距離の対局場であった。飛行機を利用すれば短時間ですむのを、森は断固として「陸路を行きましょう」。
理由を聞くと「鉄の塊が空中に浮くのがおかしい」である。
八戸市は上野駅から特急で7時間余、出雲市は東京-岡山間を新幹線、岡山-出雲間は伯備線で8時間。長道中の旅であったが、なつかしい思い出である。
「高校生のころ、オートバイで走っていたらダンプにぶつかって、一瞬、ぼくは空中に舞いあがって…。それが川の土手を転がってケガなしなんですよ」
列車の旅ではこんな話を聞いていた。
高知県中村市の出身であるが、森を”土佐っぽ”だなあと思ったのは、出雲市の対局を終えたあと、出雲大社から日御碕の燈台に昇ったときだ。
7月上旬の暑い日だった。
森はシャッをぬいで上半身裸のままで、観光客でにぎわう日御碕にやってきた。目ざとく燈台をみつけて、「福本さん、昇ってみましょう」。
森は灯台内の垂直の鉄梯子をかけ昇るようにして昇っていった。
わたしは手の汗をぬぐいながら、下をみないようにして鉄梯子にしがみつくようにして昇っていった。
頂上から見た日本海は雄大であった。
森は両腕を胸の前でがっしりと組んで空と海がぴたりと合体している水平線のかなたを、佇立したままいつまでも眺め続けていた。強い夏日を受けて、森の上半身から汗が噴きだしていたが、森はあかずに海に魅入っていた。高知の桂浜を想い起こしていたのかー、
翌年、昭和53年に森は中原誠名人に挑戦した。名人戦史上に残る”森、剃髪の挑戦”の第36期名人戦である。
中野英件さんが撮った、すばらしい写真集は、異様な対局風景が活写され力感無類である。
「対局の朝、挑戦者が突然、頭を丸めて登場したらたいていの人は驚く。それが前日まで何の変化もなく、明るくふるまっていた森雞二八段だけに、驚きはより大きい。
対局の朝8時20分に第1局の対局場仙台ホテルに現われた森八段にびっくりした。対局開始5分前、中原名人につづいて森が登場。こんどは私以外の人が驚く番だ。対局室は森の剃髪に一種異様な空気が流れた」(毎日新聞・加古明光記者)
名人戦開始前の森語録も評判を呼んだ。
「中原将棋は強くない。相手が勝手に転んでるだけだ。こんなやりやすい相手はいない」
剃髪といい刺激的な発言といい、迫力満点である。
これほど話題満載の名人戦は珍しい。
森は一躍スターになったが、将棋というゲームが面白そうだと一般の関心を呼んだのは、森の果敢さの功績であろう。
さらにこの名人戦は第3局の「銀波荘」対局がテレビで放映された。NHKテレビ「勝負―将棋名人戦より」は、それまでタブー視されていたタイトル戦の対局室に、テレビカメラが入って盤上、対局者の表情をとらえたことで画期的であった。
これは余談になるが、将棋の普及が遅遅として進まない主因は、将棋が密室ゲームであることだとわたしは思っている。タイトル戦を温泉地やホテルでなく、広いホールでファンの見守る中で公開対局にすれば、将棋ファンは激増するだろう。
NHKテレビの名人戦放映の視聴率は12%という高率であった。
「空気は汚染され水は濁り、東京は人間の住む所ではない。子供達のためにも大気が澄み水の美しい高知に帰りたい。勝負師の限界を感じたら、郷里で 将棋教室を開いてレッスンプロで後輩を育てたい」
第40期棋聖戦(昭和57年)で初タイトルの「棋聖位」を獲得したとき、森は「40歳になったら郷里で暮らしたい」と話していた。当時の森は36歳であった。が、40歳で郷里のうまい水を飲む森の人生設計は、ちょっと早すぎたようだ。
42歳の今年、森は「王位」のタイトルを手中にした。
王位の挑戦者決定戦、森と森下卓五段の対局は、6月24日に行われた。わたしは観戦記担当だったが、穴熊の森下が巧妙な指し回しで優位に立った。控え室の継ぎ盤を見た中原、米長が”森下よし”だから、挑戦者は森下で決まりかと思っていた。
午後10時すぎ、森の△5一竜に森下は▲7二歩と打った。次に▲7一飛で△同竜▲同歩成でと金を作って森下の勝勢である。
ここで森は△6二銀(1図)と打った。
「延長戦にもっていく一手か、フフフ」
と森は不敵な笑いを浮かべていた。
△6二銀は▲7一飛を防いだだけの手である。駒の効率的な使いかたに腐心するプロのヨミにない手である。
森は「考えて指したのでなく手が自然にいった」と話していたが、良くも悪くも森将棋の特質を示すものである。
第40期棋聖戦で、森は二上棋聖に挑戦した。その第1局の芹沢観戦記を紹介する。
「(森の飛行機ぎらいにふれて)本人が云うに今年は飛行機がいけないと占いに出たそうであるが、占いなんぞ信じる将棋指しは真にもって珍なるものである。この飛行機に乗らぬことと、いつぞやの名人戦で突如剃髪して現れたことと何か共通しているような気がする。森には良い意味での”狂気”を感ずる。ことによると筆者らを越えた素晴らしい”感性”があるのかも知れない」のあと、二上優勢で森が▲6九歩(2図)と打った局面で芹沢さんはこう解説する。
「米長が意外な手だと云っているのであるから、と云うことまで考慮してそれぞれ書いたようである。米長は『ハイ、〆切です。当たりは▲6九歩です』誰一人として当たりなし。こんな手、どんな頭で思いつくのであろうか、この手の意は△8八と▲同金△6八飛を防いでいるだけである。
プロの指し手は一手に最低二つの意味がある。▲6九歩は一つしか意味がない。プロの思いつかぬ手である」。
対森下戦の△6二銀と、この▲6九歩は共通した感覚だと思う。
この手は、森でなければ指せない独自の感性である。
「棋聖位」から5年たって森は「王位」に就いた。
谷川と七番勝負を戦って競り勝ったのは見事である。
「将棋は手数を読めれば強いと云うことではない。読まずに、少ししか読まずにそれが正しいと判断出来る大局観が必要なのである。この大局観は鍛練で得られるのと、本能に近い肌で感ずるような二種類あると思う。森はその両方を得ているようである。得難い才能と思う」(芹沢観戦記から)
谷川-森の王位戦を、わたしは第2局と最終局の第7局を観戦した。
第2局に敗れた後の徹夜のマージャン風景も目に残るが、それよりは第7局で勝ちがみえてきたときの、一手指すごとに立ちあがって手洗いに行き、胃液を吐きながら闘い抜いた森の、何かに憑かれたような表情が忘れられない。
芹沢さんが言う。良い意味での狂気の状態であった。
ぎりぎりの終盤で、手洗いに立った森はそのままドアの前で立ちつくしていた。握りしめた左手のおしぼりが、ぶるぶるとふるえていた。
明朗で快活な、ふだんの森からは想像もできない、ぞっとするような勝負師の顔であった。
ラスベガスのカジノで、ただ一人でカードに挑戦していたとき、日御碕の燈台で日本海をにらんでいたとき、名人戦に剃髪で登場したとき、そして王位戦のこぶしをふるわせていたとき、森は同じ顔であった。
王位戦最終局の振り駒で、森は記録の高田三段に「天井にとどくぐらい高く振ってよ。うんと高くね」と注文した。先番が握りたかったのだが、堂々と注文するのが森流である。念力を信じているふしがある。
そういえば、対局中も森からはいろんな発言を聞いた。
大山棋聖に挑戦したとき、控室に現われた森は「次は妙手を指すからね」と自慢していた。妙手予告というのを初めて聞いた。
中原棋聖と熱海の「石亭」で対局、中原優勢の局面で森は苦心の一着。中原が指す構えをみせると、森は「切れてくれ」と叫んだ。中原が応手を誤ると切れ筋があるのだが、そんなことは中原はとっくに承知である。だから森の叫びを聞いて中原は「そんな無茶な…」と言って思わず苦笑してしまった。
王位挑戦権の森下との対局でも、途中で「間違えてくれ!」と言って森下をあきれさせていた。
森が勝負の世界という魔界に身をゆだねたとき、その将棋に凄味と精彩が加わるような気がする。その境界を踏みこえるためのスプリング・ボードが一連の念力ではないか。
飛行機に乗らないとき、新幹線でも万一の事故はあるよ、と言ったら、
「列車事故なら奇蹟的に何人かは助かる。その何人かの一人に、ぼくは入っている」
10月下旬、東京・日比谷の「松本楼」で、森王位の就位式があった。広い会場が出席者であふれるほど。
森はニコニコと明るい笑顔。現在、最年長のタイトル保持者である。奥さんや子供さんたちも参加して、なごやかな就位式であった。
「七番まではいかないと思って、オーストラリアに出かけるつもりで予約してましたら、7局までもつれて予約金を損しました」
うれしさが言わせる冗談であるが、予約金の5万円を損しても王位のタイトルなお余りあるものがある。
若手の時代の将棋界に、中原が王座に返り咲き、森が王位を奪取して中年パワーの底力を示したの感がある。
そのまえに30代の田中寅彦棋聖も誕生している。
その田中が「今は私が最年長タイトル保持者ですが、そのうち私が最年少タイトル保持者になりますよ」と、棋聖になった直後に話していたが、タイトルをめぐる世代のせめぎあいはこれから一段と激化しそうだ。
「よくポカをやるから…。これは大丈夫だろう。うん、うん、大丈夫だ。これを間違えるようでは…」
王位戦7局目の終盤で、森が▲4三銀と打つ直前のひとりごと。谷川は席をはずしていたが、森はいったん手にした銀を駒台に返して、右手を空中で2、3回強く振った。そして再び銀を手にして、はっしとばかり▲4三銀と打った。
森の顔は美しく紅潮していた。
勝負の魔界から、するりと抜けだしていた。
* * * * *
「ここからはだれかの創作と思うので、そのつもりでお読みください」と福本和生さんは書いているが、福本さんがこの当時の棋聖戦担当の産経新聞の記者だったので、本当の話と思って間違いないだろう。
* * * * *
「プロの指し手は一手に最低二つの意味がある」
これは、とても考えさせられる言葉だ。もちろんプロとは比較にならないが、自分の将棋を振り返り、そのようなことを一度も意識したことがなかったことに気付く。
* * * * *
「一手指すごとに立ちあがって手洗いに行き、胃液を吐きながら闘い抜いた森の、何かに憑かれたような表情が忘れられない」
谷川浩司八段(当時)が新名人となった1983年名人戦第6局〔加藤一二三名人-谷川浩司八段〕、江國滋さんの観戦記では谷川八段が詰みを発見した瞬間、「ああ、という押し殺したような声とともに、挑戦者が不意に喘ぎはじめた。息苦しそうに顔を左右にはげしく動かし、手さぐりでひろいあげた純白のハンカチを急いで口元に押し当てながら、肩で大きな呼吸をくり返した。どう見ても嘔吐をこらえているとしか思えない苦悶の表情だった」と書かれている。
考えに考え抜いて、光明が見えてきた瞬間に(あるいは非常に安心した瞬間に)、急に吐き気が襲ってくることがある。
森雞二九段が胃液を吐いたのは、同じような状況と考えることができる。
* * * * *
「切れてくれ」「そんな無茶な…」のやりとりがあったのは、1983年の第41期棋聖戦五番勝負〔中原誠前名人-森雞二棋聖〕第1局でのこと。
→森雞二八段(当時)「おいしそうだな、2個は食べられないでしょう」、中原誠棋聖「いや、食べる、食べる」