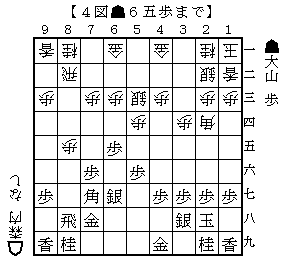将棋世界1991年11月号、スポーツライターの玉木正之さんのエッセイ「丁稚の将棋 旦那の碁」より。
わたしは将棋が大好きである。
下手の横好き、振り飛車一本槍という程度の実力であるうえに、最近は盤に向かうことすらまったくといっていいほどなくなったが、それでも、将棋について訊かれると、声を大にして胸を張り、わたしは将棋が大好きだ、と答える。その言葉の裏には、わたしは囲碁ではなく将棋が好きだ、という意味が込められている。そして、そう答えることのできる自分に、ほのかな心地好さすら感じている。
というのは、わたしに将棋の指し方を教えてくれた人物―すなわち、わたしの父親が、将棋を指すたびに口にしていた言葉を思い出すから、である。
「丁稚の将棋、旦那の碁、というてな、丁稚は将棋を指すもんや。囲碁は旦那にまかしとけ。丁稚には将棋が似合うんや」
といった具合に、わたしの父親は、盤上を見つめ、わたしから奪った駒を楽しそうに手のなかでジャラジャラと鳴らしながら、口癖のように「丁稚の将棋、旦那の碁」という言葉を何度も何度もくり返したものだった。
京都の祇園で小さな電気器具販売商を営んでいる父親は、終戦直後に徳島の山奥にある寒村を離れたあと、大阪の市岡という下町にある電気店で、何年間か丁稚奉公を経験したという。わたしは、その話を子供のころから聞かされ、知っていた。だから親父は囲碁でなく将棋を指し、「丁稚の将棋、旦那の碁」という言葉を口にするのだろう……と思っていた。が、中学生になったころ、わたしは久しぶりに親父と盤を挟んだ折に、少しばかり疑問に思ったことをふと口にした。
「昔は丁稚でも、今は店を持ってるんやから旦那やろ」
「まあ。そうやな」
「ほな、なんで囲碁をせえへんの?」
親父は、じっと盤面を見ながら、しばらく何もいわなかったが、やがて、口を開いた。
「旦那か丁稚かというんは、立場で決まるもんやない。それに丁稚が旦那より下というわけでもない」
親父はそれだけで口をつぐみ、わたしは親父の次の一手の王手飛車取りに、「エエーッ」と声を張りあげ、「待った、待った!」「阿呆いえ!待てるか!」「1回だけ、勘弁してえな!」「あかん、あかん!」などといいあうなかで、その話題は立ち消えになった。
その後わたしは、青年期を迎えた世の男の子がすべてそうあるように、父親との交流以上に悪友との付き合いが中心になり、親父と盤を挟むことはなくなった。が、このときの親父の言葉は、意味のよくわからないまま、なぜか何度も思い出された。
高校生になり、大学生になると、何人かの友人から囲碁を覚える機会を得た。
「将棋よりも囲碁のほうが奥行きが深いぞ」と、彼らは口をそろえた。なるほど囲碁とは、石の並び方の美しさに宇宙を感じるものだ、とも思ったが、その奥行きは頭で理解しながらも、心の底からのめり込むということが、どうしてもできなかった。
それは、「丁稚の将棋、旦那の碁」という親父の言葉が脳裏にこびりついていたからに違いない。
いま考えてみると、わたしは親父の言葉から「人間の分際」と「人間の矜持」とでもいうべきものを学んだと思う。
人間には「分際」というものがある。しかし、それによって自らを卑下する必要もなければ、自慢するべきでもない。人は「身の程」というものを知ることによって、はじめて自分のできることがわかる。
将棋は将棋、囲碁は囲碁。碁で勝つ者は将棋で負ける。歌は碁の如く詩は将棋の如し。
どっちが上でどっちが下ということは断じてない。
少々理屈をこねるなら、そのような多様性のなかにこそ文化の広がりがある、といういい方ができるに違いない。そして、そのような多様性と広がりのすべてのなかに、一人の人間が身を置くことなどできない、ということだ。それが「分際」というものだろう。
今年の夏、女房と3人の子供を連れて、久しぶりに京都の電気屋に帰ると、腰の曲がった親父が「久しぶりに、いっちょ、やろか」といって、将棋盤を引っ張り出してきた。わたしは、「長幼の序という言葉を知っとるなら、この手は待て」などと強権を振り回す親父に苦笑いしながらも、楽しい一時を過ごした。とはいえ、わたしがその一手を待ってやったおかげで逆転勝ちした親父が、「やっぱり、まだまだわしの方が強いな」といったときばかりは、本気でムッとしたのだったが……。
* * * * *
個人的には、将棋と囲碁は、隣接するものではなく、全く世界の違うものだと思っている。
「将棋よりも囲碁のほうが奥行きが深いぞ」は、「トンカツよりもアイスクリームのほうが奥行きが深いぞ」や「サッカーよりも茶道の方が奥行きが深いぞ」のような言葉と同様、比較をすること自体がおかしい意味のない言葉だと思う。
「丁稚の将棋 旦那の碁」も、比較をすることに意味がないという、同じような考え方と言って良いだろう。
* * * * *
「身の程」という言葉で思い浮かぶのが、司馬遼太郎『項羽と劉邦』、およびそのベースとなっている『史記』。
自分の持っている器量というものを理解し、身の程をわきまえた人が成功している。(言葉を変えれば、殺されていない)
「身の程をわきまえる」というのは自分のためのリスク管理であって、決して消極的・退嬰的なことではない。
最も身近な例は酒で、自分の身の程を超えた量を飲むと、ろくなことにならない。
50人の企業の名経営者が300人の企業の名経営者になれるとは限らない。
企業を発展させる過程で、その経営者が持つ器量を超えた段階(規模)から、変になり始めることも多い。
3億円の自己資金で株式投資に大成功していた人が、ファンドを作ってお金を集めて50億円の運用をやって、大失敗するケースもある。
バブル時代、経験のない分野での新規事業をいくつも立ち上げて、ことごとく失敗した大企業も、結果的に身の程をわきまえていなかったと言うことができる。
* * * * *
プロの将棋の対局の盤上においては「身の程」を考える必要はない。むしろ考えてはいけないのかもしれない。
そのような意味でも、勝負の世界は見ていて純粋に楽しめるということになるのだろう。