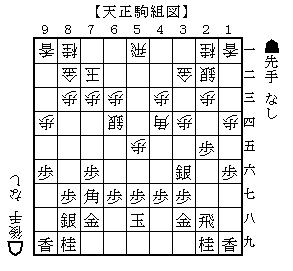将棋世界2005年6月号、先崎学八段(当時)の第63期名人戦七番勝負開幕特別寄稿「将棋界を変えたふたりの名人戦」より。
ひとつの忘れられない光景がある。昨年の3月、A級順位戦の最終局の日の出来事だった。
私はその日、名人だった羽生と一緒にNHKの大盤解説の仕事をしていた。例の『将棋界の一番長い日』というやつである。最終戦を5局同時にひとつの画面で解説するわけだから、解説の棋士にとっては一番目が回る日でもある。しかし、自分でいうのもなんだが、羽生と私のコンビは最強であった。次から次へとスイッチする画面に我々は実によくついていった。口も頭もよく回った。もちろん強い棋士というのは手が早くよく見えるわけだが、手が見えてからそれを口にするまでの時間には個人差がある。我々は口と頭の動きの連動がいいタイプなのだ。
夜中になり、日付が変わった。当然疲れてはいたが、充実した仕事ということもあり、羽生は上機嫌だった。
森内が島に勝ち、名人への挑戦を全勝で決めた。直前に竜王戦でストレート負けを喫して、また今現在第53期王将戦で1-3と自分を追い詰めている最強のチャレンジャーである。だが羽生はそこは棋士になって20年選手、まあベテランともいえる。番組の中ではさらりと流した。
「まあ出てくるべき人が出てきたという感じですね」
そこにNHKのスタッフが来ていった。
「今から森内さんがスタジオに来るそうです。よかったら羽生さんとツーショットでやってもらえませんか」
それを聞いた瞬間、羽生の顔が見事にゆがんだのだった。そしてきっぱりと「いや闘う相手なので」と断った。
羽生は昔から心の動きが表情に出るほうである。特に、嫌な気分になった時にそれは顕著である。若い頃、ふざけて品のない冗談をいったり、一度いい出したら絶対にきかない頑固な性格につっかかった時などによくしかめっ面見せたものだ。しかし、若さという角が取れ、長いこと露骨な表情の変化は見せなくなっていた。しばらく見ることのなかったその顔が出たのだった。
ああ、意識しているんだなあ、と思った。もちろん当時の状況はナーバスになるだけのものではある。なにしろ次から次へと負かされている相手が、さらに挑んでくるのだ。だが、それでも羽生が、あのような余裕のないそぶりをあらわにするのはちょっとした驚きだった。
森内がスタジオでカメラの前に立っている間、我々はふたりで廊下の隅のパイプ椅子に腰掛け、お茶を飲んでいた。会話といえる会話はなかった。疲れきった表情は隠しようもなく、寒くもないのに縮こまっている。私の紙コップにお茶がなくなると、黙ってペットボトルからついできた。羽生が私にこういうことをしてくれるのは珍しいなと思った。
なぜここ1、2年の間に森内は羽生を圧倒し、そしてまた羽生が盛り返して来たのか、それを考える前に、まずは基本的なことのおさらいから入ろう。
(つづく)
——–
何度も思うことだが、このような文章は、世の中で先崎学九段しか書けない先崎学九段ならではのもの。
じっくりと味わいたい。