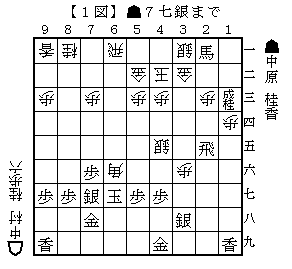将棋世界1986年4月号、スポーツニッポン新聞社の後藤大介記者の「第35期王将戦を盤側に見て ガケッぷちに経つ中原」より。
棋界の”天下人”中原誠王将に”新人類”中村修六段が挑戦する第35期王将戦七番勝負は、誰もが予想しなかった中原開幕3連敗という異常事態のうちに第4局を迎えた。中原が敗れると第5期の大山康晴王将・名人-升田幸三八段以来、30年ぶりに”名人が指し込まれる”という大事件になる。指し込み制というのは、将棋界に7つあるタイトル戦のうち王将戦だけに認められている恐怖の制度で、あまりの厳しさに現在は”4連勝して指し込んだあとも当分香落ちは指さないで終了する”と規定が柔らげられてはいるが、時の名人にとってこの上ない屈辱であることに変わりはない。
中原のカド番という思わぬ事態で第4局を迎えた対局場の彦根プリンスホテルでは、前夜祭開幕前から緊張度がぐんぐんエスカレートしていった。「万が一、中原さんが負けたら打ち上げの席で、なんと挨拶したらいいんだろう……」「初めてお迎えする王将戦で王将・名人が4連敗で指し込まれるということになったら、”縁起の悪いホテル”とイメージダウンするんじゃないでしょうか…」主催社の担当役員やホテル上層部はオロオロ、ピリピリ緊張しながら両対局者を迎えたのだった。
第3局の千日手指し直し局同様、中原は序盤から攻勢に出た。だが中村の反発はもっと凄い。指しかけ直前△6七歩成と王手をかけた。「タイトル戦史上初めてではないか。観戦歴40年の私の記憶にありません」と観戦作家香取桂太氏が断言する”王手をされた局面での封じ手”というハプニングもあって取材本部は一日目から目の色が変わった。
”23歳の新王将誕生!”を当て込んだ、NHK、TBS、MBS、地元テレビ局、共同通信や地元紙、週刊誌、ヤング誌、将棋専門誌など押しかけた取材陣もフィーバー気味で、それらのカメラがみなあからさまに中村だけを狙うアングルをとるので、盤側としてはハラハラしっぱなしの二日間だった。
車で5分ばかり離れた近江プラザホテルで行われた桐山清澄棋王による大盤解説会も大人気だった。150くらいしか席のない会場に200人を超える熱心なファンが詰めかけ、取材本部の山川次彦八段と桐山棋王の電話のやりとりが会場にナマで流されて臨場感を高め、対局場見学で満足度は最高のはず。それも第4局の勝負どころとなった昼食休憩再開後だった。担当者が「今から観戦のファンを入れますのでよろしく…」と対局者に伝えると「うわぁ、こんなときにやるんですか。対局者が可哀想…」記録係の神崎二段が思わず洩らしたほど緊迫した局面だった。
対局場見学は初めての人が多かったようで、多くのファンは雰囲気に呑まれたように息をのんで座りこんでいた。係員が声をしのばせて「時間ですからお引きとり下さい」と何度伝えてもほとんど馬耳東風、一人一人背中を押すようにしてご退去願う始末だった。
「なんや、いっこも指さへんやないか…」対局場を出てゾロゾロ歩くファンの中の一人が不満気な声を出したが、とても指せるような雰囲気でも局面でもなかったのだ。
事実、昼食再開後、中原に最強の受け▲7七銀とぶつけられて、正念場の読みに沈んでいた中村は、ざわめきで読みの集中力をプツンと中断され、ファン退場後しばらくして△4四角と引いたが、その一手あたりから勝負の流れが変わっていったのである。
中原は指し込み制度が残っていることをうっかり忘れていたらしい。第一日の封じ手後、自室に引き上げて「王将が封じ手で王手かけられちゃったよ」と笑いながら余裕を見せていたが、そのあとで対局規定を読み直して指し込み制に気づいたようだ。二日目は朝から表情が一変していた。午前中、中村の反撃に挑戦者ややよしと評されたころには、厳しさを通り越して凄まじい形相と表現したくなる顔つき。中原のこんな凄い顔を見たのは本当に初めてだった。このとき、中原は20年の棋士生活で、初めて断崖絶壁に追い詰められた気持ちになっていたのだろう。恐らくは、4年前、9年間保持してきた名人位を加藤に奪われたときより切羽詰まった気持ちだったのではないか。
午後5時過ぎ、中原の▲2一飛成で大勢は決した。だが中村は粘りに粘る。「ここであっさり投了したら、流れを変えてしまうかもしれない」
神経質そうにマユを寄せ、合掌した手で額を支えて瞑目する。盤上と駒台の持ち駒の間を視線が何度も往復した。今シリーズ、クールに通してきた新人類が初めて見せた苦悶の表情だった。残り少ない持ち時間を注ぎ込んで、起死回生の勝負手を模索したのだがが…。
残り10分。「何分から秒ヨミますか…」神崎記録係の声に「3分から…」と短く答えた中村の声がノドにひっかかるようにカスれた。秒読みが始まった。中村の瞳から急速に光が去っていった。対照的に中原の顔が、いつもの温かさに溢れた表情に戻っていた。
中原は第一のカド番をしのいだ。だが危機が去ったわけではない。無死満塁が一死満塁になっただけだ。いや、もっと厳しく、王将位防衛までには前人未到の三つの関門が残されている。「第5局に中原が勝ったら、流れが変わったとみていいね」と立会人の丸田祐三九段。
昨年、3年ぶりに名人位に返り咲いた一局と同じ琵琶湖をのぞみながら、本シリーズ初の白星をあげた中原、将棋界に前例のない大逆転劇への挑戦がつづく。長く遠い道のりである。
—————
王将戦の指し込み制は、七番勝負で4連勝した場合に指し込みとなり、タイトル防衛(奪取)が決まった後も、王将が香を落として一局指す、というまるで罰ゲームのような制度なのだが、後藤大介記者が書いている通り、「4連勝して指し込んだあとも当分香落ちは指さないで終了する」という規定が併記されているので、4勝0敗で勝負が決まっても香落ち戦が指されることはない。
とはいえ、名人が指し込まれるとなると、世が世なら香を落とされて名人が下手にならなければならなかったのだから、とても耐え難い状況だ。
中原誠十六世名人が凄絶な表情で指していたのは、非常に気持ちがわかる。
—————
中原誠十六世名人がそのような事情、中村修六段(当時)はこの勝負に勝てば王将位獲得。
記録係の神崎健二二段(当時)が「うわぁ、こんなときにやるんですか。対局者が可哀想…」と言うほど、緊迫した対局室。
その時の局面が1図。
見ただけでハラハラする、どちらも持ちたくない局面。
そのようなタイミングで現れた対局場見学ツアーの多数のお客様。
—————
「中原に最強の受け▲7七銀とぶつけられて、正念場の読みに沈んでいた中村は、ざわめきで読みの集中力をプツンと中断され、ファン退場後しばらくして△4四角と引いたが、その一手あたりから勝負の流れが変わっていったのである」とあるが、後の検討では、△4四角以外の手は思わしくなく、1図の時点で既に流れは先手に傾いていたという。
—————
中原誠十六世名人は、この対局に勝って、続く第5局も勝つ。
しかし、丸田祐三九段の「第5局に中原が勝ったら、流れが変わったとみていいね」の予想があったものの、第6局は中村修六段が勝ち、中村修王将の誕生となった。
—————
「新人類」は1986年の新語・流行語大賞に選ばれた言葉。
今見ると、非常に奇異な浮き立った言葉に思える。
新語・流行語大賞となった言葉ほど、年数が経つごとに劣化が激しくなっていくものなのだろう。
—————
中村修王将誕生の翌朝の写真。雪と戯れる王将と書かれている。(将棋世界1986年5月号、撮影は中野英伴さん)