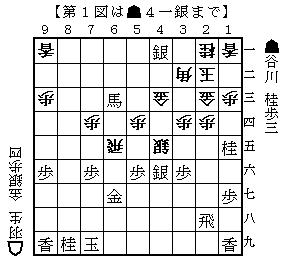昨日の記事の10ヵ月後の話。
先崎学八段の2001年に刊行されたエッセイ集「フフフの歩」より。
郵便受けに「週刊将棋」が入っていた。一面は今年の十大ニュースだった。一位は谷川永世名人誕生。小見出しは「大コウジ完成」だった。浩司と工事。昔、酔った勢いで、谷川さんに谷川道路工事先生といってしまい深く反省したことがあったっけ。
二位が羽生。三位が矢内さん。パラパラとページをめくった。順位戦中間展望、今年のこの一局。谷川長男誕生。のんびりした記事がつづく。紙面を閉じて、裏一面を見た。そこに、その記事はあった。
佐藤康光君が王将戦の挑戦者になってインタビューを受けていた。
見出しは、勝ちたいと思っています。そりゃそうだ。とりあえずは残留が第一目標。なるほど相変わらず謙虚だな。後手番で横歩取りを指すようになって戦法のレパートリーが増えた。ふむふむそうか。将棋の勉強は昔に比べると減りました。そうだよなあ、独身生活を謳歌していると楽しいことも多いもんなあ。モテ光君だしなあ。
問題はその後である。次のくだりで、平和で優雅な僕の一日は無残に崩れた。ちょっと長いが引用させて頂く。
-ところで、とてももてているといううわさがありますが(笑)。
「(笑)いや、そんなことないですよ。全然そんな、とんでもない。よく誤解されるんですけれど。まあ、先崎よりは、という程度で、郷田さんとか森内さんにはとても及ばないです」
-でも、もてるでしょう?
「いや、とんでもないですよ。僕は結婚願望があるほうですから、もてていたらとっくに結婚しています」
な、なんじゃこりゃあ。僕は激しく動揺した。脈が早くなっていくのが分かった。あわてて次の煙草に火をつけた。
康光君がモテ光君なのはいい。自分でモテルといったのだし、事実、先崎データサービスの極秘調査によっても明らかである。それは認める。だからといって、社会の公器たる「週刊将棋」の、しかも裏一面でダメを押すことはないじゃないか。
もう一度よく読む。そうすると様々なことに気がついた。佐藤君は、先崎よりモテルが、郷田、森内よりはモテないという。必然的に郷田、森内は、先崎よりも、はっきりとモテルといっているわけである。ワシャ最下位かいな。
しかもだ、次に、自分が、いかにモテないかを語っている。この狙いは明らかである。自分がモテないということによって、先崎の地位をさらに貶めようというのに違いない。ゆ、ゆるせん。
ベランダに腰かけて、僕はじっと腹を見る。モテ光君にそのあなかじゃもてないですよといわれた腹である。その中は煮えたぎっている。
男としてここまでいわれて黙って引き下がるわけにはいかない。といってこればっかりは”勝負”ということもできないし、どうすることもできない。
どうすることもできない局面で、じっとしていられないのが僕の性分である。共通の女友達の所にTELしてみる。
「もしもし先崎ですが」
「あら久しぶり、どうしたのこんな昼間から」
「いやちょっと聞きたいことがあるんだけど、いやさ、すごくくだらねえことなんだけど」
「なに」
言うべきかどうかさすがにためらった。恥ずかしかった。
「あのさ、俺と佐藤康光君と、どっちがモテルかなあ」
「はあ、どうしたの、なにかと思えば」
「はっきりといってくれ、これは俺の人生にとって、とても重要なことなんだ」
「なにそれ、本当にどうしたの、ははあ、一人の子を二人で好きになって、ってやつね。ようするに」
「三角関係。自分で言ってどうするんだ、そうじゃない。プライドの問題なんだ」
「ますます珍しい。先チャンからプライドなんてきくとは思わなかったわ」
「答えにくいならこうしよう。ここに郷田、森内といれて、四人で、誰がモテルと思う」
「郷田君かなあ、ハンサムだし」
これは予期していた答えだった。彼女は郷田ファンなのだ。
「佐藤君はどうだ」
「経済力はありそうだし、モテルと思うわ、食いっぱぐれは無さそうだし、立派な家に住めそうだし」
「三十女のドライな意見はいいんだ。俺はどうなんだ」
「三十女とは失礼ね。まあ本当だけど。いったいどうしたのよ。本当に。先チャンは話していて面白いし、交友が広いし、要するに各人各様ってことね。そんなのに順番つけるのやめなさいよ」
その台詞は佐藤君にいってくれ、声が喉元まで出かかったがやめた。
受話器を置いて横になる。佐藤君の勝ち誇った顔が浮かぶ。今頃、愛車の三菱FTOで颯爽とドライブしているのだろう。横にいるのは彼好みのお嬢様タイプ。特技はピアノ。口説き文句は僕の部屋でバイオリンの伴奏をしてくれないか。
考えているうちに阿呆らしくなってしまって、そのまま寝てしまった。
—–
棋士が負けず嫌いであることがよくわかる。
あるいは、極論すれば、棋士のOS(オペレーティングシステム)は”負けず嫌い”とも言うことができるだろう。
先崎八段の「一葉の写真」にも次のように書かれている。
1990年代初頭の話。
観戦旅行の目的はというと(当然将棋の勉強が主なのだが、それだけではツマラナイでしょう)、バックギャモンをすることである。
(中略)
とにかく、ところかまわず、なのである。二つ折りにしてコンパクトになるため持ち運びが便利で、電車のなかから駅のホームなど、場所などまったく関係なく四つのサイコロを振りまくる。森けい二九段が指南役で、先崎、羽生、郷田の三人組が同じくらいの実力なのだが、みんな自分が一番うまいと思っているらしく、また、三人とも負けず嫌いのため、その負けたときの口惜しがりようは大変なものである(羽生の顔がゆがむのは、見ていてじつにおもしろいですよ)。
棋士にとって、将棋の対局の時が、最も喜怒哀楽の表情を出さない時なのかもしれない。
—–
「僕の部屋でバイオリンの伴奏をしてくれないか」という口説き文句は、かなりな傑作だと思う。
ところで、最近では将棋ファンの女性が増えており、8月16日の東京スポーツでは『若い女子の間でブーム!いま「将棋女子」が増えている』という特集を掲載している。
中倉彰子女流初段と中倉宏美女流二段がインタビュー されている。
私はこの記事を読むことはできなかったのだが、写真を見てみると、”将棋女子に大人の王手”、”親子で始めれば娘との会話も続く”など、男性への将棋普及につながるような、東スポならではの切り口の面白い記事のようだ。
東京スポーツに敬意を表して、”将棋女子に大人の王手”をかけられるような口説き文句をいくつか考えてみた。
「僕の部屋で、一緒に順位戦中継を見てくれないか」
「僕の部屋で詰パラを一緒に解かないか」
「9月になったら、二人でウェスティン都ホテル京都へ王座戦第2局を見に行こう」
「僕たちで穴熊のような暖かい家庭を作らないか」
「四間飛車を指す、君が好きだ」
「君のためなら王手飛車取りを掛けられても構わない」
・・・あまり破壊力はなさそうだ。