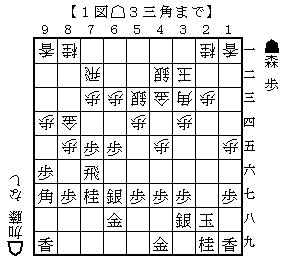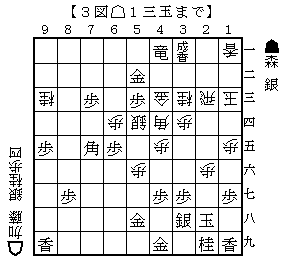森雞二九段を語った名文章。そして、見えてくる森雞二九段の個性と魅力。
将棋世界1986年10月号、中平邦彦さんの「痛恨の一局(森雞二九段の巻)」より。
司馬遼太郎さんの紀行文に『竜馬と酒と黒潮と』というのがある。土佐人の気骨を見事にとらえた名文である。
高知城下の飲み屋の二階で酒を飲む。
大座敷を屏風で仕切った所で、こういう場所が土佐人に好まれる。だが、こうした席につきものの三味線の音や唄がない。
あるのは議論である。
これをサカナに盛大に飲むのである。背中合わせの屏風の後ろからすさまじい議論が聞える。中身は何か。
「犬が利口か、猫が利口か」
なのである。議論のたねはなんでもよく、たねがなければ杯は大がよいか、小がよいかでもいいのである。しかしその議論は、まあまあという妥協が決してない。あくまで黒白をつけねば収まらない。明快でなければならない。たとえ夜を徹しても。
だから高知は弁護士が多い。人口密度比で日本一である。理由は簡単で、民事訴訟が多いからだ。県民たちは互いの議論で片付かぬとなると断固法定へ持ち込む。黒か白か、生か死か、勝ちか負けか、という、あいまいならぬ、抜き差しならぬ決着をはなはだしく好む。
この性格が幕末の尊皇攘夷運動になり、脱藩になり、自由民権運動になり、今の日本一過激な教員組合運動と、逆の日の丸校長との対抗となる。
土佐人の行動が一種異様に見えるのも、その議論好きの言葉によることが多い。ある行動、たとえば「脱藩をする」と土佐人が言葉を吐くとする。するかしないか明快になりすぎ、途中で気が変わってももう遅く、自分の前言の手前、脱藩してゆかざるを得ない。
幕末、最も多くの脱藩者が出たのは土佐藩であった。彼等の行動はその言語のごとく鋭利であり、そのために最も激烈な行動に参加し、その時代、個人参加の志士という立場で死んだのは土佐人が最も多かったという。
なぜそうなのかの定説はない。
(中略)
土佐は僻地だ。ところが普通はこれに劣等感を抱くのに、土佐人は奇跡的なほどこれを持たず、自慢をし、明るい。
酒の一人当たり消費量日本一の土佐は、酒による事故もまた日本一だ。泥酔して車にはねられたら、普通は、だから言わんこっちゃないと言われるが土佐は違う。そこまで飲んだか、痛烈なことよと思う。
司馬さんはこう書いている。
『土佐人が他の日本人ときわだってちがうところは、かれらの意識をどういう暗い意識が通過しても、出てくる瞬間には化学反応をおこしたように明るくなっていることだ』
鋭い言辞を吐くが、その論理的態度は乾ききっており、あっけらかんとして楽天的なのである。
前置きが長くなった。
しかし森雞二九段のことを語るには、土佐人を語らねば始まるまい。森は土佐・中村の出身である。
1
昭和53年春。
名人戦第1局の朝、挑戦者の森は青々と剃髪して対局場に現れた。日本中の将棋ファンはあっと思ったが、一番驚いたのは中原名人だったろう。
つるつるの剃髪に和服姿、精悍で鋭い眼光の森は異様な迫力があり、さすがの自然流中原も動揺したようだった。そして将棋もいいところなく押し切られた。
この名人戦はテレビカメラが初めて入った記念すべき対局だった。それが早速茶の間に流された。ブラウン管から突如、森のあのかん高い声が流れてきた。
「中原さんは強くない。ええ、やりやすいですねえ。これまで負けた人は勝手に転んでいるんですよ」
そう言って不敵に笑った。
カメラは苦悶する名人のアップを映し、その表情にかぶせて森の舌鋒が追い打ちをかけた。
「相手が長考すると、うれしくなっちゃうんですよ」
テレビを見ながら、やるなあと思った。それは戦慄的で、感動的であった。男が男に勝たんとし、全身全霊をぶつける猛々しさを、美しいと思ったからだ。そしてこのとき、ああ、これは土佐人だなと感じた。
挑戦者になったとき、森は中原将棋を600局調べ尽くした。きっと「お前は中原に勝てるか」と自分で議論したと思う。そして「勝てる」と黒白をつけたのだろう。だからそのまま口に出した。
剃髪はどうか。
これも明確な理由がある。名人リーグ戦。新加入の森は5連勝と突っ走ったが、6局目に必勝の将棋を有吉に負けた。このとき、森は心に決めた。
「俺はおっちょこちょいでだめだ。もし名人に挑戦できたら頭を剃ろう」と。それは軽忽を自ら戒める決心だった。人があっと驚く奇矯とも思える剃髪も、森自身にとっては自然の行動で、やると決めたらやらざるを得ない行動だったのだ。
鋭利な言辞と、そのために生じる激烈な行動。前述の土佐人の気質がそのまま出ているではないか。
だが、勝負はそんな森の思惑を外れ、結果は4勝2敗で名人の防衛となった。後日、森は語っている。
「あの七番勝負は2局目で事実上終わっていた。勝ってる将棋を、催眠術にかかったかのような状態で落とし、自分がいやになってしまった」と。
あれは自分に負けたのだ。名人は動揺の振幅が小さいが、自分は次に響く。技術はすれすれだが、俺はまだ精神修行が足りなかった。
―では、名人に勝つにはどうするの、と聞いたら
「精神力を高めるといっても、あれは不安定でね。坊主でも悟らないというぐらいだから当てにならない。だから技術を上げる以外にない。これから香一枚強くなればいい」
と言った。
土佐人は無神論的であっけらかんとし、暗い面をすぐ明色化してしまう天才だと司馬さんは言った。挑戦のときの猛々しさと、敗れたあとのうらやましいほどの明るさと。
2
昭和57年。
将棋界は大激動を迎えた。不動の大名人とされた中原が加藤に名人位を奪われたのである。
そのショックに追い打ちをかけるように、彗星のように現れた21歳の谷川が加藤名人に挑戦した。
名人―。
このたった二文字の称号にこめられた重さ。名人になるために棋士は生きてきたのだ。だが名人ははるか遠くにあった。それなのに、加藤が奪い、少年のように若い八段が挑戦をする。かつて名人に挑戦し、届かなかった棋士たちの心境は複雑に揺れた。森もその一人であった。
東京、湯河原、蒲郡、熊本、京都、箱根。
名人戦のある所、すべてに森の姿があった。立会の仕事ではない。じっとしておれず、自ら対局場に足を運んだ。熱にうなされたように。
谷川が3連勝したあとの第4局、熊本で谷川は無謀ともいうべき強攻を試み敗れた。このとき控え室にいた森は「もしこれが成功したら俺は将棋なんか指せなくなる」と叫んだものだ。
その夜、私の部屋に押しかけてきた森は、部屋中のビールとウイスキーを飲み干し、話を続けた。
「将棋界は生ぬるい。弱い奴が得をしている」と言い、「敗者には何もやるな」と叫び、「月給制をなくせ。食えなかったら土方しろ」と怒り、「名人をとったら中村に帰るぞ」と何度も言った。
飛行機嫌いの森が土佐に住めると思えないが、もし名人をとったら実行するかもしれないと思った。
「名人か。ああ、俺も名人が欲しいよ!」
と森がわめき、疲れて黙り込んだころ、夜は白々とあけていた。そして森は九州から東京まで一人で汽車で帰って行った。ひどい宿酔いだったはずだ。
最終局の箱根、花月園。ついに21歳名人が誕生し、対局場は嵐のようになった。
二人の顔を見るんだと言っていた森は、なぜか控え室から一歩も動かず、ひっそりと座っていた。深い衝撃とともに、強い決意があったのではないか。
―ようし、今度はおれの番だ、と。
3
以上が伏線である。そして第42期名人戦挑戦リーグが始まったのである。森は、すさまじい闘志でリーグを戦った。まなじりを決していた。
(中略)
6局戦って5勝1敗は、加藤とともにトップであった。あとに4勝2敗で中原、大山、森安が続いていた。
森と加藤は第7局にぶつかっていた。これに勝った方が断然有利になり、ぐいと挑戦権に近づくのである。
昭和59年1月23日。
15年ぶりという2回の大雪に見舞われた東京だったが、その混乱もようやく収まり、この日は名残の雪がある程度だった。加藤は朝9時35分に千駄ヶ谷駅を降り、凍てついた道に用心しながらゆっくり連盟に歩き、10時10分前に到着した。
このときすでに森は対局室に居て、床の間の軸をにらみつけていた。傍にはトレードマークの4合ビンのミネラルウォーターを5本並べて。
神楽坂に住む森は普通、9時20分に家を出るのだが、この日は9時に出てきた。気合いが入っていた。前夜は早めに寝たから睡眠は十分だった。しかしこれが必ずしもいいとは限らない。
睡眠不足の場合は妙手も指さないし大悪手もやらないが、睡眠をとりすぎると手が見えすぎて余計なことまで考えてしまう。早く勝とうとすることがある。
駒箱をのぞいた加藤は、いつもの駒に変えてくれと注文をつけた。森は、またいつもの癖かというようにニヤリと笑った。それから加藤の顔を見ながら「さあ!」と気合いを入れて両手を左右に伸ばした。ゴングが鳴る寸前のボクサーのようだった。
先手は森である。
ノータイムで飛車先を伸ばす。ひねり飛車の採用は1週間前から決め、過去何年かの棋譜を調べ済みであった。だからぐいぐい飛ばした。
だが、加藤はいつものように序盤から長考が目立ち、時間はどんどん経っていった。
1図は加藤が△2二角を△3三角としたところ。次に森の▲5八金左を待って△4四角としたのが慎重。すぐに△4四角は▲4六歩△同歩▲同飛がある。
この△3三角に1時間の長考をし、残りは早くも1時間になっていた。加藤の長考の間、森は記者室にいてモニターを見、「もっと考えろ。考えて時間を使え」と念力をかけていた。
4
(中略)
加藤はこのときもう残り5分。秒読みが始まっていた。一手指すと窓際に行き、窓をあけて大きく息を吸い込んだ。
とたんに森が指す。すると加藤はあわてて戻って指す。森はまだ3時間以上残しているのに、加藤に考えさせまいとしてか、負けずに早く指す。そして、動作の方も加藤に負けず、立ち上がって空手のような仕草で「ヤァーッ、ヤァーッ」と気合いを入れた。
3図からの指し手
▲3二銀△2四飛▲4三銀不成△5五角▲3九玉△4三銀▲同竜△2八銀▲4八玉△2七歩成▲6六銀△3八と▲同金△2九銀不成▲3九金△2八銀▲5五銀△3九銀不成▲5九玉△2八飛成▲3三竜△2三金(図)手順は長いが、ここの手順は勝敗に直接関係ない。
森の▲3二銀では▲3二竜の方がわかりやすかったが、森の勝勢はもう動かない。なにしろ銀1枚をただで取っている。
むしろ勝負のアヤは森の心理の方にあった。
加藤は△5五角になけなしの1分を使い、とうとう1分将棋になったが、もうずっと前から秒読みだったし、1分将棋など手慣れたものだった。
危険な兆候は、むしろ2時間半も時間を余している森の、意識過剰とも思える闘志のほとばしりである。
清水孝晏氏の観戦記をひく。
『(加藤が58秒で指すと)対する森も間髪を入れずに切り返して立ち上がる。手洗いに行くのかと思うと記録係の後ろに回り、秒読みの時計を覗き込む。1秒でも過ぎたら”時間切れだ”と言おうというように。
加藤が指すとパッと座布団に飛び移り、サッと指し、また記録係の後ろに戻り、両手を伸ばしたり覗き込んだりと、燃えに燃え、首筋のぬれ手拭いもポッポと湯気を立てている』
光景が目に浮かぶようだ。
森の感情は熱く、アドレナリンは多量に放出されたろう。睡眠は十分、体調も万全で、いくらでも手が見える。こういうときこそ危険であった。
5
4図がそのハイライトだ。
4図からの指し手
▲4三竜△7六桂▲7九角△5七桂▲同角引△同歩成▲同角△2四歩▲2五歩△7七角▲6八桂△4八銀打▲同金△6八桂成(投了図)
まで、136手で加藤前名人の勝ち森はここで手洗いにでも立つべきだった。記者室で一息入れてもよかった。だが、早指しを続け、気合いで圧倒し、闘志のかたまりになっていた森はノータイムで痛恨の一手を指してしまう。
▲4三竜が手痛い敗着となった。自分で転んだといってもいい。
ここは▲2五桂△同竜(△1四玉は▲3二角で勝ち)▲4三竜で勝ちであった。しかし、森は先に▲4三竜でも同じだと思っていた。
▲4三竜△7六桂▲2五桂に△同竜の一手と思い込んでいた。それなら▲3九角で勝ちである。
ところが、あとからの▲2五桂では△1四玉と逃げられてしまう。全部わかっていながら、つい軽く手順前後を犯したのである。
▲4三竜と指した瞬間、森はその△1四玉に気付き、あっと思った。頭にカーッと血が昇り、それから急に寒気が襲ってきた。そして次にやってきたのが耐え難い自己嫌悪であった。
秒読みの中で加藤もこれに気付いた。太い指が駒台の桂をつかみ、盤が揺れる力強さで△7六桂が打ち下ろされた。
加藤に△7六桂と打たれ、森は▲7九角と打つのに8分考えている。この8分間に、森は自らに向けて、ありとあらゆる罵詈雑言をあびせたのではないか。
最後は即詰みとなった。そしてこのとき、森が1年がかりで執念を燃やし続けた名人位の挑戦は、ひらひらと逃げていった。
感想戦は2時間に及び、森は「アホ、バカ、トンマ、間抜け」と自分に悪態のかぎりをついた。終わったときは夜中過ぎ。森は「今夜は眠れないよ。帰れないよ」と言い、目で飲みに行く仲間を探したが、みんな気の毒がって首をすくめてしまった。
森はこの期、結局6勝3敗で終わり、谷川名人に挑戦したのは7勝2敗の森安八段だった。
この敗戦の痛みは尾を引き、米長に挑戦中だった王将戦の敗戦を含め、過去に経験のない7連敗を喫するのである。
6
「神様が鉄槌を下したんだ。相手に考えさせたら損だという邪心が入った。姑息な考えが入ったのが敗因だった」
この将棋を想い出しながら森は言った。
―その夜はどうしたんです?
「仕方ないから帰って寝たと思うよ。負けて酒飲むと悪酔いするからね」
―眠れたの?
「負けたときは自分が悪いのだから怒ったってしょうがない。一晩寝ると、負けたことも、いやなことも忘れてしまうよ」
この局の解説を聞いたのは昭和61年4月だった。名人は中原が取り返し、挑戦者は63歳の大山であった。森は九段になっていた。
「やはり名人位が頂きたいね。あと2、3回、七番勝負に出たいよ。前のときは2局目が勝負だったのに負けた。この対加藤戦もそうだけど、はしゃぎすぎがいけない。一番の敵だね」
―大山さんが挑戦したけど……
「うん。俺は今度の順位戦で挑戦者になればいい。まあ見とってくださいよ」
そう言って大きなカバンを持って立ち上がった。なんでも阿佐田哲也さんらと一緒にニューカレドニアにハレー彗星を見に行くんだそうな。
その後ろ姿を見送りながら、また司馬さんの言葉を想い出した。
―どんな悲惨な話でも、土佐人にかかったら、からりと明るいものに変わってしまう。
森にとって、痛恨の一局は笑いながら話せるただの一局にすぎない。悔恨の黒白は、もうあのときに済ましているから。
森の愛読書は『竜馬が行く』である。
—————
高知県出身の方が皆が皆、司馬遼太郎さんが書いているような性格とは限らないと思うが、一つだけ言えることは、森雞二九段は司馬遼太郎さんが考える土佐人の気風に非常に近いということ。
—————
森雞二八段(当時)が名人戦で剃髪にした理由も述べられている。
以前から決めていたことであり、名人戦での挑戦が決まった以降は、いつ剃髪を実行するかという段階であったことがわかる。
—————
『(加藤が58秒で指すと)対する森も間髪を入れずに切り返して立ち上がる。手洗いに行くのかと思うと記録係の後ろに回り、秒読みの時計を覗き込む。1秒でも過ぎたら”時間切れだ”と言おうというように。加藤が指すとパッと座布団に飛び移り、サッと指し、また記録係の後ろに戻り、両手を伸ばしたり覗き込んだりと、燃えに燃え、首筋のぬれ手拭いもポッポと湯気を立てている』
この対局の光景が凄まじい。
究極の時間攻めと、秒読みの相手へのウルトラプレッシャー。
この場にいたら、ハラハラを通り越して、見ているだけで胃から血が出てしまうのではないかと思えるような凄絶な闘い。
—————
時間攻め(秒読みの相手に考える時間を少しでも与えないよう、自分の手番でも超早指しをすること)をすると、時間攻めを仕掛けた方が敗れることが多いようだ。
大事なことがある前日に、良かれと思い十分な睡眠をとった結果、余計な所に力が入り、かえってマイナスにはたらく場合もある。
普段と変わらない姿が一番良いのだろう。
—————
それにしても、森雞二九段の個性と魅力の根源が、司馬遼太郎さんの文章を通して語られると、より理解が深まる、というところが興味深い。