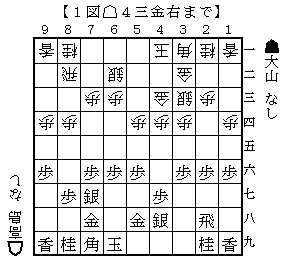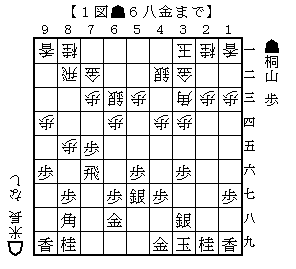将棋マガジン1986年2月号、川口篤さん(河口俊彦六段・当時)の「対局日誌」より。
升田、大山の全盛時代、二人の対決で升田が勝ったりすると、升田の取りまきが大勢来て感想戦に口をはさみ、升田にお追従を言ってから、「さあ祝杯だ」などと叫びながらドヤドヤと対局室を出て行ったりした。
取り残された大山は黙ったまま盤をはなれず、「ここでは作戦負けだ、あとは調べてもしようがないだろう」と言われたそのあとの局面を調べはじめるのだった。それは、角の王手に銀を合駒したら、とか、必至を逃れる手はないだろうか、とかの、最後の場面の研究だった。
記録係の私は仕方なく見ていたが、内心「負けと判っている局面を調べたってしようがないじゃないか」と軽蔑していた。今思っても冷や汗が出てくるが、それも無理はなかった。15、6の子供に、大山は手段を考えているのではなく、人間の心理を研究していたのだ、などの推測ができるわけがない。しかし、もしあるカンが働いて、本物の将棋はここにあるんだ、と気がつき真剣に大山の研究を見つめていたなら、もうすこしましな将棋指しになっていただろう。
(以下略)の
* * * * *
升田幸三九段の気配が濃厚に残っている場所での相手の心理の再検討。
恐ろしいまでの勝負師だ。
大山康晴十五世名人の「忍」。
* * * * *
大山十五世名人の若い頃、お客さん達が勝った対局相手を誘って飲みに行き、自分ひとりだけが取り残された経験をしている。
対局相手や状況は異なるが、このようなことがある度に、悔しさを自分のエネルギーに変えていた部分もあるかもしれない。