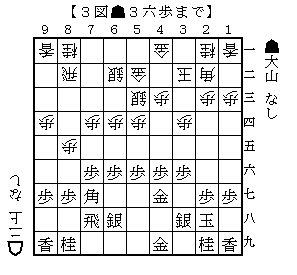将棋世界2000年10月号、鈴木輝彦七段(当時)の「師と私(上)」より。
塾生としてスタートしたその日に、将棋界の特異性に出会う。初めて塾生以外で会った人は三段だった真部さんだ。
この出会いが、私の人生を変えた。悔いはないが、会っていなければ、とは思う。強烈な出会いで、30年余の苦労の始まりであった。
見たこともないような背広と色で度肝を抜かれる。加えて相当な美男子だった。18歳の真部さんを見て、東京は凄い所だな、と思わされた。今の若手は信じられないと思うが、器械体操で鍛えられた肉体で、はち切れんばかりの若さに溢れていたのだ。
その真部さんが何を思ったのか、塾生部屋の片隅に座る。坊主頭の15歳の少年に声を掛けた。「君、将棋を指そう」と。一局五十円で始められた将棋は、一番も勝つことなく千円近く負けた。夕方になり、ポン友の椎橋さんが現れ、「さあ、女の子でも引っ掛けにいくか」なんていっている。私はズボンのポケットに入っていた全財産の五百円札を出した。岩倉具視を上にして「残りは給料が出たら払います」といった。この五百円は、母が別れた時にくれた物だ。入会金の一万円だって、着物を質屋に入れて作ってくれた。その貴重なお金を前にして真部さんは「おまえは、これしか持ってないのか」と言った。ああ、無情。ジャンバルジャンだ。
「それじゃ残りは出世払いだ」といった後、「名前は」と訊かれた。こんな状況で親から譲り受けた名前を名乗れる筈もない。恥ずかしくて「僕はミジメです」と答えた。「立心偏に参議院の参か」と呑気なものだ。この日から私の名前は「ミジメ君」になった。
何故だか、毎日真部さんは来る。
(中略)
毎日来て、私と将棋を指した。他に奨励会員はいるのに私だけ。お金は賭けなくなった。無いのを知ってるから。
暫くして、囲碁まで教えた。ルールも知らなかったのに、それでも教える。半年で井目位になったが、他の人とは打たない。少し覚えてきて、勝てそうな時に悪手に気づき待ったをした。その刹那、扇子の指先でビッシと打たれた。隠れて剣の修行でもしているのかと思った程だ。次の時は真部さんが大悪手を指して待ったをした。周りに、扇子を探したが見つからない。「待ったはいけません」と言うと「上手の置き直しといって古来から許されている」という返事だった。何でも都合よく考える人だ。
自己中心的で自分の考えることが正しいと思う人、周りの認識は正しい。ただ、見たこともないような才能の持ち主で兄貴のように慕っていた。付き合って見ると、男ぷりだけでなく、きっぷも良かった。冷たく見える一面も、弱みを見せたくない、の心理だった気がする。情に脆いのに、ストレートに見せることもない。持って生まれたスター性を御し切れていないようにも見られられた。
真部さんが毎晩のように酒を飲むようになったのは、19歳の時、東西決戦で負けてからだと思う。
(中略)
一年半で2級になり、2年目にスランプが訪れた。有段者の層が厚く、全然勝てなくなってしまった。二度目のBクラス落ちに「3級に落ちたら辞めます。才能が無いんですね」と相当に思い詰めて真部さんに話した。「奨励会に入る才能なら皆同じだよ。よし研究会をやろう」と言われ、飯野君との三人研究会が始まった。東西決戦で負けた傷も癒えて、真部さんもやる気になっていた。
週に一度、塾生の休みの日に大久保の真部さんの家の二階で指した。成績を付けたが、真部さんが9割の勝率。これから四段に上がろうという人だから勝てる訳はない。この時にB1の実力はあった気がする。しかし、終盤を読み切る姿勢は参考になった。正に目から鱗が落ちる思いだ。
(中略)
研究会は続いたが、成績はBから1勝4敗でいよいよ追い詰められる。しかし、次の例会で一局目に勝ってから12連勝して、1級からそのまま初段に上がった。3ヵ月間は殆ど負けず、2年半が経った9月の17歳だった。これは、研究会の力だろう。飯野君も三段に上がっていた。
真部さんも秋から勝ち始め、三段リーグのトップに立っていた。この期は飯野君も間に合って二人の対局もあった。
これは実力差があった。終盤で真部さんが必勝になり、持ち歩を全部テーブルの上に置いてしまった。二歩を打たなければ負けない、の意志表示だ。「あれば、さすがに悪かったな」と今でも笑う。親しさもあったからに違いない。
三段や四段に並んだとしても、数年で実力差がハッキリするものだ。並んだ時に、その差が見極められないと生き抜いていけない。C2で先崎君と並んだ、と思ってはいけない。数年後にはA級とC2に分かれてしまう。その差を判っている人だけが、何とか上がっていけるのだと思う。
初段から二段になり、三段も時間の問題、と考えたのが私の間違いだった。三段になっても上がれる三段の実力ではない。段の魔力に負けていたのだ。この時三段になっていたら、現在の実力にはなっていなかったと思う。
(中略)
一人暮らしを始めて、内向的な性格になっていた。この頃、三段になっていれば……、と書いたのは、気持ちの問題で、将来にとって良かったと信じている。48年の春に真部さんが淡路さんとの東西決戦で上がった。学生服の詰襟を着ていたが、お金も入るようになって夜飲みに誘われた。そんな生活が1ヵ月以上続き、塾生を辞める原因にも繋がっていく。4月一杯で辞める、と決まってから途方にくれていた。「何とかなる」と真部さんは言う。考えて見れば、他の奨励会員と同じになるだけだった。しかし、15歳で上京してから他の生活は経験がない。果たして、三食たべていくことが出来るのか。不安にもなるし、イライラもしていた。二人で半年続けた少林寺拳法を辞めるのとは訳が違う。
相談したかったが、三段時代からの鬱屈が晴れて真部さんはルンルン気分だ。
「ミジメ、碁を打とう」と夕食の後の碁が楽しみで誘われる。しかし、そんな気分ではない。「いやです」と初めて抵抗した。それでも手を引っ張って一階の応接室に連れていこうとする。足でも抵抗した。それが足の付根の大事な部分に触れて、真部さんの顔色が変わった。一度自分の決めたことが出来ないと子供のように怒るのが悪い癖だ。イヤだけど、きっとやるようになるんだろうな、と思ったのは再三である。この時は「何だ」と言ったまま、一階にいってしまった。
この時のことは、今までも話し合ったことはない。この3年間は、真部さんの部屋にある書籍は殆ど買って読んだ。知識の面でも傾倒していたが、18歳の多感な頃だから仕方ない気もする。私は自分のことが精一杯で、真部さんの気持ちを斟酌する余裕はなかった。真部さんからは私の気持ちを理解できたと思うが、自分から折れることはしたくなかったのだと思う。
半年位して、「元気か」と連盟で声を掛けられた。私はまだ引きずっていて「暗いです」と言った。「一人暮らしは俺も経験あるけど、内向的になるからな」と何もなかったように言う。
「まあ、一杯飲もう」と手を差しのべてくれた。私は、森信雄さんの後にトボトボとついていく村山君みたいだった。
(以下略)
——–
将棋世界2000年12月号、真部一男八段(当時)の「将棋論考」より。
本誌10、11月号にまたがり、鈴木輝彦君の「師と私」と題する文章が掲載された。まず200枚という分量に驚かされた。
その上、頻繁に私も登場させられていた。これを読んだ何人かの知人が感想を云っていたが、それぞれの立場での言葉だから表現は様々である。
1回目を読んだ後、この文章に対して何か書こうと考えたが、完結編があるとのことだから静観することにした。
そして、それを読み終えて私の頭はさらにまとまりがつかなくなっていた。
「書くべきか、書くべきに非ざるか」などとハムレットを気取っても仕方がない。若い時分には二人のお手本があった。
加藤治郎師と米長先生である。
世間的な出来事で自分では判断をつけかねるような局面で、この御二人ならばどう考えるだろうかと考えることが、ある規準になった。
今回はそうもいかず、困ったことにぞなりにけりだ。
毎日考えていたわけではないが、頭の片隅にひっかかっており落ち着かぬ。
昔から考えがまとまらない時は、本を読むことが多い。
今回は岡潔と小林秀雄の「人間の建設」という対話を読み直してみた。
昭和40年が初版の古くて新しい本である。若い頃に購入して5年に一度くらいずつ引っ張り出しては読み返す愛読書である。
あの文章に対して書くことは山ほどあるのだが、どうも手が付かない。
それを考えるヒントになる言葉がこの本の中にあった。
小林は岡にこう云う「あなたは、確信したことばかり書いていらっしゃいますね。自分の確信したことしか書いていない。(中略)いまの学者は、確信したことなんて書きません。学説は書きますよ、しかし私は人間として、人生をこう渡っていると書いている学者は実にまれなのです」。
これを受けて岡は「どうも、確信のないことを書くということは数学者にはできないだろうと思いますね。確信しない間は複雑で書けない」
とこう述べている。
私はこれかな、と思った。
もちろん、大数学者の岡潔と自分を較ぶべくもないが、私も将棋指しの端くれ、少しは理解できた気になれた。
「確信しない間は複雑で書けない」
私が今、書けないのは確信していないからであろう。
もうひとつ、わたくしが入ってしまうために書けないことを自覚できた。
私と鈴木君のつき合いは30年にも及ぶ。それゆえ彼を書こうとすると知らず私心が入り込んでしまうようだ。
そういう、しがらみを抜きにこの問題を考えられるようになった時、自然と公平なことを書けるようになるだろう。
私事に近い話で読者には興味が湧かないかもしれないが、せめてこれくらいは表明しておかなければならぬとの気持ちで、敢えて記した。
(以下略)
—————-
真部一男八段(当時)がどのようなことを感じ、どのようなことを書こうとしていたのか、想像がつくようなつかないような、気持ちがわかるようなわからないような、非常に微妙なところだ。
—————-
下の写真は、1971年、タイトル戦の記録係をしている真部一男三段。
—————-
「私は、森信雄さんの後にトボトボとついていく村山君みたいだった」があまりにも絶妙な表現。