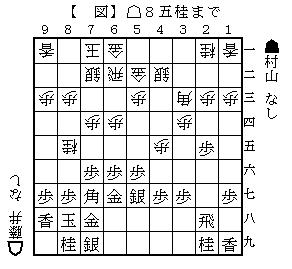将棋ジャーナル1984年1月号、才谷梅太郎さんの「棋界遊歩道」より。
K七段は大変な自信家である。今は下位に甘んじているが、その自信はいっこうに衰えない。
将棋の実力も、自分では名人級と信じているようである。石田和雄八段(当時六段)との順位戦で、こんな事があった。
石田八段は自信家が多い将棋指しの中にあって、数少ない悲観派棋士の一人である。この日は大事な順位戦の第1局目である。
ただでさえ気弱な石田氏。押し寄せるプレッシャーに、対局前から絶望感に打ちひしがれていた。
おまけに対戦相手は、自信の塊K七段である。石田氏は何日も前から、薄暗い下宿の布団の中で考えた。
その結果、得たものはK七段の性格から考えて、おだて作戦に出るのが一番と気がついた。
そして当日の朝、盤を挟んで対峙すると、さっそく作戦を実行。
「K先生、私はダメだ。絶望です。ああ、負けてください」
事実、これで作戦は半ば成功したと言ってよい。K七段の口許が、微かに緩んでいる。
勝負はやはりK七段の負け。気のいい先生なのである。
当然石田氏は、局後のサービスも怠らない。
「K先生、ずっと私のほうが悪かったけど、どの手がマズかったんでしょうか」
これでOK。敗戦の憤りは、たちまちK七段から消滅する。そして、こう言うのである。
「この飛車打ちだよ。ちょっと並べてごらん」
こんなこともあった。
K七段は口先だけというわけではなく、若かりし頃の米長現王将に、平手で連勝した実績もある。
この日の相手は、その米長氏。当時七段であった。記録係が、現在朝日アマ名人の加部康晴氏だったのも懐かしい思い出である。
米長氏、自信家の先輩に王将を譲った。小さなことでも、刺激を与えるのはマズイからである。
玉将を手にしたとはいえ、米長氏がクラスは上である。記録の加部少年は、迷わず綺麗に並んだ米長陣の歩を5枚取り、振り駒をしようとした。
さすがの米長氏も、そこまでは気が回らなかったと見える。そこでK七段から、すかさず声が上がった。
「コラ、振り駒をする時は、上手の駒でやらんかい」
どうしたらいいのか判らずに、ただ呆然とするばかりの加部少年。
* * *
K七段はスポーツも得意、らしい。本人の話では、ゴルフはプロ級、野球なども20代の若手に混ざって、攻守に渡りプロ並の活躍ができると言う。
特に足には自信があるらしい。将棋連盟野球部の中でも、強肩が自慢のキャッチャーNと、酒の席で言い争いになったことがある。
K七段曰く、
「どんないい球を投げたって、俺が盗塁したらプロのキャッチャーだって刺せねえよ」
N、すかさず反論して曰く、
「先生が10回走ったら、間違いなく9回は刺してみせる」
この対決は、当然ながら後日実現した。
たしかにK七段は、速かった。ただし、野球というゲームは、足が速いだけでは盗塁はできない。
ピッチャーのモーションを、盗む技術が必要である。そんなセオリーは、まったく無視のK七段。
ピッチャーが球をセットした瞬間には、もう走り出しているのであった。
当然ピッチャーは、軸足を外して一塁に投げる。しかし天は、あくまでK七段に味方した。
当時から一塁に入っていたHは、仲間から常に、
「肩の骨でも、はずれてるんじゃないか?」
と言われるほどの弱肩だったのである。
ピッチャーから球を受けたHは、精一杯の力で二塁に投げるのだが、それこそハエがとまりそうな山なりボールなのである。
これでは駿足のK七段を、セカンドベースで刺せるはずがない。
ベース上に仁王立ちのK七段は、『どうだい、お前達とは格が違うだろう』
と言わんばかりの顔をしている。ようするに、野球での勝負はできないのである。
「あれは完全な暴走である」
と、理を説いて聞かせるのだが、
「それなら刺してみろ」
と、開き直られるとどうしようもない。話が先に発展しない。
強肩Nとの勝負は、こうして痛み分けとなったのである。
その後、一時的に野球に病み付きとなったK七段は、セオリーを無視して走り続けた。
その姿は、あまりにも印象的で、相手チームから、「褐色の弾丸」と言われて、恐れられた時期もあるにはあった。
* * *
K七段は、女にもモテたらしい。本人の話では、これまで切った女は200人とのことである。
奨励会の若い者を呑みにつれ出し、
「きみ達は可哀想だ」
と切り出す。
若い者が、いったい何の話かと耳を傾けると、
「今のトルコは料金が高すぎる。俺達の頃は、記録料で女が抱けたもんだ」
ということなのである。
なんでもK七段の奨励会時代には、対局後、数人の悪友との赤線参りが、その日の定められたコースであったらしい。
かつて、K七段主宰の将棋研究会があった。その会のメリットは、『リーグ戦の優勝者、およびK七段に勝った者は、その日トルコに御招待』
というものであった。
血に飢えた奨励会員達は、それぞれ必死の形相で対局した。
K七段が関わった女が、すべてプロと速断するのは誤りである。
素人をモノにする秘訣は、財布にあるという。デートの間、自分の財布を女に預けてしまうのが決め手らしい。
豪放磊落を絵に書いたようなK七段にも、たった一つだけ悩みがある。肌の色が黒いのだ。
こればっかしは、どうもがいても仕方がない。
今日も将棋連盟対局室で、悪友達が噂している。
(中略)
K七段の運命的ともいえる滑稽さは、話が一段落した所へ偶然顔を出してしまうことである。
「あっ、来た来た」
これを聞いたK七段。急に不機嫌そうな表情を作り、
「また俺の悪口を言ってたな」
と、つぶやくのである。
* * *
K七段は悪人ではない。むしろ根っからの善人と言うべき人物であろう。
それは次の情景を見ても明らかである。
とある新聞棋戦。その日K七段は、原田九段と対戦していた。3対7の棋勢でも、自分が必勝だと信じて疑わないK七段。
ところがその将棋は、紛れもなくK七段の必勝であった。原田九段は力なくつぶやいた。
「さすがにダメか」
これを聞いたK七段、何か喋らずにはいられない心境になった。
「次に何やっても、飛車を2枚ぶった切って寄りですからね」
これを聞いた原田九段、投了を中止して何かをやった。
K七段はノータイムで、飛車を2枚ぶった切る。そして……
何と原田陣の王様は寄らないのである。そうこうしているうちに、渡した二枚飛車で逆に寄せられる運命が待ちかまえていた。
* * *
棋士には自信家が多い。K七段に限らず、その自信をあからさまに表情に出す人もたくさんいる。
K七段の場合、たまたまそれが一種のユニークさを伴っているだけかもしれない。
もしもK七段のような棋士が、せめて全体の1割もいたら、テレビ界への進出もこれだけ囲碁に差をつけられなかったかもしれない。
—————-
「デートの間、女性には財布を開けさせない」は古来よりの定跡とされているが、「デートの間、自分の財布を女に預けてしまう」は鬼手とも言える手筋。
全くの逆転の発想だ。
もちろん、財布の中には1日では使い切れないくらいの金額が入っていなければ迫力が出ない。
—————-
飲んでいる間、自分の財布を一緒にいる信頼できる年下の男性に預けていたのが故・団鬼六さん。
何軒も飲みに行って、その都度、財布を預かっている男性が支払いをする。
団鬼六さんの対談の時だったか将棋ペンクラブ大賞贈呈式の時だったか、団鬼六さんが「持っとって」と故・中野隆義さんに財布を預けているのを見たことがある。
—————-
K七段は、もちろん剱持松二七段(当時)のこと。
剱持松二九段は、将棋会館建設、テレビ東京「早指し将棋選手権」創設の際などに大きな貢献をしている。
また、この数年後、順位戦で羽生善治五段(当時)を破って大きな話題となっている。
日本将棋連盟野球部「キングス」の名付け親でもある。
—————-