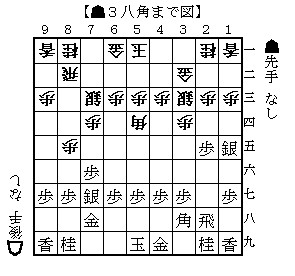升田幸三実力制第四代名人は、木見金治郎九段門下だが、将棋を鍛えてくれた実質的な師匠は兄弟子の大野源一九段だった。
(久保利明棋王・王将は、将棋年鑑のアンケートの”故人を含めて指したい棋士”で大野源一九段の名前を挙げている)
升田少年が入門した日、兄弟子の角田三男二段が飛香落ちで二番、大野源一五段が二枚落ちで五番、稽古をつけてくれた。
角田三男二段(後の八段、角田流ひねり飛車を創案)とは1勝1敗だったが、大野五段には四番立て続けに負かされ、五番目にかろうじて勝つという結果だった。
升田少年はプロの強さをはじめて知って呆然とした。
木見九段の夫人が「大野みたいになりや」と激励してくれたので、ようやく升田少年は人ごこちをつくことができた。
しかし、7歳年長の大野五段は、その後も升田少年を負かし続け、負かすたびに早口の大阪弁で叱咤した。
(升田幸三「勝負」より)
大野さんは将棋も強かったが、口も悪かった。私を負かすたびに、早口の大阪弁で、
「升田、もう田舎へ帰れ。将棋やめて百姓したほうが身のためや」
などという。これがまたくやしかった。
この、くやしがらせる、というのが、じつはわれわれの道での指導法でもあるわけなんです。
—–
東公平「升田幸三物語」より。
兄弟子の大野源一が入門したころは、まだ将棋だけでは生計が立たず、伏見町で『大音』といううどん屋を兼業。大野が出前持ちをしたこともあったが、この老松町では稽古先も増え、東京生まれでひょうきん者で、しかも将棋の強い大野五段がよく働いて『将棋所』を支えていた。升田は、小柄で色の黒い大野を、自伝などで『チビクロ』と呼んだりしているが、事実上の師匠である。大野の晩年まで最大の敬意を表し、親しくしていた。
—–
大野源一九段は東京下谷の生まれ。将棋クラブで指しているのを、たまたま遊びにきていた大阪の中井捨吉三段(後の八段)が見て認められ、1925年、13歳の時に大阪の木見門下へ入門することになる。本人は何も知らなかったが、中井三段と大野九段の父親の間で話がついてしまっていた。
(将棋世界1972年2月号の大野源一-石垣純二対談より)
大野「入門して1年半くらいウドン屋の手伝いにきたのかなんだかわからなかった。朝は六時起き、夜は遅いんですょ(寝るのは午前二時)」
(中略)
大野「問屋街でね。朝早いのは奥さんと二人で天満の市場まで材料の仕入れなんです。帰ってくると昨日出前したドンブリを取りにいき、それでやれやれと思うとそのドンブリを洗わなくてはならない。そうするともう食べにくる」
石垣「ヘエー深夜に眠って六時起きでよく身体をこわしませんでしたね。将棋の勉強などする暇がないではないですか」
大野「眠るときフトンの中で新聞将棋を見るのと、昼の二時から五時の比較的暇なときに二階へ行き、神田さん(辰之助九段)などの指しているのを見るくらいですかな」
石垣「それで強くなっていくというのはどういうことですかね」
大野「一生懸命将棋を見ましたね。強くなったもう一つは、ウドン屋をしたおかげですかな。こんなことをいつまでもしていられないということでね」
石垣「脱ウドン屋ですか。大山、升田さんなども出前されたんですか」
大野「そのときはウドン屋はやっていませんでした」
—–
大野源一九段の将棋の出発点はこのようなものだった。
兄弟子もなく、将棋を見るだけで強くなったのだから、天才といえる。
「悔しがらせて育てる」方法が大野流なのか、当時の徒弟制度の世界の定跡だったのか、どちらかはわからないが、この育て方は升田少年に受け継がれて、大山少年(十五世名人)を鍛えることになる。
升田少年は、大野五段の強力な攻めに対抗するために強靭な受けを身に付けざるをえなかった。
大野五段の鍛え方が素晴らしすぎたのか、この期間中に升田少年は大野五段の癖や弱点を十分に把握した。
そのせいか大野源一九段は、プロ棋士になった後の升田幸三実力制第四代名人にはほとんど勝てなくなってしまう。
(つづく)